カーテンの隙間から、朝日が射し込む。
布団を抱き締めてすぅすぅと眠っていた啓介は、初夏の陽射しの暑さに、ピクッと顔をしかめ、うっすらと目を開ける。
『何か…変な夢見てたような…』
思考の働かない脳味噌を回転させ、見た夢の内容を思い出そうとしたが、夢はいつも、覚醒するとかき消えていって、思い出せない。
嫌な夢じゃない、と思うけど。
少し前までは、見る夢と言ったら、子供の頃の夢だった。
いつも一緒にいた兄と、遊んでいる夢。
『おれ、にいちゃんだいすき!』
『オレも啓介のことが好きだよ』
楽しくて、嬉しくて、ふわふわと暖かい夢だった。
でもここ最近見るようになった夢は、何故か思い出せない。
それが目標も何もない、現在の自分を表しているようで、無性に苛つく。
『ガッコー行くのかったりぃ…サボッちまうか…』
半分しか開かない虚ろな目で枕元の時計を見ると、まだ少し早い時間。
啓介は布団をきつく抱き締め、二度寝を決め込んだ。
昨夜の帰宅が遅かったので、すぅと眠りに落ちる。
「―――介! おい、起きろ。啓介!」
肩を掴まれ揺さぶられて、啓介は再び眠りの淵から覚醒させられる。
「ん…アニキ…?」
「いい加減に起きろ。遅刻するぞ」
制服姿の涼介が、顔を覗き込んでいた。
「眠ィよ〜〜〜」
「遅くまで遊び歩いていたせいだろう。早く起きて、朝食を食べて支度しろ」
窘めるように言うその言葉は、叱ることしかしない父親と違って、声音が優しくて。
「うぃ〜〜〜」
仕方なしに、もぞもぞと起きる。
洗顔と髪のスタイリングを済ませ、制服に身を包んで階下に降りると、涼介が玄関で靴に足を通していた。
「アニキもう出んの? 朝練? にしちゃ遅いか」
「IH県予選はもう終わったから、当分朝練はないよ。日直なんだ。オマエも遅刻しないようにな。いってきます」
「いってらっさーい」
ちぇ、と口を尖らせながら、啓介はLDKに入っていった。
食卓に着いて、用意された朝食をもそもそと食べる。
1人で食べる食事なんて、どんなに豪華だろうと、美味しくもない。
こんな広いLDKで、他に誰もいなく、時計の秒針と冷蔵庫のモーターの音が、やたらと耳障りだ。
『あ〜ぁ…去年ならアニキも一緒に朝飯食ってたのにな…』
何だか無性に苛ついてきて、食事をかっ込むと、空いた食器はそのままに、玄関に向かう。
家の門を出て、見るは涼介の向かった、高校の方向。
目と鼻の先のその高校が、やけに遠く感じる。
着ている制服も、パッと見には変わらないのだが、涼介は高校、啓介は中学で―――去年まで、同じ制服だったのに。
啓介は理由の分からない苛立ちを内に抱えて、逆方向へと歩いていく。
ずっと一緒だと信じて疑わなかった日々が幻のように、例え一緒に家を出たとしても、目指す方向が、正反対だ―――。
この春、涼介は県下で一・二を争う進学校、T高校に首席で入学した。
小さい頃から成績優秀で、中学でもずっと一番だった兄。
そんな兄が、啓介には誇りで、憧れで―――でも、ずっと追いかけてきた背中は、とてつもなく大きくて。
追いかけ続けても追いつくことは出来なくて、いつか隣に並ぶことなんて、不可能なのかも知れない。
退屈な授業も聞かず、啓介は頬杖を突いて、窓の外の青空を眺めていた。
いつの間にか、出来ていた溝。
目の前にいた兄は、いつの間にか遙か遠くまで行ってしまった。
何でオレは、アニキと同じように出来ない?
何でオレは、こんなに出来損ないなんだろう―――アニキの弟なのに、同じ血を分けている筈なのに。
『もしかしたら、オレは貰われっ子なのかも』
『だってアニキはAB型で、オレだけO型じゃん』
子供の頃、涼介にそう言ったら、呆れたように微笑って言った。
「お父さんがA型でお母さんがB型で、その場合、A型、B型、O型、AB型、全ての血液型の子供が生まれるんだよ」
そんな風に説明してくれたけど、だからってそれが、オレが貰われっ子じゃないって証明にはならない、って聞き流してた。
《何で兄のように出来ないんだ》
《兄は優秀なのに、それに比べて弟は》
親も教師も、口を揃えたように同じ事を言う。
そんなの、オレが一番思ってる。
オレが一番知りたいのに。
何でアニキと同じように出来ないんだろう。
理由の見つからない苛立ちで、喧嘩と単車の暴走に明け暮れる日々。
そんな毎日に、嫌気が差しても、他にどうすることも出来ない、ジレンマ。
両親・周囲の期待通りに、父親の跡を継ぐべく、医者への道を目指す涼介。
それに比べ、何もない自分、誰も何も期待などしていない。
このまま、涼介も遠くに行ってしまうのだろうか。
自分を分かってくれる人間は、いなくなるのだろうか。
感情を持て余し、煙草を銜える。
美味くもない煙草の煙を吐き出し、紫煙の消える先をぼ〜っと見ていた。
「まるでオレみてぇ…」
目標も何もない、つまらない、空っぽな毎日。
単車で走り回っても、靄靄は晴れない。
オレは、何の為に、生きている―――?
今日も変わらず、自暴自棄に過ごす啓介は、美味くもない煙草を銜える理由を考えた。
そんなことを考えてしまう、理由を考えた。
答えなんて、いつも出ないけれど。
コンビニ前でしゃがみ込んで、煙草を燻らせていると、野良猫が寄ってきた。
「来〜い来い…」
ちょっと撫でてやろうと思ったけど、つるんでる馬鹿な連中のせいで、野良猫は逃げていく。
舌打ちをして、煙草をアスファルトに押しつけた。
そう、オレの周りにいるのは、ロクでもない野良犬。
ソイツらが憂鬱という名の下らない手土産を持って、今夜もやってくる。
夢も目標もないままに、今夜も夜の国道を、駆けていく―――。
◇ ◇ ◇
前橋・高崎辺りで最大勢力を誇る暴走族、紅蠍隊(クリムゾン・スコルピオンズ)の幹部に目を掛けられ、可愛がられている啓介は、持て余したエネルギーを、チーム同士の抗争でぶつけて、喧嘩に明け暮れていた。
無免許で単車を転がし、警察沙汰になることもしばしばだ。
家に散々迷惑を掛け続け、親にはとうに見放された。
叱られてばかりいた日々が遠く感じる程に、叱ることさえ、放棄した―――《アレ》はダメだ、と決めつけて―――。
あんな窮屈な家に、オレの居場所なんか無い―――。
「いてて…」
深夜過ぎ、自宅に帰った啓介は、靴を乱雑に脱ぎ捨てて、ドスドスと広い廊下を歩き、豪奢な階段を通り過ぎて、奥の階段に向かった。
ドカドカと階段を上がっていくと、自分の部屋の隣のドアが開いて、涼介が顔を覗かせる。
「何時だと思ってるんだ。父さんも母さんももう寝ているんだから、静かにしろ」
「フロア別なんだから、聞こえちゃいねぇだろ。聞こうとしねぇの方が正しいか」
そう吐き捨て、洗面所に向かう。
「オレが聞いている。遊び歩くのは勝手だが、せめてもう少し早く帰ってこい。夜中に警察から電話がかかってくるようなことはするな」
「へいへい、パクられねぇようにすりゃいいんだろ?」
水で血や泥を洗い流しながら、右から左へ聞き流す。
「そういう問題じゃない。…怪我してるのか?」
洗面所までやってきた涼介は、啓介の様子を見て、息を吐く。
「また喧嘩か。手当てしてやるから、部屋に来い」
日常茶飯事でしょっちゅう怪我をして帰ってくる啓介の為に、涼介の部屋には救急箱が常備されていた。
ベッドに座らせて、怪我の箇所を消毒していく。
「いてて、沁みる、沁みる!」
「消毒くらいで叫ぶな。殴られるよりはマシだろう。沁みない消毒薬もあるが、オマエの場合、沁みる消毒薬の方が懲りてくれるかと思ってな」
「アニキ、サドかよ? オレが痛がるの楽しんでねぇ?」
「そうかもな」
「ちぇ」
手際良く手当てする涼介を、啓介はじっと見つめていた。
呆れながらも、涼介はいつも、こうして丁寧に手当てしてくれる。
喧嘩に明け暮れる啓介を窘めながらも、ちゃんと相手してくれる。
怪我をすれば、涼介が手当てをしてくれるから、無傷で済ませられるのを、わざと怪我したりもしていた。
自分を見て欲しい、構って欲しい。
それを試したくて、アレコレと馬鹿なことをしている。
そんな毎日。
「啓介…この家が窮屈で何もかもが面白くなくて荒れるのも分からなくはない。でもな…喧嘩をするなとは言わないが、いくらオマエが強くても、いつ取り返しのつかないことになるか分からないんだ…オレに心配ばかりかけさせるな」
切れ長の瞳が、真っ直ぐに啓介を見つめる。
「アニキは…オレのコト、オヤジ達みてぇに見放さない?」
「何言ってんだ、当たり前だろ。オレ達はこの世でたった2人きりの兄弟なんだ…オレはオマエを見放したりなんかしないよ、絶対に」
優しい声音で言ってくれたその言葉が嬉しくて、啓介は子供のように涼介に抱きつきたい衝動に駆られた。
しかしいい年をしてそれはガキじゃあるまいし、とグッと堪える。
自室に戻り、キングサイズのベッドに寝転がって、啓介は天井を見つめた。
小さい頃から、涼介は啓介にとって憧れで、ずっと、涼介のようになりたいと思ってきた。
でも、どんなに頑張っても、涼介のようになれるどころか、差は開く一方で。
目指す憧れがすぐ傍にいるのに、遠く感じる。
比べられて、嫌な思いは散々してきた。
だが、比べられるのは、同じ血を引いた兄弟だからだ。
何にも変えられない、切れることのない、強い絆。
それを嬉しいと感じる自分は、マゾなのだろうか?
親や教師に見放されようと、涼介さえ自分を見てくれるなら、信じてくれるなら、それで充分だ―――。
そう、思っていたけれど。
最近、何か変だ。
涼介が自分を見て、信じてくれればそれでいい、と思いながら、《それ以上》を望むようになった。
何をどう、《それ以上》なのかは分からないけれど。
涼介のことを考えると、無性に胸の奥が熱くなる。
ジリジリと、夏の陽射しより熱い、これは一体何だろう?
『アニキみてぇに頭良くねぇから分かんねぇや…』
理由の見つからない苛立ちと、焦れた感情を持て余し、ただ惰性で繰り返すだけの日々が、意味も成さずに過ぎていく―――。
◇ ◇ ◇
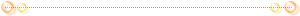
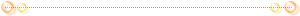
◇ ◇ ◇
秋が深まり、山が紅葉して色づいても、啓介の目には、モノクロにしか映らなかった。
季節感なんて、分かりゃしない―――暑いとか寒いとか、そんな感覚さえも麻痺してる、このカラダとココロ。
「啓介〜、オマエ全然家帰ってねぇだろ? たまにゃ帰らなくてもいいのかよ?」
倉庫に住んでる幹部のヤツが、入り浸っている啓介に、ふと言った。
「いいんすよ、帰ったってオレの居場所なんかねぇし、―――誰が待ってる訳でもねぇし」
自暴自棄に、吐き捨てる。
「―――ま、オレも勘当されてる身だから、オマエの気持ちも分からなくはねぇけどさ。ゆくゆくはオマエにチーム任せてやってもいいって思ってんだけど、やっぱ気持ちは変わらねぇ訳?」
「ずっと世話ンなってて悪ィっすけど、オレそ〜ゆ〜のガラじゃねぇんで。切り込み隊長のままでいいっすよ」
いつもの溜まり場で、新しい単車の話とか、学校で教師と一悶着起こしたとか、どうでもいいような話題を、適当に聞き流していた。
煙草を燻らせていると、群れの一角が、ざわついている。
「高橋啓介さんは、いますか?」
聞いたことのない、男の声。
啓介は気怠げに立ち上がり、歩み出る。
一見して整備士と分かる、ツナギ姿の男が、まっすぐに啓介を見つめた。
「―――啓介さん、ですね?」
「そうだけど…アンタ誰」
穏やかな容貌をしているが、一癖ありそうな、雰囲気のあるその男に、つっけんどんに啓介は返す。
「アナタを、連れ帰りに来ました」
「はぁ? 何言ってんだ? 連れ帰るって、ドコに」
「勿論、ご自宅ですよ。ずっと帰っていらっしゃらないでしょう。涼介さん―――お兄さんが、大変心配されています。オレが送っていきますから、帰りましょう」
「アニキが? 心配してるって? ハッ、だったら何でずっとオレのコトほったらかしでいるんだよ? あんな家、もう帰らねーよ。オレは一人で生きてくんだ。アンタが誰か知んねぇけど、アニキにでも頼まれてきた訳? じゃあアニキに言っといてくれよ。オレのコトなんか忘れちまったアニキなんて、もう縁切ってやる、ってな」
自分で口に出しながら、言葉に含めたトゲが、ちくちくとココロに刺さって―――とっくに忘れたと思っていた痛みが、胸を貫く。
痛む胸を押さえて、くるり踵を返すと―――男に肩を掴まれた。
一見優男なのに、掴まれた肩が、軋むように痛い。
「痛ぇなっ、何す―――」
骨まで破壊されそうなその力に、文句しようとしたら―――男のもう片方の拳が、啓介の腹に深く突き刺さる。
「ぐは…っ!」
内蔵まで潰されたかのような、重いパンチ。
これまで喧嘩では負け知らずで来ている啓介が、たった一発のパンチで身体がくの字に折れ、胃液が逆流しながら、アスファルトに膝を突いた。
「ガキが生意気言ってんじゃねぇぞ。責任も取れねぇヒヨッコが、大人ぶってんじゃねぇ」
男はぐいっと啓介の胸ぐらを掴んで、ドスの利いた声で、言い捨てる。
「あっ…コイツ、どっかで見た顔だと思ったら…黒松組の若頭、昇り龍のシュウ―――ッ!」
紅蠍隊の連中がざわついている中、啓介はそのまま、意識が遠のいていった。
気が付くと、啓介は自宅の門の前で、行き倒れのように、転がっていた。
ポツポツと雨が降ってきて、次第に雨脚が強くなっていく。
「いて…」
あれからどれくらい時間が経ったか分からないが、付近の住宅の家の明かりが殆ど点いていないのを見ると、夜中なのだろう。
腹を押さえながら上体を起こすと、門の所に啓介の単車が停めてある。
あの男がご丁寧に単車も家まで運んで、啓介を地べたに転がしていったんだろう。
「ったく…コレで連れ帰ったっていうのかよ…宅配便よりタチが悪いぜ…」
単車を押して、ガレージに停めようと、門の中に入っていく。
が、そのガレージには、涼介の車はなかった。
「んだよ…アニキいねぇんじゃん…心配してるとか、どうせ体裁とかで言ってんだろ、オヤジ達みてぇに…」
久し振りの我が家に入り、まっすぐに自分の部屋に向かう。
泥と雨で汚れた服を脱いで、ドアの前に洗濯されて畳まれて置かれていた服に着替える。
外は土砂降りに変わっていった。
「オレの心の中も土砂降りだっつの…」