|
『アナタの夢は何ですか?』
あの時、オレはその問い掛けに答えられなかった。
夢が無かった訳じゃない。
口に出したら叶わないと思った訳でもない。
人に言えないような夢という訳でもない。
多分、夢を叶えようとするだけの覚悟がその時はまだ出来ていなかったんだ。
『アナタの夢は何ですか?』
そんなモン無かった。
あったら教えてくれよって思ってた。
やりたいことも何も見つけられなくて、空っぽでモノクロのツマンナイ毎日。
突然色づいて、人生がガラリと変わったあの日。
夢中になれるコトが出来た。
目標も出来た。
そして、気付いた。
オレの夢は、ずっと小さい頃からあったんだ、って。
『アナタの夢は何ですか?』
そんな漠然としたこと、考えたこともなかった。
毎日眠くて、寝てる時はよく夢を見るけど、そういう意味の夢じゃないんだろうな。
延々と繰り返される、至極平凡な日常。
それがあのヒト達に出逢ったことで、イキナリ日常が非日常になった。
オレにとっての日常的なモノが、特別なことだなんて思えなかったのに、周りが凄く喜んでくれるんだ。
日常的に繰り返される、非日常の毎日。
色んな凄いヒト達と出逢って、目標みたいなモノも出来た。
目標はなるべく口に出して言った方が良いんだって、言われたっけ。
オレには目標と夢の違いとか分かんないから、多分、それが夢…なのかな。
でも、非日常の毎日も、まるで夢みたいだった。
夢の世界を共に過ごしてきた相棒は、今はもう、いないけれど。
◇ ◇ ◇
夏の終わり、秋の始まり。
今年は残暑も厳しくて、いつまでも暑いけれど、山の上というのは、日中でも涼しい。
当然、夜になればかなり冷え込むのだが、ついこの間まで、熱いバトルに身を投じていた。
冷える筈の夜の山中も、熾烈を極めるバトルと、ギャラリー達の盛り上がりで、熱に浮かされたようだった。
そんなプロジェクトDの遠征も終わって、早2週間が経つ。
今日は、一年間夢中になって打ち込んできたプロジェクトDの、解散パーティーが赤城大沼の湖畔にて、行われていた。
湖の傍ということもあるし、季節的に、もう涼しい筈の赤城の山の上は、バーベキューの火で、かなり暑かった。
もっとも、その割を一番食っているのは、みんなのオカン、史浩である。
「ほらほら欠食児童共、食った食った」
最高級の牛肉の味に、さっきから感激しきりで涙しながら貪るように食べている拓海とケンタに、汗だくになりながら史浩は焼けた肉をトングで次から次へと取り皿に載せていく。
「あざーす! あー美味ぇー」
「あちちち…、はふっ、美味いっす!」
「松本と宮口も、食ってるか? ビールもいいが、どんどん食ってくれよ」
肉より酒、の大人組に、ほらほら、と焼けた肉をトングで摘み上げて、メカニック達を促す。
「食べてますよぉー。ていうか史浩さん、遠征の時もバンガローで皆のメシ作ってくれてて、今も焼き係で、何か申し訳ないような…」
すんません、と皿を差し出して、熱々の肉を受け取る宮口は、取り敢えずコップを傍のテーブルに置いて、食べることに専念した。
「オレ替わりましょうか? バーベキューなら料理のウデは関係ないですし」
史浩さんこそ食べて下さい、と松本も差し出された肉に礼を述べながら、しかし替わろうと皿をテーブルに置きかけたのだが。
「ハハハ、気にするな。こういう役回りをするのがオレの役目みたいなモンだからさ、もう身体に染みついてるんだよ」
「料理が出来る男はモテるぜー? 自分の胃袋満たしてくれる男に女は弱ぇだろ、ゼッテェ胃袋ガッチリ掴んでる女があちこちにいるんじゃねぇかと思うんだけどよー、浮いた噂聞かねぇんだよなー」
けらけら笑いながら、啓介はビールを呷っている。
「あのなぁ啓介…今までプロジェクトDでいっぱいいっぱいだったのにそんなヒマなんかないって。淋しいモンだよ」
モテるってのはオマエや涼介のことを言うんだよ、とビールばかり呷っている啓介に、史浩は取り皿に肉を載せ、ほら、と差し出す。
「ホントかぁー?」
皿を受け取って一旦テーブルに置いた啓介は、ケンタの皿がカラになっているのを見て、やるよ、とケンタに渡そうとした。
「でも史浩さんはオレ達の胃袋掴んでくれてますよぉー! 遠征中も史浩さんのお陰でコンビニ以外のメシも食えて、オレ普段の食生活が侘びしーんで、史浩さんサマサマっすよ!」
あざーす、とケンタは啓介から貰った肉を早速頬張りながら、声高に主張する。
「まぁ涼介のお陰もあるけどな。オマエ達が今感激してるこの肉とかも全部、涼介が用意してくれたモノだし」
チラ、と涼介を見遣ると、涼介は皆を穏やかな表情で眺めていた。
「でも涼介さん、忙しいのにいつ買いに行ったんですか? こんなに沢山の食材…」
何処のデパートだろ、オレなんか行ったことないような高級デパートだと全部揃うのかな、と拓海は見たことのない謎の貝肉をモグモグと食べながら、静かに佇んでいる涼介を見遣る。
「何でわざわざ買いに行くんだよ?」
ビールに口を付けている涼介に代わって、啓介が呆れたように口を開いた。
「え…どういう…」
「パソコンからインターネットで注文出来るじゃん。電話すりゃ届けてくれるしな」
「へ…?」
「涼介と啓介の家は基本的に電話一本で届けてもらう、ってスタンスだからな。スーパーに買い物に行く、とかは殆ど無いんだよ」
咄嗟に理解出来ていない拓海に、兄弟と付き合いの長い史浩が分かりやすく説明した。
「うひゃあ〜…流石セレブ…;」
「じゃあオレらが感動してるこの牛肉とか謎の貝とか、涼介さんや啓介さんは普段食べてるモノなんすか?」
ケンタはただ感嘆としていたが、拓海はケンタよりも兄弟との付き合いが短い為か、ケンタのようにはするっと受け入れてはいなくて、更に次の疑問が出たのだった。
「そーだけど? オレはオマエらが何でそんなに感激してんのか分かんねーよ。てか藤原、オマエ鮑食ったことねぇの?」
何だよ謎の貝って、と啓介は呆れている。
高橋兄弟の金持ちっぷりをまざまざと見せつけられて、拓海は思わずメキッと手の中の割り箸を折った。
「気持ちは分かるけどな…松本、藤原に新しい割り箸やってくれ」
次々と焼いている史浩は、手が離せないので松本に顎でしゃくった。
「啓介、オマエには珍しくも何ともないんだろうが、ビールばっかり呑んでないで、肉も食えよ。空きっ腹にアルコールばかり浴びてると悪酔いするぞ。涼介も、さっきから全然食べてないだろ」
ほらほら、と史浩は取り皿に焼けた肉を載せ、啓介と涼介に差し出す。
「ずっと禁酒してたからビールが美味くてよ」
「あぁ、すまないな…食べるよ」
拓海に新しい割り箸を渡していた松本は、続けて啓介と涼介にも割り箸を渡した。
先に割り箸を渡された啓介は、口に銜えて割りながら、じとっと松本と涼介を見遣る。
松本の差し出す割り箸を受け取りながら、啓介行儀悪い、と涼介は窘める。
しかし啓介はスルーして、面白くなさそうに2人を見据えた。
「松本ってさー…マジアニキのシモベ、って感じだよなー。殿様の傍にいつも控えてる感じのさー、んで殿様の秘密も全部見てんの」
ぶぅ、と口を尖らせながら、啓介は熱々の肉に食いつく。
「オレはそんなんじゃないですよ、啓介さん」
穏やかに微笑むその姿には、どこか凄みがあって、過去の経験からしても、啓介は松本が苦手だった。
(松本ってオレよかとんでもねー修羅場くぐってるよなゼッテェ…アニキは教えてくんねーけど、ゼッテェカタギじゃねぇよな…?)
「はは、しもべという言い方が正しいかどうかはともかく、2人してよくコソコソしてるからな…松本はオレより涼介のこと知ってるんじゃないかって思うよ、オレも」
粗方焼いた史浩は、ヤレヤレと軍手を脱いで、ようやく肉に齧り付いた。
「まぁオレのことはいいから…楽しんでくれよ」
「あっアニキ誤魔化した!」
「酔ってるな、啓介。オマエは弱いんだから、程々にしておけよ」
「えー、程々じゃ楽しくアリマセーン!」
ワイワイと、慰労会のような解散パーティーは、盛り上がっていった。
解散パーティーと銘打ってはいるが、乾杯もなかった、リーダーである涼介からのスピーチもなかった。
ただ、皆で集まって、いつもは夜にしか来ない赤城で、バーベキューをして、他愛もない話をしながら、楽しんでいるだけだった。
それが、常に楽しんでやってきたプロジェクトDの、スタイルなのかも知れなかった。
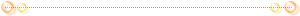 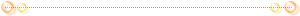
180SX、インプ、バンの順で、3台連なって、夕暮れの赤城の峠を下っていく。
運転手3人の中で健二が(自分のクルマだし)一番安心出来ると言うことで先頭で、次いで助手席に拓海を乗せて恐る恐るインプを運転するイツキ、最後に免許取り立て若葉マークの緒美が運転手のバンが、当然車体の前後に若葉マークを貼って(緒美が持参してきていた)、ゆっくりと走っていった。
寝転がっていようと思った啓介だったが、若葉マークを貼っているのを見て途端に恐ろしさがこみ上げて、起き上がってしまっている。
だが史浩の言う通り、緒美の運転は予想外にも、酷いことはなく、意外と上手いのではないか(兄弟の脳内の緒美比)と思われた。
峠道を下りきると、畜産試験場交差点で180SXとインプは右折して別れ、バンは皆を家に順に送り届けるべく、ノンビリと南下していく。
だがやはり可愛いイトコ殿に命を預けるのは落ち着かなくて、心地好い酔いもスッカリ醒めてハラハラと手も口も出しそうになっていた涼介は、《涼兄うるさーい!》と言われてしまい、仕方なく黙っていたのだが、市街地に降りてきて、ようやく人心地が付いた気がした。
啓介も安堵したように、寝転がっている。
緒美の醸し出す雰囲気そのままが運転にも表れて、そのゆったりしたゆりかごのような運転に、涼介以外の面々は酒が入っていることもあり、ウトウトと寝入っていた。
道が不案内な緒美に、助手席の涼介は道案内でぽつりぽつり口を開き、ふと世間話でもしたくなった。
「なぁ緒美…緒美は、夢ってあるか?」
「夢? そーだなぁ、薬剤師になって、涼兄と一緒に高橋総合病院で働くこと、かな」
急ブレーキも踏まない緒美は、キチンとポンピングブレーキをし、信号での発進も緩やかだ。
「それは…夢と言うんじゃなくて、目標、じゃないか? 現実的な…」
何だかデジャヴを感じながら、立場が逆か、と緒美が何と答えるのかを待つ。
「そーおー? 目標かも知れないけど、緒美は夢だなー。緒美にとって、ちいちゃい頃からお医者さんは涼兄で、まだホントのお医者さんじゃなくても、涼兄が診てくれたら治ったし、凄く頼もしかったんだ。だから、緒美もそんな風になりたいって思ったし、オウチのこともあるけど、薬剤師になって、涼兄と一緒にお仕事したいって思ったの。とても重要で大変なお仕事だけど、間接的にでも涼兄のお手伝いが出来て、今までの恩返しが出来たらいいなって。そしたら、凄く幸せだろうなって思うの。だから、個人的なワガママかも知れないけど、緒美にはそれが夢なの」
「そうか…」
「涼兄は?」
「え?」
「涼兄の、夢って何?」
まるで、3年前のあの時のような。
思い出して、トクンと鼓動が跳ねる。
「―――そうだな…優秀な医者になって、地域医療を発展させたいかな」
さっき大沼湖畔で語っていたことは緒美に話すような内容でもないな、と思い、咄嗟に表向きの《夢》を話す。
「えぇ〜? 涼兄っぽくなーい!」
「え…そう、か?」
小さい頃から緒美に言っていたし、それで問題なく納得してくれると思ったのだが。
「それって、子供が、《大きくなったら何になりたいの?》って訊かれた時に答えることや、目標、でしょ? 涼兄だったらもっと、周りがビックリするような、スケールの大きいこととか、そういうこと考えてると思ったのに」
ぷぅ、と緒美は口を尖らせている。
「ダメ…だったか?」
「涼兄のそれは、夢って言うのとは違うよー。確実に淡々と実現していきそうだしー、そこにワクワクとか無さそうだしー。夢って、もっとワクワクすることだと思うなー。分かった! 涼兄のことだからスッゴイ大きなコト考えてて、周りをビックリさせようと思って、内緒なんでしょ」
時々鋭いところを突いてくるよな、と胸がドクンとする。
「はは…オレの考えてることなんて、至極ちっぽけなことだよ」
「もう、誤魔化してぇー。ふーみんも言ってたよ、涼兄は一般的な基準とは真逆なんだろうって。涼兄がちっぽけって思ってるコトって、普通に考えたらきっと物凄く大きなコトなんでしょ」
昼間大沼で史浩に言われたことを、またそっくり言われている。
2人が近しい仲になっていたというのは驚きだったが、案外似合いのカップルなのかも知れないな、と思った。
「そうかな…」
「涼兄って、普通のささやかなことは絶対自分じゃ叶えられないって考えて、諦めてるんじゃないかなって。オウチの病院を継ぐのはとても大事なことだと思うよ。でもその為に、自分の本心を押し殺して誤魔化したり、最初から諦めたりするのは、ダメだよ。涼兄は優秀なんだモン、本気で願えば、どんなことだって叶えられるよ。緒美には分かるモン」
ニッコリと、その穢れを知らない無垢な笑顔に何度、癒されてきたことか。
本当に、諦めなくていいのか?
叶えられると、信じていいのか?
自分の《願い》には、障害が多すぎる。
「そうなのかな…」
「そうだよ」
2人の背後で、横になって寝ていた筈の啓介は、ゆっくりと目蓋を開けていた。
|