「啓介? 何処だ?」
ウッカリ小さな啓介から目を離していた。
どれくらい時間が経ったか分からないが、慌てて辺りを見渡す。
何処からか、小さな啓介の泣き声が聞こえてくる。
泣き声を辿っていくと、小さな啓介はトイレの前でえぐえぐと泣いていた。
ツンと匂ってきた匂いで気付く。
「あぁ、漏らしちゃったか…」
どうやら、便意を催したことで、自分でトイレに向かったが、すぐに脱げなくて、間に合わなかった、ということなのだろう。
「泣かなくていいよ、啓介。うんちをしたくなって、自分からトイレに行ったんだろ? 自分でトイレでうんちしようとしたんだろ? 啓介は今まで出来なかったことが出来てるんだ。今回は漏らしちゃったけど、次はちゃんと出来るから。お兄ちゃんが気付いてあげられなくてごめんな」
宥めるように、優しく頭を撫でる。
「けーちゃ、ひとりでといれ、できなかった…にーちゃみたいに、ひとりで…」
ぐしゅぐしゅと泣きじゃくる小さな啓介に、涼介はポンポンと頭を撫でながら、優しく微笑みかけた。
「少しずつ、出来るようになっていけばいいんだから。焦らなくていい、今日出来なくても明日は出来るようになっているから。な? 泣かないで。着替えよう」
涼介は子供部屋から小さな啓介の替えのパンツを持ってきて、脱がせて汚れたお尻と局部を拭き、汚れたパンツはダストボックスに投げ込む。
「けーちゃ、じぶんで!」
兄に綺麗にしてもらうと、小さな啓介は兄の手から、パンツを奪い取る。
「―――…」
空いてしまった手に、淋しさを感じるのは何故だろう。
いつでも、にぃに、にーちゃ、おにーちゃ、おにーちゃん、にーちゃん、アニキ、アニキと兄ばかりを追い掛けて、兄だけを頼り、兄にベッタリだったのに、離れて行かれてしまうような、この淋しさ。
弟が自立出来るようにと促し手伝いながら、イザ自立されて自分の元から離れられると淋しく感じるなんて、弟離れが出来ないのは自分だろう。
ずっと傍にいて欲しい、自分の手元に置いて、育てていきたい。
啓介の夢を叶える為には、いつか離ればなれになる時が来る。
その時オレは、正気でいられるか―――?
虚ろに手を見つめていると、小さな啓介が一生懸命パンツを穿こうと頑張っているのに気付き、しまったちゃんと見てやるんだった、と手助けの口を開こうとしたら、覚束無いものの、一人で穿けていたのを見て、涼介は驚く。
今日だけで何度も教えて実践しているし、学習能力が高いのだということが如実に分かる。
今でこそ啓介が学習能力が高いこと、言葉より身体で覚えるタイプだということは分かっているが、3歳の小さい頃には、まだ気付いてはいなかった。
小さくとも啓介は啓介なのだと、思い知る。
自分勝手に淋しさを感じている場合じゃない、弟の成長を喜ばなければ。
「凄いな、啓介。パンツとズボンなら、もう自分で穿けるじゃないか」
「けーちゃ、にーちゃみたいになりたいの。にーちゃみたいにじぶんでできるこになりたい」
半ズボンも一人で穿けて、小さな啓介はキラキラした笑顔で、兄を見上げていた。
「オレみたいに…?」
『オレはアニキみてーになりてーんだ。いつでもオレの目標は、アニキだから』
少年から青年へと変わっていく弟の、向日葵のような笑顔が思い出される。
こんなに小さい頃から、啓介はオレを目標としてくれていた―――果たしてオレは、それに恥じることのない、理想の兄だっただろうか―――?
淋しさなんて感じている場合じゃない、これからも理想の兄でいられるよう、精進しなければ。
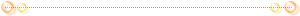
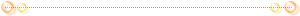
玄関のチャイムはいつまでも鳴っていたので、しつこい勧誘だな、と思いながら洗面所に行き、急ぎ顔を洗って髪を梳かし、階下に降りる。
LDKでインターホンを取ると、モニタに映っていたのは、緒美だった。
「はい」
『アレ? その声、涼兄?』
緒美の反応を怪訝に思いながらも、解錠ボタンを押した。
玄関に出迎えに行くと、緒美は目を丸くしている。
「涼兄、おっきいね」
「は? まぁいい、上がれよ」
「うん。お邪魔しま〜す」
まだ過去の世界にいた時の感覚から抜けきらない涼介は、経年を感じさせる屋敷内に戸惑いつつ、LDKに向かった。
「今日はどうしたんだ? 緒美。家庭教師の日だったか?」
一体今日は何日なんだ、と自分が過去に行っている間にどれくらい日数が経っているのか、過去にいた日数と同じか、それとも違うのか、全く分からず、心許ない。
「え? う〜ん、啓兄に英語見てもらおうと思って来たけど、涼兄がいるなら他の教科も見てもらいたいな」
この緒美の言い方では、やはり自分がいない時間がこの時代にあったのだと、確信する。
「お洗濯もしちゃうね! 溜まってるでしょ?」
「え…さぁ、どうかな…」
緒美はリビングのソファに鞄を置くと、パタパタと出て行った。
それを見送った涼介は、グルリLDKを見渡す。
ほんの数日振りの筈なのに、随分と久し振りな感覚だ。
ゆっくりと確かめるように、室内を見て回る。
(何だろう…随分日にちが経っているような…そんな感じがするな…今日は何日だ…?)
テレビは殆ど観ないし世間の情報はインターネットで事足りるからと、兄弟2人しかいない今は新聞を取っていないので、日にちを確認出来ない。
携帯が今何処にあるか把握していないし、緒美に訊けばいいか。
(あの感じだと、緒美はオレがいない間にこの家に来ているよな…啓介は部屋で寝てるのか…?)
啓介を起こしに行くか、と思ったその時。
リビングの奥、テレビの前のテーブルに何かが置かれているのが目の端に映った。
「何だ…?」
歩み寄ると、ハンディビデオカメラと、そのビデオテープのようだった。
出してあるということは、何か撮影したんだろうか、とテーブルの傍で覗き込む。
「何だ…メモ…?」
ビデオテープが重しになって、何かが書かれた紙があるのに気付き、手に取ると、ドクンと鼓動が跳ねた。
子供の書いた字―――何となく、懐かしさを覚える文字の形状。
《23さいのぼくへ。みてください。5さいのりょうすけより》
ずっと考えていた―――過去にいる間、5歳の自分は何処にいるのか、と。
「此処に…いたのか…?」