スッカリ陽が高くなっている。
エアコンを付けていない部屋で、啓介は暑さで目を覚ました。
「ん…アレ…?」
僅かに開いた瞳。
虚ろに映る景色に、机に涼介は向かっていない。
『朝…? もう昼か…? アニキ、大学行っちまったんかな…』
今日は日曜だから余程のことがない限り夏休み中だし家にいる筈というのは、咄嗟に頭が回らなかった啓介は、寝る前のことを思い出して、ガバッと起き上がった。
「…アニキ…負けちまったの、嘘じゃ…ねぇんだよな…」
しゅんとするが、泣いたことで、幾分スッキリしている。
寝て起きれば気持ちを切り替えるタチなので、負けは負け、と自分が負けた時と同じように、既に認め、受け入れた。
だが、《高橋涼介が負けた》という事実は認められても、悔しさがない訳ではない。
『アニキが負けちまうなんて、考えらんなかったけど…こうなったら、オレがもっともっと走り込んで、オレのアニキはスゲェんだってコト、オレが代わりに証明してやる…その為に、アニキにいっぱい教えてもらうんだ…』
真性の弟属性の啓介は、メジャーな世界でビッグになるという目標はあっても、イコール兄より上になるという考えは、全く持っていないのだった。
気持ちを切り替えて、苦手なリロンのお勉強も頑張ろうと決意を胸に抱いたその時。
《何か》にシャツの裾を掴まれているのに気が付いた。
「アレ、アニキ寝てたんか…気付かなかっ………」
アニキいたのか、と思い、ふと目を下に落とすと、いっと顔を歪めた。
「な…何だ…? この子供…」
小さな子供が、啓介のシャツの裾を掴んで、すぅすぅと眠っているのだ。
思わずキョロキョロと部屋を見渡すが、此処は涼介の部屋で、部屋主の涼介は何処にもいない。
屋敷内に他に誰かがいそうな気配もない。
「何だよ、この子供…何でアニキの部屋に…肝心のアニキはドコ行ったんだよ?」
壁の時計を見遣ると、昼に近い。
啓介がグースカと寝ている間に涼介が連れてきたとか、そういうことなのだろうか。
「近所の子供とか、親戚の子供とかか…?」
それにしては、随分綺麗な顔立ちの男のコだ。
目を閉じていても、賢そうな雰囲気が滲んでいる。
育ちの良さも感じられる。
「何となくアニキに似てるよな…目元とか、口元とか…耳の形も…」
くぅくぅと眠る謎の男のコをまじまじと観察すればする程、涼介にそっくり瓜二つな箇所ばかりが目に付く。
「ま…まさか…」
啓介は嫌な予感が過ぎった。
「アニキの隠し子…?!」
過去、自分がヤンチャして家に寄りつかなかった間に、涼介がどうしていたのか、知らないのだ。
今は想いが通じ合って、禁忌の関係を育んではいるが、涼介に昔女の恋人がいてもおかしくはない。
『そうだよな…アニキ、秘密主義なトコあるし…実は知らねぇコトとか、オレいっぱいあるし…』
もしかしたら兄の隠し子かも知れないと思うとショックを隠しきれないが、自分とてヤンチャ時代に寝た女の数は数え切れないし、どこかに自分が種の子供がいる可能性も捨てきれない訳で、お互い様なのだが。
『オレ…アニキは童貞だと思ってたんだけどな〜…』
取り敢えず起こして、何故此処にいるのか訊いてみよう、とつんつんと頬をつついてみる。
「柔らけ…大福みてぇ」
小さい子供とはなかなか触れ合う機会がないので、新鮮に感じた。
「ん…んん…」
ピクッと反応して、ゆっくりと目蓋が開かれる。
「お…オハヨウ?」
恐る恐る、啓介が声を掛けてみると。
男のコは驚いたようにガバッと起き上がった。
『うわ〜ぁ…どっからど〜見てもアニキの子供〜って感じ…;』
涼やかな目元は賢そうで、涼介をそのまま小さくしたようだ。
「だっ、だれだ!」
キングサイズのベッドの上で、男のコは警戒心を顕わにして、後退る。
「へ? この家のモンだけど…コッチこそ、オマエ誰だ、なんだけど」
「このいえの…? ゆうかいはんじゃないの?」
男のコは目の前の不審人物の言葉を受けてキョロキョロと、部屋を見渡す。
「誘か…って、何でだよ」
「ここ…ぼくのいえのつかってないへやとおなじ…ぼくのへやのとなりのへや…いつのまにこんな…」
不思議そうにしている男のコに、啓介の方も、怪訝に思う。
「何かよく分かんねーんだけど、取り敢えずオマエ、名前は? 何でココにいんの? アニキはどうしたんだよ?」
「ひとになまえをたずねるときはまずじぶんからなのるって、こどものときにおそわらなかったんですか?」
何だか警戒している男のコに、涼介が連れてきた訳ではないんだろうか、と啓介は首を傾げる。
「へいへい。オレの名前は高橋啓介。この家の住人だ。コレでイイか? で、オマエは? アニキが連れてきたんじゃねーのかよ?」
「……え…?」
男のコは、目を見開いて啓介を見つめた。
「どうせいどうめい…? めずらしいなまえじゃないけど…でも…」
「オイ、聞こえなかったのか? 名前は? トシは? 何でココにいるんだ?」
畳み掛けるように、啓介は尋ねたのだが。
「…たかはしりょうすけ。5さいです。なんでここにいるのかって…ぼくはじぶんのへやでねていたのに、なんで…」
「………はぃい?」
「ほんとうに、ゆうかいはんじゃないんですか?」
じ、とつぶらな瞳がまだ警戒を解かずに啓介を見つめているが、啓介は思考が一瞬途切れた。
「ほ…本当に、オマエ《たかはしりょうすけ》って〜の?」
涼介の別れた恋人が、生まれてきた子供に忘れられない元彼の名前を付けたのだろうか、とか、未だに《涼介の隠し子説》から離れられずにいたのだが。
「え、え〜と…因みに訊くけど、オヤの名前は? 職業は?」
「おとうさんはたかはしそうすけです。おかあさんはたかはししょうこです。おとうさんはおいしゃさんで、おかあさんはおとうさんのおしごとのおてつだいをしています」
啓介は思わず頭を抱えた。
涼介と啓介の両親は、父が聡介、母が粧子という名前であり―――そう、今この男のコ《たかはしりょうすけ》が言った名前と同じなのだ。
『イヤイヤ…待て待て待て? アニキの元カノが妄想で子供にそう教えてたとか? イヤでもそれならジーサンバーサンだよな? でもアニキとして育ててたとか? どんな妄想だ? ソレ…』
隠し子説から頭が離れない啓介は、こんがらがってきた。
「おじさんは、このいえのひとなんですか? なんでぼくといっしょにいるんですか?」
「おじ…ッ、コラ待て、誰がオジサンだ! お兄さんと言え!」
「このへや、どうみてもぼくのいえとおなじにみえるんだけど…でも、ちょっとふるくなってるかんじはするけど…こんなにおなじなんて、へんだよ…」
男のコはスルーして、相変わらず部屋を観察している。
「おにいさんは、ほんとうにたかはしけぇすけっていうなまえなんですか?」
ちゃんと聞いてたんだな、と思いながら、啓介はコクンと頷く。
兄と呼ばれることに、新鮮さを感じながら。
「そ〜だよ。それが何か?」
男のコは、何やら考え込んでいた。
見れば見る程、涼介にそっくりで、啓介は隠し子説から飛び越えて、ひとつの考えに至った。
『まさか…まさかだけど…アニキの子供じゃなくて、子供のアニキ…とか…言わねぇ、よな…?』
もしそうだとしたら、おかしいと感じている部分全てに、辻褄が合うのだ。
『イヤイヤイヤ…そんな、有り得ねぇだろ、ドラマや漫画じゃあるめーし…』
だが、本来頭の柔らかい啓介は、ある考えが浮かんだ。
『まさか…アニキ、やっぱ昨日のバトルで負けたことがショックで、子供になっちまったとか…』
どんな不可思議な事柄でも、涼介に起こる出来事であれば、《あの高橋涼介なら有り得る》と、すんなり納得してしまえるのだ。
「なぁ、同い年の幼馴染みっている?」
「おさななじみ?」
5歳の子供に《幼馴染み》という言い方はオカシイか、と言い方を変えようと考え。
「えーと、仲のイイ友達、っつーの?」
「きんじょにふみひろっていうおなじ5さいのともだちがいます。よくいっしょにあそんでます」
「…ソイツの家、自動車工場、とか?」
「はい。しってるんですか? ふみひろのこと」
「ぐぁー! やっぱアニキなのかよー! 何で子供になってんだよー!」
啓介は頭に両手を当て、仰け反って叫んだ。
「? どうしたんですか?」
「あの、さ…弟、いるよな?」
「はい。けぇすけっていいます。おにいさんとおなじなまえです。でもめずらしいなまえじゃないし、どうせいどうめいはよくある…」
「あの…な…オレ、だよ」
「え?」
「だから、その弟って、オレのコト」
「……は?」
男のコは、一瞬何を言われたのか、理解出来ない、と目を丸くする。
「オレ、アンタの弟だよ」
「うそだ! ぼくのけぇすけは、まだ3さいだ! そんなふりょうみたいなかみのけじゃないし、ちいさくてかわいくて、あったかくてやわらかくて、ぼくのたからもの…っ!」
「僕の啓介って…;」
恥ずかしい台詞の数々に、間違いなくこの子供は、小さくなった涼介なのだ、と啓介は確信した。
涼介でなければ、こんな聞いてる方が恥ずかしくなるような台詞を真顔で言ったりはしないだろう。
「イヤ、マジで。アニキが小さくなっちまったんだよ。っつ〜か、子供のアニキが未来にやってきちまったのか?」
その辺はよく分かんねーけど、と啓介は手を伸ばして、小さな涼介の脇に手を入れ、抱き上げて胡座を掻いた上に座らせた。
涼介は戸惑いと困惑の入り交じった表情で、啓介を見上げている。
「ほんとうに…けぇすけなの…? ぼくのおとうとの…?」
「そ。アニキの中じゃオレはまだ3歳みてーだけど、カッコよく育っただろ?」
「…そんな…たしかににてるなっておもってたけど…ぼくのかわいいけぇすけが、こんなふりょうになってるなんて…」
ガーンという音でも聞こえてきそうに、涼介はショックを受けているようだった。
「不良じゃねーし! イヤ確かに不良だったけど! 今はもう真人間…とは言えねーか…とにかく、恥じるようなコトねーから、今のオレは!」
じぃ、と涼介は啓介の薄茶の瞳をまっすぐに見つめた。
清らかなそれは、確かに自分の知る弟と、よく似ていて。
「けぇすけは…いまなんさいなの…?」
「オレは今21だよ。アニキは23だったのに、5歳になっちまうなんてな〜。ん? 縮んだ訳じゃねーから、どういうこった?」
頭は柔らかくても使うのは苦手なので、現状を理路整然と把握することは出来なかった。
「…そとをみてみてもいい?」
「ぁ? うん」
涼介は啓介の胡座の上から降りて、ヨイショとベッドを行儀よく降り、ベランダに向かう。
が。
「………」
小さな身長では、見上げてもベランダの向こうは見えなかった。
燦々と降り注ぐ真夏の太陽だけが、真上に恨めしく存在を主張している。
「抱っこしてやろーか?」
「…うん。おねがい」
ベッドの上から声を上げ、タラタラとベランダに向かった啓介は、ひょいっと涼介を抱き上げ、外を見せた。
「今日もあちーなー…」
抱き上げられた涼介は手すりに掴まって、眼前に広がる景色を見渡す。
「ほんとうにぼくのすむまちだ…でも、いろいろかわってる…つまり、ぼくはみらいにきたってこと…?」
「そーなんのかね。難しいことはオレにゃ分かんねーけど」
キョロキョロと見渡している涼介のまるっとした後頭部を見ながら、5歳の子供ってこんなに小さくて軽いのか、と思いつつ、啓介も普段余り見ない、昼間の街並みを眺めた。
涼介と共にベランダから外を眺めるのは、いつも夜か明け方だから、別の街のように見える。
「腹減ったな。メシ食おうぜ。何か色々考えなきゃなんねーコトあると思うけど、腹が減ってちゃ戦は出来ねーからな、まずは腹ごしらえして、それからにしようぜ、アニキ」
啓介はぐぅと鳴る腹の音に気付いて、涼介を抱きかかえたまま、室内に戻った。
「あ、うん…って、おろしてよ! じぶんのあしであるける!」
何となく気恥ずかしくて、バタバタと藻掻く。
「あーつい。だってアニキ軽いんだモンよ」
「…っ、ぼくはしんちょうもたいじゅうもひょうじゅんだ! 5さいなんだから、21さいのけぇすけからみたらかるくたってしょうがないじゃないか!」
まだ降ろそうとせず、軽々と抱きかかえたまま部屋を出て、抗議し続ける涼介の言葉をスルーして、階段を下りていった。
ようやく降ろしてもらえたのは、LDKに入ってからだった。
「スリッパは?」
文句を言おうと思ったが取り敢えず飲み込んで、涼介は啓介を見上げる。
「ぁ? 子供用スリッパなんかねーから、裸足のまんまでいーだろ?」
何でそんなの必要なんだ、とでも言いたげに、エアコンのスイッチを入れる。
「あしのうらがよごれるよ。おぎょうぎだってわるいだろ。スリッパどこにあるの?」
啓介は大きい涼介が部屋で履いていたスリッパで降りてきていたのだが、仕方なしに、ハイハイと玄関にあるスリッパを持ってきて、涼介の足下に置いた。
「ほい」
「ありがとう。へやのなかみてもいい?」
「自分ちなんだから未来だからって遠慮すんなよ。好きに見ろって」
涼介に見上げられるというのは、どうにも奇妙な気分だ。
ベッドの中で上に乗っかっていれば見上げられることはあっても、本来ほぼ同じ身長だから、この明らかな身長差は、新鮮さを通り越して戻ってきている気がする。
「へぇ…やっぱりだいぶかわってる…18ねんごのみらいなんだから、あたりまえか…」
物珍しそうに、見慣れている筈なのにだが変わっているLDKをキョロキョロと、涼介は見ていた。
「っと…おぎょうぎわるいな…」
深窓のご令息に育てられている涼介は、幼くともその躾はシッカリと行き届いていることを証明するかのように、ソファに行儀良く座った。
座ると床に足はつかないので、スリッパは脱いで足下に揃えている。
気が付くと啓介はキッチンに行き、冷蔵庫を覗いていた。
「ん〜と、材料何があっかな〜…」
「けぇすけがつくるの? おかあさんはおしごとにいってるの? ほかにだれか…」
「誰もいねーよ。莱子サン、足骨折しちまって暫く来れねーからさ」
「らいこさんって?」
「家政婦サン。まぁ他に臨時のヒト来てもらってもいいんだろーけど、オレもアニキも殆ど家にいねーし、自分のメシの世話も出来ねーよーなガキじゃねぇしな、オフクロが時間あったら作ってくこともあっけど、オレはいつもヒマだしさ、ちょこちょこメシ作るよーになったから、ちょっとしたモンだぜ?」
「へぇ…すごいな、けぇすけ」
手慣れたように調理に取り掛かる啓介を見て、涼介はスリッパに足を通してパタパタとキッチンまで歩いていき、啓介を見上げた。
「ぼくにてつだえることある?」
「アニキ、メシ作る手伝いとかしたことあんの?」
「まだないけど…けぇすけひとりにつくらせて、ぼくだけだまってすわってるだけなんて、できないよ」
小さくとも、涼介は既に《兄》なのだな、と思うと、啓介は何だかほっこりした気分になった。
「すぐ出来っから、気にすんなって。覚束ねー手で怪我させる訳にゃいかねーからな。アニキパジャマのまんまだから、着替え…ってもねーか…確か物置にガキの頃の服がまとめてあるってデッカイ方のアニキに聞いたことあるし、後で探してくっから、テレビでも見て待ってろって」
ニッと笑う啓介に、涼介は納得して、わかった、と戻っていく。
だが、テレビなどより啓介の食事の支度を見ていたい、と思い、ダイニングの椅子によじ登って、システムキッチンで手際よく調理を進める啓介の姿を眺めていた。
『なんでぼくは…みらいのせかいにきたんだろう…けぇすけのねがおをみながら、どんなおとなになるんだろうなっておもいながら、ねむったからなのかな…まさか、めがさめたらほんとうにおおきいけぇすけがいるなんて…やっぱりゆめのつづきなんじゃないのかな…』
小さな手で、涼介はほっぺたを抓ってみる。
「…いたい」
ということは、夢じゃないのか。
俄には信じがたいが、さっきのあの啓介の笑い方は、自分のよく知る、大切な弟にそっくりだった。
3歳の頃の面影もある。
『でも…ほんとうにけぇすけだとしても、にんげんがみらいにくるなんて…どんなにかがくがすすんだって、じくうをとびこえるなんて、できるわけないよ…』
小さくともリアリストな涼介は、非科学的なことは信じていない。
物心付いた時には既に、サンタクロースは両親なのだと知っていたくらいだ。
だが、目の前に起こっている現実は、受け入れなければ。
『そうだよな…ものごとはじゅうなんにかんがえられなきゃ、りっぱなにんげんにはなれないよな…しやのせまいにんげんにはなりたくないし…』
お利口な涼介は、啓介の調理を眺めながら、自分自身に起こった信じがたい《現実》を受け入れるべく、アレコレと考えを巡らせたのだった。
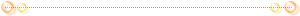
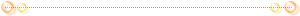
今後のことは他に色々話しておくこともあるのだが、取り敢えず史浩は帰り、大学へのうまい言い訳を考えることにした。
「ねぇけぇすけ、おとなのぼくとけぇすけがのってるくるま、みてみたいな」
史浩を見送った後、涼介がグラスを片付けようとしたので、いつもならそのままにしておく啓介が代わって片付けていると、ふと涼介は言いはなった。
「ふみひろとけぇすけがあんなふうにいってくれるくらいおとなのぼくがむちゅうになってるくるま、みたいよ」
「じゃあアニキの靴取ってくるな」
2階に行って、啓介はまず涼介の部屋の引き出しからFCのキーを掴んで、それから一度階段を下りて、両親の部屋がある方への階段を上っていき、物置から涼介の靴を見つけて、持って降りた。
2つの階段を上って降りて、面倒だな、と思いながら、涼介は玄関で待っていた。
「ほい、コレでイイか?」
「うん。ぼくのくつだ」
これを思うのは何度目か、自分の中ではピカピカの靴がこんなに古びていて、別のモノにさえ思えてくる。
新品の靴が足に馴染む前に次の新しい靴を買い与えられるので、それに慣れきっている為、古い靴というのは、抵抗がある。
だがそれよりも、外の世界に出てしまうドキドキの方が、上回った。
玄関のドアが開けられると、門までの景色をまず眺める。
屋敷を囲うように植えられている緑が、驚く程に背が高くなっていた。
リビングからはカーテンでハッキリ見えなかったので、こんなになっているとは、圧巻だ。
「みどりがすごいな。あそこのさくらのきも、すごくおおきくなってる」
キョロキョロ、と涼介はあるモノを探す。
「…いぬごやがなくなってる。…エディソンはいつしんじゃったの?」
別の場所に移動しているかもと思ったけれど、どこにも見当たらない。
成犬だったからそうそう長生きしないことは理解していても、18年後にはもういないのかと思うと、やはり淋しくなる。
「あ? あーそういやガキの頃デカイ犬がいたっけ…オレあんま覚えてねーんだけど、オヤジとオフクロも段々忙しくなってって、世話が出来ねーからって誰かのウチに貰われてったよ確か。どうなったかは分かんねーな」
「そうなのか…ぼく、エディソンすきだったのにな…けぇすけもすごくすきだったのに…ぼくがしっかりめんどうみるから、よそにやらないでっていおうかな…」
「でもさー、オレがよく覚えてねーくれーガキの頃だったら、アニキだってそんなでかくなってねーだろ? 犬は毎日散歩させなきゃいけねーし、ガキにゃ無理だと思うぜ? いくらアニキでもな」
しゅんとしているので、肝心のクルマを見に行こう、と涼介の手を握って、ガレージに連れて行く。
「ホラアニキ、クルマ見るんだろ?」
「あ、うん」
広いガレージに2台並べて駐車してある、RX―7。
傾いてきた陽の光が射し込んで、輝いている。
「白い方がアニキのクルマで、黄色い方がオレのクルマだぜ」
やはり涼介も男のコ、わぁ、と目が輝く。
「カッコイイだろ?」
「うん! おなじあーるえっくすせぶんっていってたけど、ずいぶんかたちがちがうんだね! なんで?」
「アニキのクルマからフルモデルチェンジされて、型式もFCからFDに変わってるし、オレの方が最新式で、アニキの方はその前のカタチなんだよ」
「よりよくへんかしていってるってことか。うんてんせきにすわってみたいな」
「鍵持ってきたから開けるな。エンジンかけといた方がイイと思ってたから、鍵持ってきて良かったぜ」
啓介が鍵を開けると、涼介はヨイショ、と乗り込んだ。
大きな体躯には狭く感じるコクピットも、今の涼介には、広くさえ感じられる。
「ふしぎなすわりごこち…。けぇすけのへやにもおなじいすがあったよね。これがばけっとしーとっていうの?」
資料に出てきた単語を1つ理解した涼介は、興味津々、メーター周りを見たり、手を伸ばしてハンドルを握ってみたりした。
「ハハッ、こーやって見てるとアニキやっぱちっこいなー」
もっと雰囲気を出してやろう、と啓介は涼介に4点式シートベルトを締めてあげた。
「サーキットや峠を走る時は、コレ締めてるんだぜ」
チャイルドシートの子供みたいだな、と思いつつ、今の涼介のサイズではシートベルトの意味を殆ど成していないな、と思う。
今まで車にはそれ程興味の無かった涼介だが、こうして自分の車というモノがあって、運転席に座ってシートベルトを締めると、ワクワクしてきた。
「ぼくのくるま…」
そんな風に感情をストレートに表に出す涼介が、啓介には新鮮で、大きくなっていくにつれて段々と多くの制限が涼介を縛っていったんだな、と気付く。
「うごいてるところもみたいなー。でもぼくはうんてんできないから、けぇすけのくるまにのりたいな。まだあかるいし、どらいぶにいこうよ」
涼介は目を輝かせて、啓介を見上げた。
「ぁ? そりゃ勿論イイけど…ウチにチャイルドシートなんかあんのかな…」
物置にゃ見当たらなかったような、と考え込む。
「ちゃいるどしーと? ぼくそんなにこどもじゃないよ。なくてもだいじょうぶだよ、しーとべるとすればいいだろ?」
「イヤ、6歳未満の子供はチャイルドシート着用の義務があんだって…アニキ5歳だから、チャイルドシート無しじゃオレ罰則食らっちまうよ」
走り屋の行為は交通ルールを破ってはいるが、それ以外については、啓介はキチッと守るのが常識としてあったので、『それくれーイイか』とは思わなかった。
「そうか、18ねんごのみらいじゃちゃいるどしーとのぎむかがさだめられているのか…じゃあしょうがないな、たぶんいえにはないだろうし…あきらめるよ」
涼介はしゅんとして、心底残念そうにしていた。
「あっ、オレ明日にでもチャイルドシート調達してくっからさ、今日は我慢して! な?」
何とか涼介の機嫌を治さねば、と啓介はオロオロする。
「そだ、エンジンかけっから、ちっと降りて。ロータリーのエンジン音聞きゃ、ちっとは雰囲気出るだろうし」
締めていた4点シートベルトを外してやって涼介を抱き上げて降ろして、代わりに啓介が運転席に座る。
滅多にFCを運転させてもらえることはないので、FCのコクピットというのは少し新鮮に感じて、嬉しかったりもした。
エンジンを駆けると、ロータリーのアイドルが心地好くて、やはり最高だ、と思う。
何となくじーんときて浸っていると、じぃっと視線を感じた。
ぼくのことわすれてるだろ、とでも言いたげに、じとっと見つめられている。
「っとワリ。アニキ座って」
慌てて降りて、涼介を抱き上げ、もう一度座らせた。
「なんだろ…そんなにくるまにのったことはないけど、ぼくのしってるくるまのおとじゃないみたいだ…かいぞうしてるから?」
「エンジン内部はノーマルなんだけどな。でもまぁチューニングしてっと音は変わるし、ロータリーエンジンだから、やっぱ違うと思うし」
「さっきしりょうでみたよ。ろーたりーえんじんはにほんのまつだだけがそのえんじんのかいはつとじつようかにせいこうしてるって。あーるえっくすせぶんはとくべつなくるまなんだな」
ロータリーのことをどう説明しようか、と思っていたら、既に理解していたのは、流石と言うべきなのか。
涼介はヨイショと運転席から降りると、グルリ外側を眺めた。
「まっしろできれいだな。けぇすけのくるまはきれいなきいろで、けぇすけみたいだ」
隣のFDもグルリ見て、FCとの違いを見比べている。
「はやくはしってるとこみたいなー」
背伸びしてサイドウィンドウからFDの中を見ながら、ポツリ呟く。
こうしていると、大人びたことばかり言って仰天させられても、涼介は5歳の子供なのだということを、再確認させられた。
『可愛いぜー、アニキー…』
「ぼく、くるまのこともっとしりたい。へやにもどってしりょうのつづきよみたい」
「え? あー…それはどうなんだろな…」
これ以上未来の自分のことを知っていいのだろうかと思いつつ、子供の好奇心の芽を摘み取るのは良くないよな、とやめさせることは出来なかった。
取り敢えずFCのエンジンだけにして、エンジンを切って屋内に戻ると、靴を脱いでキチンと揃え、スリッパに足を通してパタパタと階段の下まで行くと脱いでスリッパを手に持って、上っていった。
『あそっか、子供の足じゃあのスリッパ履いてちゃ階段上り下りキケンだモンなー…アニキ、ちゃんと分かってんだな…』
足の裏が汚れるし行儀が悪いから、大人用スリッパでも履きたいと言っていた涼介が、それらより危険回避の方を優先させているのを目の当たりにして、こんなに小さい時から既に、自分の能力というモノをハッキリ分かっているんだ、と感心した。
啓介だったら、子供の頃はそんなことは考えもせずに怪我ばかりしていたし、涼介に注意されてばかりいた。
つい最近まで、無茶と思うことも強引にやっていたし、かなり紙一重なこともやらかして命の危険も感じたことがある。
しかしようやく、無理だと思ったら行かない、という判断が出来るようになってきたところだった。
部屋に入ると、小さい涼介は、手が届く範囲の資料は殆ど本棚から引っ張り出していた。
「けぇすけ、うえのほうのとって」
「アニキー、そんな全部出さなくたって、一気に全部読める訳じゃないし、順番に読んでいきゃイイじゃんかよ」
あーあー、アニキの部屋がこんなに散らかっちまって、と啓介は呆れる。
「そうだけど、ぼくにはどのふぁいるにどんなないようがかいてあるのかわからないから、ちょっとだけみてどれをさきによむかきめたいから」
「それもそっか。っつってもオレだって見せてもらえねーモンばっかだから、どれがナニとか分かんねーぞ」
ヒョイヒョイと高いところにあるファイルを取り出して、おっとコッチは大学関係だから戻そ、とパッと見てクルマ関係だと分かるモノだけをドサッと、床に乱雑に積み上げて置いていった。
「ありがとう」
涼介は積み上げられたファイルを順に簡単に目を通して、読む順番を決めているようだった。
テキパキと積み上げ直し、きれいに調えていく。
そして早速読むのに夢中になっている小さな兄に、啓介は手持ち無沙汰で、ベッドに腰掛け、ぼ〜っと眺める。
『つーかマジでちゃんと読めてる感じ…やっぱアニキってちっこい頃から天才だったんだなー…』
自分が見てもピンとこないデータや説明文なのに、漢字や英語なども入り交じったモノを5歳の子供が読んで理解しているというのは、とてつもなく凄いことだと思う。
ふと、小さい頃の自分を思い出す。
兄の後ろばかり追い掛けて、世界の全てが、兄で出来ていたあの頃。
尤も、今もそれは変わっていないように思うが、兄の言うことが全てで、兄が与えてくれる世界に、存在していた。
『オレ…ずっとアニキにおんぶに抱っこしてっけど、大学卒業したら、この家を出てくんだよな…アニキはこの家に残って医者になるから、アニキと離ればなれになるってコト…アニキを頼ってちゃダメなんだ…群馬に残るアニキに心配かけないように、アニキを安心させられるようにならなきゃダメなんだ…』
そうは分かっているのだが。
『でも…どーやったらいいんだ…? 自分の足で立って歩いてくのって、どーやれば…』
初歩で躓いている啓介は、悶々と考え込んだ。