|
思えば、アニキは毎年、この時期に様子がおかしくなることがあった。
アレはいつからだっただろう?
そんなに前からじゃなかったと思うんだけど。
連絡もせずに何日も帰ってこなかった時があったりもした。
去年は、やっぱり連絡の取れない日があって、かと思えば、イキナリ1人で他県にまでバトルしに行ったとか、アニキらしくない行動をしてたように覚えてる。
夏の終わり、秋の始まり、その時期のアニキは、何だか不安定で、儚げで、まるで消えてしまいそうで―――ぎゅうっとオレの腕の中に閉じ込めておきたくなった。
長い時間を掛けて、やっと手に入れたアニキ。
想いが通じ合えた時は、天にも舞い上がるようだった。
あれからずっと、オレは幸せだったけど、こんな風に予想外の行動に出たり、行方が分からなくなったり、まるで消えてしまいそうなアニキを見ると、不安になった。
でも、その度に、オレとアニキは、何度でも通じ合えた。
大丈夫? って訊くと、決まってアニキは、オレは大丈夫だよ、オマエを残していなくなったりしないよ、って、言ってくれた。
だからオレは、アニキを信じてる。
そうやってオレにも黙って行動するのにも、深い理由があるんだって。
だから、心配なんかしない。
アニキの為に、オレは最終戦、勝利をアニキに捧げるから。
目標が見つからなくて退屈だった人生に、クルマっていうとびっきりの世界を教えてくれた、アニキの為に。
だから、アニキ…白い翼に乗ってるんなら、羽ばたいてきて。
羽を休めに、オレの元に帰ってきたら、いつも通り、「おかえり」って言ってやるからさ。
◇ ◇ ◇
それは暑い夏の始まりだった。
群馬の夏は、取り分け暑い。
全国の最高気温でニュースに群馬が登場することもしばしばだ。
熱中症患者が続出し、全国の病院に救急搬送される毎日、涼介の通う群馬大学の附属病院でも、慌ただしく対応に追われている。
だがまだ大学2年生である涼介には、医学部医学科といえど病院に関わることは殆ど無く、その他の学部の学生と同じ夏を送っていた。
まぁ、夜な夜な峠を爆走し、週末には近郊のサーキットに出掛ける生活が、果たして《同じ》と言えるのかは、甚だ疑問ではあったのだが。
夏季休講に入ると、涼介の所属する硬式テニスサークルでは、荒牧キャンパスにて、全学部合同の親睦交流会が開かれた。
荒牧キャンパスにはテニスコートが6面あるが、ソフトテニス部が3面、硬式テニス部が3面、とサークル活動日が重なる日は分けて使用されているが、今日は硬式テニス部で全面使用させてもらっている。
交流会の内容は、親善試合などが主で、男女別のシングルスとダブルス、男女混合のミックスダブルスの5種類で、一応トーナメント方式で、優勝者にはそれぞれ、草津温泉のペア宿泊券がプレゼントされるらしい。
涼介は運動神経も人並み以上にあるが、サークル活動を熱心にしている訳ではなかったので、各種大会などに張り切って出場している連中に花を持たせる為に、シングルスにのみ出場し、適当なところで敗退した。
すると待っていたかのように、女達が群がってくる。
「高橋クゥ〜ン、一緒に女子の方応援しなぁ〜い?」
可愛らしく媚びを売っているつもりなのだろうが、涼介には獲物を狙うハイエナにしか見えなかった。
「いやオレ、救護係でもあるんで…」
「大丈夫大丈夫〜v」
何が大丈夫なんだか分からないが、邪険にすることも出来なかったので、適当に合わせながら、女子シングルスの試合を観戦した。
無駄にスキンシップしてくる女達が鬱陶しかったが、適当にそつなくあしらって、試合をしている選手を眺めた。
この日は此処前橋市が、全国最高気温を記録していた。
当然、皆が滝のように汗を流している。
以前史浩に、『オマエは人間じゃない』と言われた涼介は、猛暑、いや酷暑の中で、汗一つ掻いていない、名前の通り涼しい顔で、ベタベタと汗ばんだ身体でスキンシップしてくる女達が、正直気持ち悪くてしょうがなかった。
涼介とて、汗を掻かない訳ではない。
運動をすれば汗を掻くし、そのきらめく汗の結晶に、女達が見惚れるのだ。
日常に於いて汗さえもコントロールしてしまうのが、史浩に『人間じゃない』と言われる所以だった。
涼介に群がる女達も、身だしなみとして汗のケアはしている。
だが、それでも追いつかない程に、今日は酷暑だった。
日射病・熱射病・熱中症などで倒れる人間が出なければいいが、と救護係を任ぜられている涼介は、コート全面に目を配る。
『へぇ…上手いな、あのヒト…フォームが凄く綺麗だ』
すぐ目の前の、女子シングルスのコート。
顔など見ていなかったが、その動きには無駄が無く、洗練されていた。
我知らず見入っていたが、観察眼に長けている涼介は、異変を即座に感じ取る。
まだ第1セットだというのに、相手選手より、呼吸がかなり激しくなっている、そしてこの炎天下で、殆ど汗を掻いていない。
涼介のそれとは、意味合いが違うのだ。
「まずいな、あのヒト…」
「? どうしたのォ? 高橋クゥン」
ベンチから腰を浮かせた時には、遅かった。
無理な返球を追い掛けたその時、糸が切れた人形のように、足が縺れてその場に倒れ込む。
「ッ、センパァイ!」
不自然な転び方をして、足を挫いたかも知れない、と涼介は立ち上がった。
救急箱を手に駆け寄って、様子を伺う。
「大丈夫ですか?」
女性はグッタリしていて、意識も定かではなかった。
試合中の選手達もコートの一角の騒ぎにプレイを中断し、様子を伺っている。
医師の卵のタマゴである涼介は、慌てることなく、症状を確認していった。
脈拍がかなり速い、それに反して測った血圧が低い。
親指の爪を押すと白い色が出るが、押した手を指から離して3秒経っても、赤い色に戻らない。
「どうだ? 高橋…」
合同サークルの代表である部長が、クーラーボックスを担いでやってきて、心配そうに背後から覗き込む。
「えぇ…熱射病になりかけの、日射病といった所ですね。分かりますか? どんな具合ですか? 吐き気はありませんか?」
涼介は女性に声を掛け、意識障害が出ていないか、確認した。
「ちょっと…ダルイ、かな…」
弱々しく、ようやくのことで言葉を紡ぎ出す。
「誰か、タオルを冷たい水で濡らして下さい!」
涼介は周囲に指示を出し、濡れタオルを女性の首に巻き、もう一枚で氷をくるみ、身体に当てていく。
「高橋、水分を摂らせないと…スポーツドリンク」
医学部の人間が多い為、日射病(熱射病)の応急処置の知識は既に持っていることから、テキパキと対処した。
「救急車呼ぶか?」
「大、丈夫…涼しい所で、ちょっと、休ませて…もらえれば…」
冷えたスポーツドリンクを飲んで、幾分落ち着いたのか、女性は起き上がろうとする。
「無理しないで下さい。誰か、医務室に案内してもらえますか?」
サークル活動以外には殆ど荒牧キャンパスには来ないので、荒牧キャンパスで学ぶ教育学部などの人間に医務室の場所を訊く。
「こっちです!」
涼介は女性を抱き上げて、案内に従って、校舎内の医務室に向かった。
夏季休講中ということで、医務室の医師は生憎本日不在だったが、必要なものは揃っているので、女性をベッドに寝かせると、基礎的な応急処置として、まず足を高くして、脇に濡れタオルを挟んで、霧吹きで手足や顔に水を吹きかけ、首筋や脇に当てたタオルがぬるくなってくると、取り替えた。
霧吹きは有効な応急処置だが、医師ではない学生の身である涼介は、本来なら全身に水を吹きかけるべきなのだが、相手は女性なので、必要最低限に留めておいた。
股に濡れタオルを挟んで熱を逃がすというのも流石に出来なかったので、冷たい水で濡らしたタオルを、スコートに少し覆い被せるように、腿に掛ける。
そして祭りで配られたと思われる団扇があったので、それで身体を扇いだ。
「迷惑…掛けちゃって…ゴメンナサイ…」
一瞬意識を失っていた女性は、意識が戻ったようで、ピクリ反応し、弱々しく呟く。
「気にしないで下さい。今日の暑さでどうにかならない方が、おかしいですよ。ゆっくり、休んで下さい」
団扇で扇ぎながら、涼介は優等生宜しく、柔らかく語りかける。
この様子ならそれ程酷くないだろうか、と思うが、多少の知識があっても素人判断と変わらないので、後で病院に連れて行くべきだな、と思う。
「そう言えば…足も診た方がいいですよね。おかしな転び方をしていましたから…」
扇いでいた団扇を置いて、涼介は足を診た。
「少し腫れていますね…でもそんなに酷くなさそうだ。湿布を貼って、テーピングして固定しておけば大丈夫でしょう」
涼介は手際よく、手当てしていく。
「暫く無理に動かさないようにして下さい」
「有り難う…キミは戻って…救護係、なんでしょ…?」
ついていて、と言われるとばかり思っていた涼介は、女性の逆の反応に、少々驚きを感じていた。
「いつ容態が急変するとも限らないんです。幸いというのも変ですが、医学部の人間が多いですから、オレじゃなくても手当ては出来ますから、気にせずに、休んでいて下さい。少しでも具合が悪くなったら、すぐに言って下さい」
涼介の真摯な声に、ようやく安堵したように、女性はふっと眠りに落ちた。
そろそろ親善試合が終わる頃だろうか。
表彰など諸々が済んだら、次は店に移動して、打ち上げだ。
だがこの女性を病院に連れて行くのを理由に遠慮させてもらおう、と涼介は思っていた。
ハイエナのようなミーハーな女達に集られるのは苦手だったので、体のいい理由が出来て良かった、と思うのはこの女性に対して不謹慎だろうか。
脈拍もだいぶ落ち着いてきているし、血圧もほぼ正常値に戻っているので、大事はないと思うが、それでも倒れた以上は、キチンと医師に診てもらった方がいい。
「ん…」
使用した道具を片付けていると、空調が効きすぎているのか、女性がぶるっと身震いして、目を覚ました。
涼介は空調の温度を上げ、脇と首の濡れタオルを取り外し、腰まで覆っていたベッドの薄い掛け布団を胸部まで覆い被せる。
「具合はどうですか?」
深みのある柔らかい声で、様子を伺う。
「ん…だいぶ、スッキリした…」
「それは良かった。荷物一式、此処にあるんで。オレの荷物はそっくりコートに置きっぱなしなんで、取りに行ってきます。着替えたら、病院まで送っていきますから」
「え? ちょ…」
涼介は机の上に置かれた荷物を指し示すと、医務室から出て行った。
荷物を片付けてコートを後にし、再び医務室に向かう。
草木の生い茂る中、建物沿いに歩いていると、医務室にカーテンが掛かっているのが目に付いた。
空調を効かせていたので窓は閉め切っていたが、外の天気を見る為にカーテンは閉めていなかったのに、閉めたのはあの女性だろうか。
取り敢えずは更衣室に向かい、テニスウェアを脱いで着替える。
もしかしたらあの女性も医務室の中で着替えているのかも知れないな、と思い、打ち上げに向かう為に集っている輪の元へ行き、部長に、女性のことと、打ち上げは欠席する旨を伝えた。
途端に女達がぎゃあぎゃあと騒ぎ出す。
「え〜っ、高橋クン来れないのォ〜?! つまんなぁ〜い!」
「あたしも日射病なって高橋クンに看病されたかったぁ〜!」
「不謹慎なことを言うんじゃありません!」
女子部の部長らしき人物に、ぺしっと叩かれていたのを見て、内心ヤレヤレと息を吐きながら、医務室に向かった。
するとカチャリドアが開いて、着替えた女性が出てくる。
「歩いて大丈夫なんですか? オレ、病院まで送っていきますよ。クルマで来ていますから」
すぐ其処ですし、と穏やかな声で、柔らかく気遣う。
髪も梳かされスッカリ身綺麗になっていたが、医師の(卵のタマゴの)目で見れば弱々しく、儚げに映った。
それはそのまま医師(の卵のタマゴ)としてなのか、別のモノによるのかは、分からなかったけれど。
「うん、何とか歩けるよ。でも大丈夫。打ち上げに参加しないコ達で、皆で乗ってきたバスで帰るから。群大の附属病院じゃ、待ってる間に具合悪くなりそうだし。もうスッカリいいから、大丈夫だよ」
外に向かいながら、大丈夫と繰り返すその女性、初めてキチンと顔を見た気がするが、余り見掛けないタイプの美人だった。
どことなく、上流階級の雰囲気を漂わせる、上品な佇まい。
いつも周りに群がってくる女達とは毛色が違うな、と涼介は思った。
「ですが、ちゃんと受診した方がいいですよ。群大病院じゃなくても、何処か別の…」
普段のサークル活動で見掛けないということは、この女性は桐生キャンパスのある工学部なのだろう、ととうに気付いていた涼介は、このまま放っておくのは心配で、食い下がった。
「ん〜、じゃあ、桐生キャンパスに戻る途中に、大学の近くに病院があるから、そこに行くよ。それならいい?」
行くと言わなければ何処までもついてきそうだな、と思ったのか、女性は眉尻を下げてそう言った。
「じゃあ其処まで送りますよ。バスで帰れても、其処からご自宅に帰れないでしょう? 足も痛めてるんですし…って、あ、別にやましい意味じゃないですよ、ただ心配で」
食い下がりすぎるのは逆に不躾になるか、と涼介は否定して、ふぅ、と肩の力を抜いた。
「ふふ。キミにそんな心配はしてないわよ。キミ…高橋涼介くんでしょ。ウチの後輩達がキャーキャー騒いでいたわ。医学科のエリートだって」
じ、と彩られた大きな瞳が涼介を見上げる。
女の纏う香水の香りが、甘く心地好く感じた。
「あ、名乗ってませんでしたね。すみません。何か今更の気もしますが、医学部医学科2年の高橋涼介です」
優等生宜しく、涼介は自己紹介した。
「わたしは工学部環境デザイン工学科3年の桜田香織。看病してくれて…足を手当てしてくれて有り難う。じゃね」
その女―――香織は、甘い香りを涼介の元に残して、帰る連中と共に、バスに乗り込んだ。
それが、香織と涼介の、初めての出逢いだった。
この香織との出逢いが、この先の涼介の運命を狂わせていくとは、この時はまだ、涼介は気付かなかった。
そう、香織の運命もまた、期せずして出逢った涼介との関わりによって、大きく動こうとしていたのだった。
悲しい結末へと、誰も気付かないままに―――。
◇ ◇ ◇
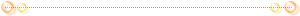 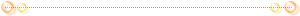
◇ ◇ ◇
梅雨前線のはびこってきた、6月。
香織は、忙しい合間を縫って電話をくれる凛と、凛のマンションでの逢瀬を重ねながら、無性に涼介に会いたくなっていた。
凛も悪いヒトじゃない。
でも、新しい出逢いに、心惹かれていて―――もっと知りたい、そう思ってしまう。
賑やかな周りの噂話からじゃなくて、直接本人の口から、聞きたいことが沢山ある。
でも、穢れを知らなそうなあのピュアな瞳を思い出すと、自分は不釣り合いなのでは、と躊躇ってしまう。
純粋で、まっすぐで、乗っている車のように純白な心を持った、年下の男のコ。
好意を持ってくれていることには気付いた。
でも、そんなキレイな彼に、想われる資格はないかも知れない。
大学からの帰り、病院に寄って、テニス肘の診察を受ける。
大分前から通って治療を続けていたので、今日の診察で、ほぼ完治、と言われた。
テニスはもう当分出来ないけれど、日常生活に支障はないので、それで充分だ。
「あ…っ」
玄関口で、目の端に白いものが映って、思わず立ち止まる。
前みたいにあの白いRX―7が停まっていないかな、と思ってしまった。
でも停まっていたのは、期待とは違う、全く別の白い車。
向かいの奥まった道にある眼科から出てきたライトバンに、香織は小さく息を吐く。
『北条さんに電話しとかなきゃ…』
テニス肘が完治したら知らせろ、と言っていたので、鞄から携帯を取り出し、電源を入れる。
凛はまだ大学で忙しい時間だから、留守電にメッセージを残すだけでいい。
「―――香織です。テニス肘は、ほぼ完治したとお医者様にお墨付きを貰いました。またお時間のある時に、誘って下さい」
今は涼介に会いたいと思いながら、こうしてご機嫌取りのようなことを言って―――やっぱりこんないい加減じゃ、涼介には会わない方がいいのかも知れない。
道路を渡ってバス停に向かいながら、目尻がじわり滲んでいく―――。
夜更け、お気に入りの薔薇の入浴剤を入れたバスタイムを過ごして、落ち着いた頃。
突如鳴った、携帯電話。
凛からだと思うと、途端に気が重くなる。
あんなことを言っておきながら、正直今は、まだ会いたくない。
でも、愛猫のエイリーンがニャーニャーと元気に鳴くので、他の住人にバレるとまずいから、意を決して通話ボタンを押す。
「…モシモシ」
『あ、香織さん? 涼介だけど』
低く深い声に、トクンと鼓動が跳ねた。
「っ、涼介、くん…? 何で…」
『え? 夕方、留守電入れてくれただろ? テニス肘が完治したって』
「え―――…」
『電話もらえると思ってなかったから、嬉しかったよ。完治おめでとう』
夕方電話したのは、凛の筈だ。
なのに何故、こうして電話をくれるのが、涼介なのか?
パニクった香織は、何を返せばいいのか、言葉が出てこない。
『で、オレ、明日午後から予定が空くんだけど…香織さんは?』
「明日…? 急ぎの用事は、無い、けれど…」
『じゃあ、何処か行かない? 散歩みたいな感じで』
「そうね…」
『香織さんのマンションの近くまで行ったら、電話するよ。じゃ』
うにゃー? と鳴くエイリーンは、自分にも話させて、とでも言うように、後ろ足で立って、テーブルに置かれた携帯電話にじゃれていた。
夕方、電話を掛けたのは凛にだった筈。
香織はエイリーンを撫でながら、携帯の発信履歴を確認する。
其処に表示されているのは、《涼介》の名。
凛の携帯番号は、苗字ではなく、ファーストネームの《凛》で登録していた。
《北条》という苗字を、見るのもイヤだったから、そうした。
最近登録したばかりの涼介も、ファーストネームで登録しているのは、響きと字面が好きだったから。
そう、奇しくも2人の名は、ら行に並んでいて―――シッカリ確認せずに掛けた、自分のミスだ。
「登録名…変えた方がいいかしら…でも…」
ニャーニャーと鳴くエイリーンは、香織の手の中の携帯を取ろうと、ぴょこぴょこ跳ねている。
「どうしたの…? エイリーンも涼介くんのこと、気に入った…?」
ニャー! とイエスの返事をするエイリーンに、香織は悲しそうに微笑う。
「北条さんには…懐かなかったのにね…」
いつも自分の気持ちを代弁してくれる愛猫の反応が、ごまかしきれない、自分の本音―――。
|