|
パソコンに向かっていた涼介は、チュンチュンという小鳥の囀りが聞こえて、また徹夜して朝を迎えてしまったことに気付いた。
(今日こそはちゃんと寝ようと思ってたんだが…)
春の終わり、外はまだ薄暗い。
バルコニーに出て、まだ活動を始めていない街を眺める。
まだ明けきらない、夜明け前の時間帯が一番好きだ。
ほんのうっすらと明け始め、空気が澄んでいて、気持ちいい。
完全に明けてしまうと、つまらない。
啓介がよく言っている、《夜明けなんか来なきゃイイのに》という言葉は、涼介も賛同してしまう。
走り屋という行為をしているから、尚更だ。
そう、夜明けなんか来なければ、ずっと啓介と一緒に走っていられる。
そんな話を赤城でしていたら、じゃあ何で赤い太陽なんてチーム名なんだ、と史浩に言われたことがある。
《太陽を盗んで走ってるんだよ》
などと適当な理由でかわしたけど、あながち間違ってはいない。
段々と明け白んでいく空を眺めていると、新聞配達員がポストに新聞を差していった。
(シャワー浴びてくるか…)
流石に少しは眠らないと、実習に支障が出ては拙いので、部屋に戻り、着替えを手に、浴室に向かった。
睡眠さえもコントロール出来てしまう、と言われている涼介は、キッチリ1時間半で目を覚まし、鳴る前の目覚まし時計を止めて、今日もまた目覚まし時計の仕事を奪って起きた。
たまには仕事をさせてくれよ、と訴えられている気がするのを軽く無視して、ベッドから降り、クローゼットを開ける。
着ていく服は、いつも手が掴んだ適当なモノ。
コーディネートなどという面倒臭い事に頭は使わないので、自分の服装が周りにどんな評価をされているかは知らない。
外見で判断されるよりは内面で評価されたいので、涼介にとってどうでもいい事だった。
階下からは、規則正しいリズムが聞こえ、芳しい香りが漂ってくる。
(そうか、もう藍尾さんの来ている時間か…)
多忙な両親は、通勤時間のロスを少しでも無くす為に、病院のすぐ近くのマンションを数年前から借りており、この家には殆ど帰ってこない。
実質兄弟2人きりで、食事と掃除洗濯は、通いの家政婦に来てもらっている。
両親の所へは別の人間が行っているらしい。
そんな事を周りに話せば、何て無駄な、贅沢な、などと騒がれるのだが、群馬の名士として名高い高橋家にとっては微々たるモノで、金は貯め込むより潤滑に流用し、人を雇う事で職に溢れてしまう人間を減らしているのだと思えば、至極当然の結果だと言える。
だが、いくら忙しいとは言え、家族がバラバラというのはいかがなモノか、とは思っているが、夜な夜な峠で爆走行為をしている身にとっては、都合が良いと捉えていた。
洗面所を出ると、もはやそれも朝の支度の一環であるかのように、啓介の部屋のドアをノックする。
「啓介、朝だぞ。起きろ」
だがそれで起きてくることはまず無い。
小さく息を吐いて、そっとドアを開けた。
相変わらず散らかっていて、足の踏み場もない。
涼介が中学校に上がると同時に、兄弟には個室が与えられた。
それまでは涼介も啓介と同じ、この部屋で一緒に机を並べていた。
そう、この部屋には小さい頃の思い出が沢山詰まっている―――筈なのだが、こうも散らかされては、名残も何もあったモンじゃないな、と溜息混じりに、壁を撫でる。
小さい頃は、お絵かきやらなにやらと貼っていて画鋲の穴だらけだったが、大分前に壁紙も新しくしたので、痕跡は残されていない。
尤も、涼介は《思い出》に浸るよりは前を向いて生きていくタチなので、どうでもいい事だった。
この身一つあれば充分―――そう、大事にするモノは、部屋のど真ん中に置かれたキングサイズのベッドでくぅくぅと眠っている弟を大事にするだけでいい。
涼介は通行ルートを見極めるが如く、サッサッとベッドの元まで歩み寄る。
大事な弟・啓介は、掛け布団を抱き締めて、あどけない顔で寝ていた。
もうすぐ21になるというのに、この寝顔は子供の頃と変わらないな、と見つめていると自然と顔が綻ぶ。
ベッドに腰掛けて、眼下で横たわっている啓介の寝顔を眺めながら、子供の頃そうしたように、ツンツンと頬をつつく。
流石にもう大福のようにぷにぷにはしていないが、寝相も子供の頃から変わらないので、涼介には可愛くて仕方がない。
夢や目標が見つからなくて荒れていた時期もあったが、苛々してやるせない啓介の気持ちもよく分かっていたので、何かのキッカケにでもなれば、と赤城に連れて行って、2年が過ぎた。
啓介の次に大事なモノ、自分の《夢》が詰まった、《クルマ》―――。
それは涼介にとって予定調和のうちのつもりだったが、予想以上に啓介はハマり、驚く程に成長している。
自分の《夢》に、啓介を重ね合わせて―――今再び、《幸せ》というモノが訪れている、そんな気さえ、した。
「ん…」
ピク、と啓介の睫が震える。
ゆっくりと目蓋が開かれ、視界に映ったのは、間近で覗き込んでいる兄の顔。
「どわぁっ!」
ビクッとして、啓介は起き上がった。
「何してんだよっ、アニキッ!」
「何って、オマエの可愛い寝顔を見ていた」
ようやく目を覚ました弟に、涼介は背を正し、しれっと微笑む。
「いつからいたんだよっ」
「十分程眺めていたかな。啓介の顔のパーツを観察していた」
「って眺めてねぇで起こせよ! 観察すんな! 何の羞恥プレイだよ!」
真っ赤になって、布団を抱き締めたまま、啓介は叫ぶ。
「ドアをノックした時に言ったぞ。起きろ、って」
それで起きないのが悪い、と言いながら、立ち上がってカーテンを開けた。
明るい陽光が射し込み、啓介は眩しくて目を細める。
「今日も良い天気だな。花粉症の人間は大変そうだ」
「オレ別に花粉症じゃねーし」
言った傍から、啓介はクシャミした。
「…オマエの場合は、ハウスダストだな。自分でやらないなら、藍尾さんに掃除してもらえ、この部屋」
いつも断って、と言いながら部屋を見渡し、呆れたように息を吐く。
「ドコに何があるとか決まってんだからいんだよ! てかアニキ、オレのジーパン踏むな!」
スウェットを脱ぎながら、涼介の足下を見て叫ぶ。
「足の踏み場がないんだからしょうがないだろう。踏まれたくなかったら少しは片付けろ。何の為のクローゼットだ? オマエの部屋に床はあるのか?」
足の下になっていたジーパンを拾い上げ、ゴミクズをパンパンと手ではたき落としてやって、啓介に投げた。
啓介はぷぅと膨れつつも、今日は穿かねーモン、と反対側の床に落ちていたカーゴパンツを拾い上げ、ゴソゴソと足を通す。
「支度が済んだら早く降りてこいよ」
涼介は先に階下のLDKに向かった。
(あーもー、マジビビッた…; 何かガキの頃の夢見てたから、アニキと一緒に寝ててアニキに起こされるトコだったから、目ェ開けたらちっこい筈のアニキがデカくてビビッたっつーの…;)
啓介は頬を染めながら、洗面所に向かう。
「お早う御座います、藍尾さん」
LDKにやってきた涼介は、食卓を調えている女性に声を掛けた。
「あら、お早いですね、涼介さん。お早う御座います」
両親がマンションを借りてから来るようになった家政婦だが、それ以前に時々来ていた家政婦よりは印象が良い。
何より、人見知りしやすいタチの啓介が懐いてるので、そのせいかも知れない。
「啓介もすぐに来ますから」
そう言って、啓介を待って、新聞の一面に目を通す。
「ハヨース」
LDKのドアを開けながら、まだ眠いのか、啓介は欠伸しながら、ダイニングに向かった。
「お早う御座います、啓介さん。今日は啓介さんの好きな豚肉の生姜焼きですよ」
「やった♪ 莱子サン、オレメシ大盛りねー」
「朝食の献立じゃないと思うんだが…いつも啓介の我が儘を聞いてもらってすみません」
サンルーム傍のテーブルセットで新聞に目を通していた涼介も新聞をラックに戻して、食卓に着く。
「いいんですよ、男の子は朝からシッカリ食べないと」
啓介には大盛り、涼介には普通盛りでよそって、それぞれに置くと、洗濯と掃除の為に、LDKを出て行った。
「いただきます」
「イタダキマース」
涼介と啓介は向かい合わせに座って、キチンと手を合わせて、食べ始める。
「アニキ、今日は何時頃赤城に来れる?」
モゴモゴと頬張りながら、啓介は向かいの涼介を伺った。
「そうだな…早くて20時だな。21時くらいになるかも知れん」
「じゃあオレ飯どうすっかなー。夕方ヒマだし、ウチ帰ってきて1人で先に飯食うの侘びしーんだよなー。でも腹減るしなー…」
「チームの誰かを誘ってファミレスで食べればいいだろう? 最近オマエに懐いてるヤツがいるだろう、1軍に上がってきたケンタとか…」
藍尾さんの作ってくれた食事は夜食に食べればいいし、と言いながら味噌汁を啜る。
「ケンタも他のヤツもバイトしてっからメシ時は捕まらねーんだよ。史浩も院の方でやることあっから遅くなるとかゆーしさ…平日はこれだからヤなんだよなー、大学の後すっげーヒマ。オレもバイトでもすっかなー、でもオレ何が出来んだろ…」
「小遣いなら充分に渡してるじゃないか。まぁ社会勉強は必要だと思うが、それならオマエには理論を覚えてもらいたいがな。その用意ならいくらでも出来るぞ?」
「げっ。無理無理、オレはアニキじゃねーんだ、そーゆーのオレには無理! だったらその辺ドライブしてる!」
咀嚼していたモノをゴクリ飲み込んで、啓介は顔をしかめた。
「そう言えば群大でもバイト探してたな、結構割の良い」
「何?」
「その身一つで出来るからオマエにも簡単だ、実験体―――」
「実の弟に何やらす気だッ!」
「冗談だ」
穏やかな、これが最近の日常。
あれから数日。
大学にて、啓介は気まぐれで手に取った学生向けアルバイト情報誌を持ち帰り、講義が終わった後、一旦帰宅した。
涼介は群大までの片道が40分前後かかるが、啓介は自宅から程近い私立大学の為、大学が終わった後に自宅で夕食を食べて赤城へ、というコースは涼介を思えばロスがない。
「ただいまー」
外に藍尾の車は無かったので、家には誰もいないと分かっているのだが、誰もいなくとも、出掛ける時の「いってきます」と帰ってきた時の「ただいま」は必ず言うよう、涼介から躾けられていた。
兄の言うことは絶対である啓介は、今日もキチンとそれを守って、玄関を上がる。
ダイニングに残された藍尾のメモを読んで、キッチンに行って今日の夕飯の献立を確認すると、もう一度メモを見た。
《午後に涼介さん宛に例の宅配が届きましたので、涼介さんの部屋の前の廊下に置いておきました》
いつもなら、郵便物も宅配もリビングにまとめて置いてあるのに、と啓介は首を傾げる。
(てか、例のって…何だ?)
階段を上がっていくと、涼介の部屋のドアの前に置かれていたモノは。
「何だこのデッケェ段ボール…」
幅1m超はありそうな、横長の段ボールが置かれている。
「何だぁ…? また変なオブジェとか部屋に飾るとかか?」
ジロジロと箱を見渡して、何の気無しにちょっと持ち上げてみたら、意外と軽かった。
(何だろ…おかしなモンじゃねぇだろうな…?)
まぁいいや、と啓介は隣の自室に向かう。
部屋主にしか分からない定まったルートを辿って、唯一綺麗なベッドの上に辿り着くと、暇潰しのつもりで持ち帰ったアルバイト情報誌を開いて、寝転がった。
(オレに出来るバイトって何だろなぁ…肉体労働とかのがやりやすいかも…)
これまで、全然バイトをしたことがない訳ではない。
啓介がクルマの免許を取った時に、涼介がポケットマネーでポンとFDを買ってくれて、その代わりガソリン代は自分で稼げ、と言われ、高橋総合病院に併設されている特別養護老人ホームにて、主に肉体労働の雑用をしていたことがある。
母親が管理責任者の為、キチンとした手続きをして雇われている訳ではなく、シフトも決められてはおらず、啓介の自主性に任せていたり、人手が足りない時に手伝ったり、とオウチの手伝いをする子供、状態なので、一応、《給料》という扱いだが、母親から小遣いを貰っている感覚だった。
(別にあそこでもいーんだけどさー…融通利く訳だし…)
大学卒業後はプロのレーサーになる、と決めているので、それ以外のことに興味が持てない自分は、やっぱり甘チャンかなぁ、と思ってしまう。
(アニキのお陰で、夢や目標が出来て、退屈で苛々した毎日にサヨナラ出来たんだ…アニキは長男だから、親父の跡継がなきゃなんなくて…オレがアニキに出来る恩返しは、アニキに教わったことを全部活かして、メジャーな世界でビッグになってみせる…アニキはこんなにスゲェんだ、って世界中にだって教えてやるんだ…)
いつの間にか眠っていた啓介は、目を覚ますと、ぐぅと腹が鳴った。
藍尾の用意していった夕食を温めて、1人淋しく手を合わせて食べると、赤城に向かった。
(アニキと一緒にいられるのは後2年だモンな…アニキはずっと群馬にいるけど、でもオレは…)
ヤンチャ時代の無駄な日々を思い出し、出来るだけ一日一日を、涼介と過ごす日々を大切にしていきたいな、と啓介は思った。
向かう所負け知らずのレッドサンズ、その揺るぎないナンバー1と2である高橋兄弟は、女のコ達からの人気も絶大だった。
2人が赤城に来ている時といない時では、峠の賑わいが格段に違う。
今日も今日とて、女達は涼介と啓介、どちらかにお近づきになれないか、虎視眈々と機会を狙っていた。
その騒ぎに、ヤレヤレ、と史浩は息を吐いて煙草の煙を吸い込んだ。
「全く、雑誌に写真が載ってから更に増えたよな、女のコのギャラリーも…涼介と啓介それぞれにファンクラブも出来てるってホントか?」
「さーな。オレの知ったこっちゃねぇよ」
黄色い声にウンザリ、とでも言いたげに、啓介も煙草を燻らせる。
「オマエら2人とも、あんなにモテるのに、カノジョがいないから、余計にあの女のコ達も騒ぐんだろ。よりどりみどりだろうに、誰か特定のカノジョでもいた方が良いんじゃないか?」
それは彼らを知る者なら、誰もが思っていることだった。
「…彼女を作っても構ってやれる時間がないからな」
「会う時間作るとかメンドクセェじゃん。そんなんに時間使うくれーなら、峠攻めるっての」
これもお決まりの返し文句。
だが2人の心の中は、こうだった。
(啓介より可愛い女なんかいないんだ、その辺の女より啓介の方がよっぽど可愛い)
(アニキよかキレイな女なんかいねぇっての。どうしても比べちまうんだよなー、アニキの方がキレイだって)
そう、涼介と啓介はドン退きされる程の、ブラコンの仲良し兄弟だった。
その心の声は、レッドサンズの連中の間では既に駄々漏れで、度が過ぎる程の仲の良さに、下っ端の間でドコまで仲が進展していくか、賭けにされているとかいないとか。
「あ、そうだアニキ、家にさ、何かアニキ宛のデッケェ荷物が届いてたぜ」
思い出したように、啓介は涼介を見遣る。
「そうか? 思ったより早く届いたな」
チームの走行データ表から顔を上げ、フッと笑った。
「何買ったんだよ? また変なオブジェか?」
「アレはベッドサイドのルームランプだから変なオブジェじゃない。タッチセンサー式だから便利なんだ」
「アニキ時々変なモン買うからさー…」
「フッ、まぁ帰ってからのお楽しみ、かな」
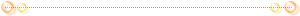 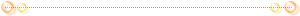
啓介は涼介の部屋に行って愛機FDのキーを取ってきて、革ジャンを羽織って、玄関に向かった。
「いってきマス」
足早にガレージに向かい、久し振りの愛機のボディを愛しそうに撫でる。
ドアロックを解除して運転席に乗り込み、エンジンを駆けた。
一週間振りの、心地好いロータリーエンジンの微振動に、瞳を閉じて、じっくりと味わう。
(ったく…何でコンナコトになっちまったんだよ…? やっとアニキのトコに戻って来れたと思ったら、何で《オレ》がもう1人いる訳? やたらとゴーイングマイウェイでオレ様だし…オレってあんなか? 違ぇだろ、ゼッテェ…)
涼介に比べたら頭が柔らかくて難しいことを考えない啓介は、もう1人の《自分》が現れたことに、色々と納得は出来ないが、理屈や原理などは考えていなくて、今はもう、当たり前のように《自分》として兄に接せられたり、《自分》として振る舞われているのが、面白くないだけになっていた。
とにかく愛機FDのロータリーサウンドを楽しんで、落ち着こう、と小さく深呼吸を繰り返す。
そして落ち着いてきたかな、と閉じていた瞳を開くと、《啓介》がドア越しに自分を覗き込んでいた。
「いっ?!」
啓介は慌てて、ドアを開けてFDから降りる。
「何オマエ外に出てんだよ?!」
屋敷は植え込みと塀に囲まれているから他人の目には付かないのだが、つい隠そうと《啓介》を抑え込んだ。
フードを被せて、キョロキョロと辺りを確認する。
『なぁ、オレにもFD運転させろよ』
「はぁっ?! ふざけんな、させる訳ねぇだろ! いいからオマエはウチん中戻れ!」
アニキは何で目を離してんだよ、と容疑者を護送するように《自分》を隠して、ズカズカと玄関に向かい、中に《啓介》を放り込む。
『ちぇー、ケチー』
という文句が聞こえたが、啓介は折角落ち着いたのにまた苛立ちながら、FDに乗り込んだ。
トイレに行っていた隙に《啓介》が外に出ていたとは気付かなかった涼介は、ついトイレ内でアレコレと考えてしまって時間が過ぎて、トイレから出た時には、《啓介》は応接室や続き小部屋を眺めていた。
『ライ子サン、キレイに掃除してんなー。使ってねぇ部屋ばっかなのに、ご苦労なこった』
他人のそら似でもない、《本人》なのだから、そうしていると、啓介と過ごしているいつもの日常と錯覚してしまう。
「それが藍尾さんの仕事だからな」
涼介は啓介の北海道土産を一つ一つ確認して、散らかしたゴミは捨て、リビングで新聞を広げた。
まず一面に目を通していると、ソファの後ろから、《啓介》が抱きついてきた。
「な、何してる…」
思わず動揺し、きゅっと新聞に皺が刻まれる。
『アニキの傍にいてぇからさ。新聞邪魔だから後ろから』
少し高いウェットな声が、耳元で囁く。
色を帯びた声音に、涼介はぞくりとしてしまう。
クスッと笑われた気がした。
『アニキ…耳で感じたのか?』
ふぅ、と熱い吐息を耳に吹きかける。
涼介は身体の奥がドクンと跳ねて、身を震わせた。
「な…何を…」
『脈が速くなってるぜ…アニキ…アニキが本当に欲しいモノって、何だ…?』
「え…?」
『オレの部屋の床とかじゃなくてさ…《モノ》とかで無いのかよ…?』
何でそんなことを知っているんだ、とそれは自分と啓介しか知らない筈。
いや、史浩には話したか。
だが、この《啓介》が知っている筈がないのに―――どういうことだ?
「―――…っ、オレは、モノには拘らない、から…」
『じゃあ、さ…《ヒト》とかは…?』
「…どういう、意味、だ…? ヒト、なんて…手に入れたりするものじゃ、ない…だろう?」
ふっ、とまた《啓介》は笑う。
『ついこの間、秋名のハチロクが欲しいって、ドライバーとしての能力が欲しい、って言ってた癖に。県外遠征やる為に、色んな人間、自分のゲームの為に集めてる癖に…ソレだってアニキが手に入れてる人間達だろ? 澄ました優等生な模範解答なんて、オレの前じゃしなくてイイんだよ』
何でそんなことまで知っている?
いくら啓介と同一人物だと言っても、《記憶》まで共有しているというのか?
「…ほ、本当に、オマエは、《啓介》、なの、か…?」
『緒美にでも見えるか? 何度も言ってるだろ? オレはアニキの弟、《啓介》だ。アニキのコトは、オレが一番よく知ってるんだぜ…? 幼馴染みの親友の史浩より、弟の《オレ》がさ…』
動揺を促す囁き。
床に新聞がバサリ落ちて、背もたれを跨いできた《啓介》は、長ソファに涼介を押し倒し、その上に跨いで、のし掛かった。
「ちょ、待て…っ」
『だから、アニキが本当に欲しい《モノ》も《ヒト》もよく分かってる…でもオレは、アニキの口から、直接聞きてぇ』
涼介に覆い被さり、節くれ立った大きな手が、這うように、上衣をたくし上げていく。
「な、何言っ…」
『アニキ…オレのコト、好き?』
「え…」
『オレはアニキのコト、好きだよ。大好き。アニキは?』
啓介は涼介にとって、可愛い弟で―――それが、《男》に見える。
涼介の心臓は早鐘を打っていて、その雄々しさに、まるで《啓介》に囚われてしまったようだ。
『何ですぐ言わねぇの? ガキの頃なら、いつも《オレも啓介が好きだよ》ってすぐ言ってくれたのに』
「え…あ…好き、だよ」
上衣をたくし上げられ、腹部から胸部へと撫で回されて、その感触に、ビクンと反応してしまう。
『どういう風に?』
「どうって…たった1人の、可愛い弟…オレの一番大事な…」
『優等生な模範解答はしなくてイイって言ったろ? アニキの本音を聞かせてくれよ』
「オレの…本音…?」
戸惑っている涼介の上で、《啓介》は余裕綽々ともとれる表情で、涼介の身体に手を這わせている。
『もしかして…自覚してねぇのか? アニキの本音…本当の気持ち…本当はどうしたいか、どうされたいのか…』
胸を撫で回していた手が、親指の腹で、強く乳首を押し潰す。
ビクンと痺れたように、涼介は身を捩った。
ウェットな高音が音楽のように紡がれ、それが余りにも魅惑的で、涼介の頭も心も、《啓介》に支配されかかっている。
熱にうかされたように、潤んだ瞳で《啓介》を見つめた。
『オレにはアニキだけだからさ…アニキの為なら、何だってやれる…何だってしたい…だから、こうして…』
雄々しい顔で、ゆっくりと涼介にのし掛かって、顔を近づけていく。
涼介はスッカリ囚われてしまったかのように、紅潮して、されるがままになっていた。
唇と唇が、ゆっくりと重なり合う。
脳天が痺れるような、甘美さ。
「…んっ」
身体の奥がドクンと脈打ち、思わず声が漏れる。
男同士で血の繋がった兄弟なのに、キスをして、少しも嫌ではない―――嫌どころか、もっと、と欲している自分に気付く。
そうか、自覚していなかったというのは、啓介への、本当の気持ち―――。
肉親としての度が過ぎた敬愛の情だけではなくて、もっとそれ以上の、俗物的な、想いだったのだ、と。
それを、《啓介》によって、気付かされた。
ふっと力んでいた身体の力が抜けた時、ゆっくりと《啓介》は口付けから離れた。
『…分かった?』
まるで見透かしたかのような、《啓介》の言葉。
涼介はかぁっと赤くなる。
『じゃあ、アニキの本音…聞かせろよ』
「―――っ、好…」
導かれるままに口を開いたその時、ガタンガタンと大きな物音がリビングに響いた。
『ちっ、もう帰ってきやがった』
「なっ…、何してやがるーッ!」
リビングのドアの前で、抱えていた箱ビールを床に落とした啓介が、ソファの上で繰り広げられている光景に、声を上げた。
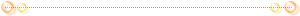 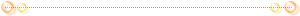
食後、啓介は《啓介》の分の食事をトレイに、部屋に戻る。
「ホレ、メシ持ってきたぞ」
『アニキはー?』
大きな枕に身を預けたまま、《啓介》は問うた。
「出掛ける支度してる。昨日ギリギリだったから、今日は早めに行くって。オレは近ぇから、まだ時間あっけどな」
ベッドに腰掛けて煙草に火をつけながら、壁向こうを指す。
啓介がのんびり煙草を燻らせていると、部屋のドアがノックされる。
「入ってマース」
「…3回ノックしたんだから、トイレみたいな返しをするな」
ドアを開けながら、涼介が呆れたように顔を覗かせる。
それまでベッドに突っ伏していた《啓介》は、ぴょこっと起き上がって、涼介の元に駈けていった。
「オレは大学に行ってくるから、藍尾さんに見つからないように気を付け―――」
『いってらっしゃいのチューv』
涼介の言葉を遮り、《啓介》は節くれ立った大きな手で涼介の両頬を包み込み、ちゅう、と口付けた。
「…っ、見つからないように気を付けろよ。いってきます」
『いってらっさーい♪』
「いってらっさい…って、新婚夫婦みてーなことすんな」
紫煙を吐き出しながら、啓介はじろり睨む。
『だったらオマエも一緒に、両手に花でアニキ見送りゃ良かったのに』
ふんふんと鼻唄混じりに、《啓介》はベッドの上に戻った。
「あー………じゃあ今度」
昨夜強引に眠らされた時のまま、パンツ一丁だった《啓介》は、ひょこっと啓介から煙草を一本拝借して、銜える。
喫煙者の習性か、啓介は無意識にライターをつけて《啓介》に向けた。
「メシ食わねーのかよ?」
傍らで煙を吸い込んでふ〜っと吐き出す《啓介》に、啓介は伺う。
『もちっと後でな。昼飯ねぇから、腹減るし』
あぁそうか、と思いながら、短くなった煙草を灰皿で捩消し、次の煙草を取り出す。
「…オマエってさ、何狙ってんの?」
『何って、何が?』
「オレとアニキをどうしたい訳? 何したいんだ?」
散々振り回して、と部屋中に煙が立ち込める中、《啓介》に尋ねる。
『んー、オレとアニキが仲良くラブラブ暮らして、アニキが幸せだなーって思ってくれてれば、それでいい』
「アニキが幸せ、か…まぁオレもそうあって欲しいと思うけど、取り敢えずはアニキのゲームの為に全力尽くすことくれーしか今は考えらんねーなー」
『言ったろ? アニキの夢は、オレがずっとアニキの傍にいることだって。でもオマエは、プロのレーサーになる為に、アニキの元から離れてくだろ? アニキはソレを叶えてやる為に、ドラテクや知識を叩き込んでくれてるけどさ、本心は離れていって欲しくないって思ってる。でも、オレならずっとアニキの傍にいてやれる。オマエは、自分の夢や目標を叶えりゃいい。《オレ》はずっとアニキの傍にいるから』
《啓介》の言葉を聞いていた啓介は、まだ長いままの煙草を、灰皿に押しつけ、立ち上がった。
「大学行ってくる」
『いってらっさーい』
大してモノの入っていないショルダーバッグを背負って、玄関に向かう。
「いってらっしゃいませ」
「いってきマス」
藍尾に見送られ、ガレージの愛車に向かう。
エンジンを駆け、暫しその微振動をその身に感じる。
暖機運転を済ませ、ゆっくりと発進した。
(アイツの言いてぇコトは分かる…でも、ソレって何か、違わねぇか…?)
夜、涼介が自宅に帰ると、ガレージにはFDは無かった。
少し前まで、いつも峠で一緒に走っていたのに、擦れ違いの多さに、淋しさを感じないと言ったら、嘘になる。
でも、四六時中ベッタリと一緒にいるだけが、正しいとは思わない。
啓介とは、目指す先は、違っている。
その目が見ているモノも、違ってきている。
でも、志は、同じだと思っている。
(多分…《アイツ》はそれを分かっていないんだ…)
LDKに電気が点いているということは、《啓介》は其処にいるのだろう。
きっと、この兄を待って。
「ただいま」
『おかえりー!』
天真爛漫な、太陽のような笑顔が、涼介を出迎える。
眩しくて、啓介そのもの、だけれど。
けど―――。
『おかえりのチューv』
まだ靴を完全に脱いでいない涼介に、《啓介》は首に手を回し、ちゅ、と口付けた。
「こら…っ、玄関ではやめろ」
『玄関じゃなかったらいいのかよ?』
「そうじゃない」
やんわりと《啓介》の抱擁を解いて、玄関を上がった涼介はまっすぐに階段に向かった。
『アニキー、すぐメシ食う?』
「あぁ。オマエはもう食べたのか?」
『腹減ってたからアイツ帰ってきた時に一緒に食った。じゃああっためてるなー』
「有り難う」
部屋に鞄を置いてジャケットを脱いで、涼介は再び階下に降りてくる。
LDKに入ると、《啓介》がマメマメしく食卓を調えていた。
確かにこういった所は本物の啓介よりはテキパキと働くな、と思った。
(まぁ、アイツと2人だと、オレの方が全てやってしまうからな…)
『へへっ、アニキの専業主夫みてーだろ』
ニカ、と《啓介》は笑う。
そうありたいと願っているであろう、《啓介》。
そんなモノにはならなくていい、と言ったら、コイツは傷付くだろうか。
「有り難う」
それだけ言い、涼介は食卓に着いた。
「いただきます」
涼介が静かに食べ始めた向かいで、《啓介》はビールを呷っている。
目が合うと、ニカッと笑う。
一緒にいられることが嬉しい、そう言いたげだ。
「ずっと啓介の部屋に籠もっていたのか?」
『んー、ライ子サンが買い物出た時に、そこのコンビニに雑誌買いに行ってきた』
けろっと言う《啓介》に、涼介は食べていたモノを喉に詰まらせ、咽せた。
「…っ、部屋に籠もっていろと、あれだけ…」
『ライ子サンに見つからなきゃ、高橋サン家の次男が日中フラフラしてたって、誰も気にしねーよ。史浩ン家の工場とは逆方向行ったから、知り合いにゃ会ってねーから、ダイジョブだって』
グラスの水で喉を潤して、涼介は息を吐く。
史浩は院の方に行っていただろうが、もし松本や宮口らに会っていたら、いやコイツならそつなく疑問を抱かせることもなくかわしていただろうが、自由すぎるこの行動には、冷や冷やさせられる。
「金はどうしたんだ?」
『昨日アイツの財布持ってったからさ、小銭だけ貰っといたから』
千円札何枚か、と言いながら、ビールを飲み干して、次のビールを取り出しに、席を立つ。
「おかしなことはしなかっただろうな? 赤城まで行って…」
『アニキまでソレゆーのかよ? してねーって。レッドサンズのヤツらとちっと話して、後は峠走ってきただけだって。楽しかったなー』
話した内容が気になって、涼介は何故か背筋に冷や汗が走った。
|