|
少し離れた後方で、NSXがスピンしたのは分かっていた。
オレの勝利はもう確定したも同然だった。
でも、僅かにでもアクセルを緩めることはしなかった。
最後まで、渾身の走りを続ける。
ゴールはもう、すぐソコだ。
終わっちまう。
もうすぐ、プロジェクトDが終わっちまう。
ゴールするのが淋しくて、一年にわたって続けてきた遠征のフィナーレを、1秒でも長く、味わっていたくて。
クルマから降りたくない、永遠に走り続けたい、この幸せをずっと味わっていたい。
色んな感情が押し寄せる中、それでも胸に去来したモノは、たった一つ。
『アニキ―――…』
◇ ◇ ◇
ドクン、ドクン、ドクン…。
ゴールまで近付いてきている。
ヒルクライム2本目、先行するFDが、後追いのNSXを徐々に引き離していると、ギャラリーからの報告があった。
我知らず、きゅっと拳を握り締めた。
ドクン…ドクン…ドクン…。
逸る鼓動は、抑えられない。
昂ぶる感情を、周囲に悟られないよう、ゴクリ唾を飲み込む。
喉はもう、カラカラだ。
ゴールはもう近い。
間もなく、愛する弟が、戻ってくる。
自分の元へ―――。
サイドワインダー陣営が、突如ざわついた。
「エ…ッ、NSXがッ、スピンしたって―――ッ!」
そんな声が聞こえた。
握り締めていた拳に、グッと力を込める。
FDの、勝利を確信した瞬間―――。
宮口が、松本が、拓海が、喜びの声を上げる。
ギャラリーも多く集っているこのドライブインでも、プロジェクトDのヒルクライムのパーフェクトウィンの決定に、俄に騒然としてきた。
間もなく、目の前のゴールに、勝利したFDが飛び込んでくる。
箱根の山に響き渡っていたロータリーサウンドが、一際大きく、轟いた。
すぐそこまで来ている。
出迎えるべく、ゴールライン間際に駆け寄るプロジェクトD陣営。
高鳴る鼓動を抑えきれないまま、何故か涼介は、今この瞬間、子供の頃のことを思い出していた。
小さな啓介が、自分の元へと駆け寄ってくる姿。
いつも自分の後を追い掛けてきて、この胸に飛び込んできて。
涼介はそんな弟が可愛くて、愛おしくて、手を広げて抱き留めていた。
腕の中にすっぽり収まった小さな弟は、今やスッカリ大きく成長して、自分とほぼ同じ体格になってしまったけれど、今も昔も変わらず、戻ってきたら抱き締めてしまいそうで、取り敢えず公共の場でそれは自制しなければ。
などと思っていた、その時。
真っ黄色の火の玉ロケットが、一際甲高いロータリーサウンドを響かせて、ゴールを切った―――。
そう、自分の元へ、戻ってきた―――筈なのに。
美しい羽根の生えた、光〈オーラ〉を放つ黄色いFDは、目の前をコンマ1秒もスピードを緩めることなく、走り抜けていった。
まるで、そのまま遠くまで羽ばたいていってしまうかのように―――…。
喜びに盛り上がる宮口らを横目に、涼介は呆然としていた。
握り締めていた拳の力も緩み、ゆっくりと開いた手のひらを見つめる。
其処にある筈の《もの》が、するり抜けていったかのようで―――。
あぁ、そうか―――…。
自分を追い掛け、胸に飛び込んできていた存在は、もう自分を追い越し、自分の力で、その羽根で羽ばたいていくんだ。
騒然と盛り上がるドライブイン駐車場で、涼介はただ、立ち尽くしていた。
「啓介さん、何処まで行っちゃったんだろ。なかなか戻ってこないや」
FDが走り抜けた先を見つめていると、NSXもようやくゴールした。
ゆっくりと降りてきた、北条豪。
何となくその様子を見ていた拓海は、スタート前とはまるで別人のように、憑き物が落ちたようなスッキリした顔をしているな、と思った。
それがイコール、このバトルの質を物語っているのだろう。
対戦相手をここまで変えてしまう、啓介さんってスゴイな、と思いながら、ヒルクライムの勝利に浮かれてないで、自分は自分のバトルに気持ちを切り替えねば、と思った瞬間、下から聞こえてきたエンジン音。
今まで姿を現さなかった、ダウンヒルの対戦相手のクルマ。
自分と同じ、ハチロク。
『あのクルマ…出来る…!』
随分先まで走り抜けていったFDが、ウィニングランからようやく戻ってきた。
東日本最速のヒルクライマーの勇姿が駐車場に降り立ち、ギャラリーは一層盛り上がる。
熱に浮かされた夜の峠で、啓介はトリを務める拓海にバトンタッチという名のハイタッチで、思いきり強く手をひっぱたいた。
それをただ、眺めていた涼介。
いつも真っ先に自分の元に駆けてきた小さな弟は、もう自分を必要としていないのではないか。
そんな寂寥感に包まれ、まだダウンヒルがあるのに気持ちを切り替えろ、と自分で自分を叱責する。
自分が認め、口にしていた筈なのに。
《ダブルエースはもうオレを超えている》
喜ばしいことなんだ。
残すところあと一つ、ダウンヒルのことだけを今は考えろ。
そんな風に脳内で葛藤と叱咤を続け、人知れず立ち直ろうとしていたところへ。
「アニキ」
まっすぐに、ずんずんとやってくる啓介。
「―――勝ったぜ、アニキ」
精悍な顔立ち。
暗い夜の峠でも、太陽のように眩しいその笑顔。
逞しく、頼もしく、愛おしく。
まだバトルの余韻を残して若干興奮気味の弟は、まるで百点満点を取ったテストの答案を見せてくるような、子供っぽさも持ち合わせていて、自分の中に去来した不安感は、すぅっと流れて消えていくのを感じた。
「―――あぁ。ご苦労さん」
啓介がゴールした時、かける言葉はいくつも考えていた。
でも、咄嗟に出てきたのは、至極ありきたりなモノだった。
これまでの道程が走馬燈のように蘇ってきて、感極まるとはこのことだろう、変に飾った言葉よりも、いつも通りの方がいい。
確かにこの最終戦で勝利を得た。
長く続いた遠征も、残る一つ、ダウンヒルで終わる。
だが、ゴールは終わりではない、これから先も続いていく次のスタートの始まりなのだから、それでいい。
「水飲むか」
「あーうん。全く夜だってのにあちーな。喉カラカラだぜ」
涼介は1号車から、ミネラルウォーターのペットボトルを持ってきて、啓介に渡した。
パキュッとキャップを捻って、ゴクゴクと喉に流し込む、上下する喉仏に、飲み干した時の癖、ペロリ口の周りを舐めるその様子に、淫らな感情が首を擡げてくる。
そんな自分に、プロジェクトDの最終戦の真っ最中なのに、集中出来ていないんじゃないか。
余りにも眩しい存在に成長してしまった啓介のせいだ。
心が動くのは、心乱されるのは、いつも啓介のせいなんだ。
◇ ◇ ◇
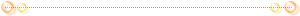 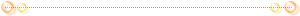
◇ ◇ ◇
涼介の部屋で、裸のまま抱き合って、短い睡眠に身を委ね、目覚まし時計によって眠りの縁から引き戻された、朝。
卒論も既に提出した啓介は、夏休みが明けても大学へと行かねばならない理由はなく、このまま惰眠を貪っていたかったが。
多忙を極める医大生の兄は、医師国家試験を年明けの2月に控え、いつも通り朝から出掛けなければならなかった。
涼介が起きるなら、自分も起きて一緒に朝食を摂り、それから二度寝しよう。
そう思い、母親が用意していった朝食を、食卓に調える。
「啓介と一緒に朝食を食べるのは、久し振りだな…」
いただきます、と手を合わせ、箸を口に運ぶ。
下半身に残る鈍痛が、幸福を反芻させて、心地好い。
「オレいつも、アニキの出てく時間にゃまだ寝てたからな。アニキあんま寝てねぇのに、だいじょぶかよ?」
イタダキマース、と手を合わせてすぐさまガツガツと食べながら、向かいの兄を見遣る。
疲れも感じさせない程に、今日も最愛の兄は麗しい。
「帰ってくる道中に眠っていたからな。オマエの方こそ、殆ど寝てないんだから、シッカリ休むんだぞ」
「んー。久し振りにアニキとえっち出来たし、疲れも吹っ飛んじまったよ」
おもむろにのたまう啓介に、涼介は思わず咽せて咀嚼していたモノを吹き出しそうになった。
自分達の他に誰もいないと分かっていても、つい周囲を気にしてしまう。
「あのな…疲労ってのは見えないところに溜まっているモノなんだ。オマエが今大丈夫と思っているのは、まだナチュラルハイの状態が続いているだけだ。休める時にはシッカリ休め。それも仕事のうちだと、遠征の間に学んだことだろう?」
「へーい」
食べ終わって、啓介が食器洗いをしている間に、涼介は自室に戻り、支度を済ませて降りてきた。
「アニキ、コーヒー出来てるから、飲んでけよ」
「あぁ、有り難う」
熱いブラックコーヒーが、身体に染み渡っていき、まだ眠っていた神経も、完全に覚醒した。
啓介の煎れるコーヒーは美味しい。
自分では殆ど飲まないのに、家で煎れるのは、もっぱら涼介の為だった。
兄の好みを完全に知り尽くした、絶妙な味加減に、家でコーヒーを飲む、それだけのことでさえ、嬉しく感じる。
「天気予報じゃ今日も暑いっつってたけど、今イイ感じに曇ってっから、FDメンテに持ってく前に、洗車でもすっかなー」
工場にメンテナンスに持ち込めば、サービスで洗車もしてくれるのだが、激戦を終えた愛機に、自分の出来るメンテナンスは自分でやりたいと思い、まず綺麗にしてやりたかった。
洗い物を終え、手を拭いて啓介は玄関を出て行く。
キーホルダーを手の中で踊らせながら、ガレージの前まで来た時、その足は止まった。
コンペティションイエローマイカのFDの隣に、クリスタルホワイトのFCが停まっているのだ。
明け方帰ってきた時には、まだ無かった。
一体いつ、戻ってきたのか。
いやそれよりも、この外観は。
カーボンボンネット。
でっかいウィング―――ケンタが言っていた通りだ。
きっと見えないところも、アレコレと弄ってあるように見受けられる。
何て攻撃的な、戦闘力の高そうなマシンだろう。
その妖しいまでの美しさに、見惚れてしまう。
呆然とその鎮座在すFCを見つめていると、涼介がやってきた。
その足はまっすぐと、愛機FCに向かっている。
「あ、アニキ、コレ―――」
「啓介、曇っているといっても紫外線は強いし、暑いことに代わりはないから、熱中症に気を付けろよ」
そう言い放ち、FCに乗り込み、エンジンを駆ける。
アイドリングしながら、サイドウィンドウがするすると開く。
「啓介、プロジェクトDの解散の打ち上げ、どういう形式がいいか、考えておいてくれるか? 今日は何時に帰ってこれるか分からないけど、帰ったら決めよう」
「う、うん。分かった、考えとく」
いってきます、と告げ、FCは近所迷惑な音を響かせながら、ゆっくりとガレージを出て行く。
啓介はただ呆然としたまま、その姿を見送った。
「な…何だよ…あのFC…」
|