夕方になり、チームの溜まり場に向かう途中、潰れた店の駐車場で何やら暴れている連中が目に付いた。
紅蠍隊と敵対するチーム、愚連隊の連中だ、と抗争で見知った顔を見つけて単車のスピードを緩める。
一般人を相手に一方的に暴行を働いているようで、相変わらずロクでもないチームだな、と啓介は暴行現場に割って入り、一般人を逃がして、一人抗争に身を投じた。
喧嘩をすることでしか、靄靄した鬱憤は、晴らせなかったから―――。
「お巡りさん、こっちです!」
通行人が警察を呼んだのか、大通りの方から声がして、愚連隊の連中は慌ててその場から逃げていった。
啓介も逃げようと思ったが、多勢に無勢だったので怪我を負い、疲労もあってすぐには動けそうもない。
あぁ、また親呼び出しになってしまう―――そう覚悟したのだが、一向に警察官は来なかった。
「……?」
軋む身体を押さえ荒い息を整えながら、声がした方を見遣る。
「其処にいるのは…高橋くんか…?」
夕闇が深まってきた大通りを行き交う車のライトに照らされて浮かび上がったのは、前崎涼介の姿だった。
「前崎…センパイ…? 何で…警察は…」
「方便だよ。あぁ言えば取り敢えず収まるかと思って…まさかキミだったとは…大丈夫か?」
駆け寄ってきて、様子を伺う。
「大したこと…ねぇよ…ちっと疲れただけ…センパイは何で此処に…」
息は上がっているが、地べたにへたり込んでいたのを、ゆっくりと立ち上がる。
「其処の書店に来ていたんだけど、店を出たら、不良に絡まれていたのを助けてくれた人がいて、逃げてきたけど助けてくれた高校生が大丈夫か気になる、って言っていたサラリーマンがいて、気になって来てみたんだ。怪我をしているじゃないか。オレの家が近くなんだ。手当てをするから、おいで」
あのサラリーマンは近所の医院に行ったから大丈夫だよ、と手を差し伸べる。
だが照れ臭くて、その手は取らなかった。
啓介は歩けない程重傷ではなかったが、単車は涼介が押して、程近い前崎家に連れていかれた。
「此処だよ。さぁ上がって」
会社経営している家らしく、住宅街の中でも立派な門構えの家だ。
「へー…結構デカイ家じゃん」
「キミの家程じゃないよ。バイクは此処に停めておいてもいいかな」
ガレージの脇にバイクを停め、玄関の鍵を開ける。
「あーうん。えっと…お邪魔、シマス…」
三和土で所在なさげにキョロキョロと屋内を見渡していると、ちょいちょいと手招きされ、靴を脱いで恐る恐るついて行く。
リビングに通され、促されるままにソファに腰を下ろすと、涼介は救急箱を持ってきた。
「…親はいねぇの? 夕方なのに」
奥のダイニングには夕食は用意されているようなのだが、他に人気を感じないので、傍らで傅く涼介を伺う。
傅く前崎涼介というのも貴重だな、などと思いながら、思いも寄らぬ切っ掛けでこんなに近付いて話すことになるとは思わず、鼓動が逸ってくるのを胸元のシャツを掴んでぎゅうと抑え込んだ。
「あぁ、母さんはちょっと用事で出掛けている。父さんは仕事でいつも遅いんだ」
ガーゼや包帯を用意し、消毒液で傷口を消毒しながら答える。
「っ、…他に家族は?」
沁みるのに顔を歪めながら、余りヒトサマの家の家族には会いたくないな、と思って尋ねた。
「いないよ。祖父母はとうに他界しているし、きょうだいもいない。三人家族だ」
睫毛長いな、とか、肌もシミ一つ無くて綺麗だな、とか、まじまじと観察してしまう。
節くれ立った大きな手は啓介と違って傷一つ無く、グレている自分と違って優等生の涼介は喧嘩とかしたこと無いんだろうな、と思った。
「へー、センパイ一人っ子なんだ…弟とか妹とかいると思ってた」
手当ての仕方も手慣れているので、弟妹相手にやり慣れているんじゃないかと思ったので、一人っ子は意外だった。
「そうか? オレは遅くに出来た子だから、まぁ確かに上でも下でも、きょうだいがいれば楽しかったかも知れないな…両親も一人っ子できょうだいがいないから、いとこというのもいないし…高橋くんは女の子の従妹がいるんだろう? 史浩が言ってた」
「あーうん。喧嘩ばっかしてて、っつっても口喧嘩とかだけど、よく史浩に仲裁に入られてた。オレも一人っ子だから、まぁ史浩とか緒美とかガキの頃一緒に遊んだりはしてたけどさ、一緒に暮らしてる訳じゃねーし、やっぱきょうだいっつーの欲しかったな。きょうだいのいる生活ってピンと来ないけど、いたら今の人生もちっとは違ったんかなって思う」
涼介の手当てを受けながら、彫刻みたいに整った顔立ちやシャツの隙間から見える生肌に何故かぞくりとして、何となく目のやり場に困ってしまった啓介は、リビングを見渡した。
啓介の家の方が立派で豪奢なのだが、調度品など全てがきちんとしたものばかりで、此処でセンパイが暮らしてるのか、と日常の涼介をもっと見てみたいな、などと思ってしまい、最近の自分はどうかしてる、と変化続きに戸惑ってしまう。
「そうだな。きょうだいのいる奴の話を聞いていると、きょうだい喧嘩っていうのをしたり、すぐ仲直りして一緒に遊んだり、でもまたすぐに喧嘩になったり、って忙しないみたいだけど…」
くるくると腕に包帯を巻きながら、涼介は啓介に同調した。
「あー…オレもちょくちょく聞くけどさ、話聞く相手が悪いのかどこもそうなのか分かんねーけど、出来の良し悪しを比べられて嫌な思いする、とかそーゆーのが多いかな」
チームの溜まり場で、他の連中がグレた切っ掛けに上げられるのが、殆どがそれだったのだ。
もし自分にきょうだいがいたら、ソイツが優秀だったら、きっとチームの奴らと同じ理由でグレただろうことが容易に知れる。
尤も、今のグレた理由も、大差ないのだが。
「あぁ、そうらしいな。それはきょうだいの問題じゃなく、親の問題だと思うよ。百人の人間がいれば百通りの個性があるのに、同じ枠に填めようとして、子供の個性を見出し伸ばそうとしないんだろう。良いところを見ようとしないで、悪いところばかり叱って子供の芽を摘み取るのは、愚かだと思うよ」
啓介は呆気にとられたように、目を見開いた。
「…何か優等生のセンパイの言葉とは思えねーな」
「? 何が? おかしなこと言ったか?」
顔に出来た擦り傷に絆創膏を貼ったりガーゼを当てたりしながら、至極真面目な顔で、薄茶の瞳を見つめる。
闇色の瞳に見つめられて、啓介はドキリとして、思わず視線を逸らした。
「や、正論だよな。オレもきょうだいとかいたら、今以上に煩く言われて嫌な思いしたんだろーなって思った。オレ出来悪いしさ、デケェ病院の院長の子供なのに、医者になれる頭ねーしさ、オヤはあんま煩くねーけどじーさんがメチャ厳しくてさ、グレちまったらオヤにはもう諦められてるし、まぁ出来損ないでも意地はあっから、必死こいて受験ベンキョーしてT高入ってやったけど、この先どうすんのか、どうしたいのか、全然分かんねーんだ。やりたいこととか見つけられねーし、オヤの跡継ぐことも出来ねーし、オレ何の為に生きてんだろーなって…」
って何でこんなことベラベラ喋ってんだオレ、と啓介はハッと我に返って、口に手を当てる。
涼介は手当てしながら黙って聞いていたが、今まで見たことの無いような、柔らかな微笑みで啓介を見遣った。
トクン、と啓介は鼓動が跳ねるのを感じる。
「高橋くんは真面目なんだな…」
「は? オレのドコが? 真面目っつーのは、センパイとか、史浩みてーのを言うだろ?」
一体何を言ってるんだこのひとは、と啓介は眉を寄せる。
「オレはそこはかとなく不真面目だよ…じゃあ言葉を変えようか。高橋くんは優しいんだ。親御さんの跡を継いで医者になれない自分をもどかしく思っているんだろう? 出来るなら医者になって親御さんの跡を継げるようになりたいって思ってるんだろう? でもどうしたらそうなれるか、やり方が分からなくて、苛々してしまうんだ」
啓介はポカンとして、涼介の言葉を聞いていた。
そんな風に言ってくれたヤツ、今までいなかった―――。
「勉強の仕方には、個人に合わせたコツがあるんだよ。全員が皆同じやり方をしても、同じように身につくとは限らない。それを見極めることが出来れば、キミも志望大学に合格することだって出来るさ。勿論、頑張り次第で医者にだってなれる」
「オレが…医者に…?」
にわかには信じられない、と言った風に、啓介は唖然としている。
手当てを終えた涼介は救急箱を片付け、ダイニングでグラスに氷を入れ、コーヒーメーカーで作っておいたコーヒーを注ぎ、ストローを差してコースターに載せて、ガムシロップと共に啓介に出した。
涼介はホットにして、斜め向かいのソファに腰を下ろす。
ガムシロップを垂らしながら、啓介はチラと涼介を見遣る。
思いも掛けずこうして話す切っ掛けが出来て、涼介に対する認識がだいぶ変わった。
ただの杓子定規な優等生じゃなくて、芯がしっかりしている。
相手のことをきちんと思いやって話が出来る。
こんな不良の自分の話もきちんと聞いてくれて、真面目に答えてくれている。
一見すればやっかみを買いそうなタイプなのに、人気があるというのは、こういったところから来るのだと分かった。
だが、自分が涼介に抱いている感情は、彼の周りにいるその他大勢の連中と同じものだとは、思えない。
(女だったら…多分惚れてたんだろうけど…センパイは男だしな…)
涼介と一緒にいる空間は、何故か不思議な居心地の良さがある。
気心の知れた史浩といる時とも、唯一の友人である久木といる時とも、違う感覚。
(そうか…もしかして…)
きょうだいのいない啓介の憧れ。
小さい頃からずっと思っていた。
純粋に憧れ慕うことの出来る兄が欲しかった、と―――。
史浩をその対象に思おうとしたこともあったが、幼馴染みのポジションより上にも下にも行くことは無かった。
涼介について知っていることはまだ少ないけれど、もっと知りたい、もっと近付きたい、そう思う。
優等生タイプは嫌ってきたけれど、多分オレは、前崎センパイみたいになりたかったんだ―――。
壁の時計の秒針の音が、やけに響く。
「センパイは…何で弓道やってんの?」
何か会話の切っ掛けを、と探っていたのだが、咄嗟に口に出たのは、至極どうでもいいことだった。
我ながら情けない、と親しくなりたい相手に対する踏み込み方が分からなくて、加減の具合を図りかねる。
涼介もいきなり何だ、と虚を突かれたような顔をしていた。
だが啓介の意図を汲み取って、ふっと微笑んだ。
「そうだな…大抵のスポーツは体育の授業でやるけど、弓道は無いからな…それで興味を惹かれて、かな」
「中学ん時は?」
「サッカー部だよ。だから高校でもサッカー部に入ろうかという選択肢も考えたんだけど、部活見学をしてた時に、武道場で見た弓道部が魅力的に映って…武道ならでは弓道ならではの礼儀作法や所作が素晴らしくて、身に付けたいなと思ったんだ」
「あー、だからセンパイって動きがいちいちシュッてしてんだ。翠巒祭ん時の模範演技、すげーカッコ良かったし」
だが高校から始めてそれで部長まで務めているんだから、元生徒会長だし、この人に(服装のセンスはともかく)出来ないことってあるんだろうか、と思ってしまう。
「有り難う。高橋くんは天文部、ちゃんと出てるのか?」
ちょっと意地悪そうに、涼介に尋ねられ、啓介は目を泳がせる。
「あーいや…ユーレイ部員なってる;」
「はは。高橋くんの運動神経、活用しないのは勿体ないと思うけどな。体育の授業でそれぞれの運動部の連中より活躍してる、って噂になってるよ」
「や、運動部とか全然キョーミねぇから。単車転がしてる方が自由で楽しいし。エンジン駆けて走り出せば、風が教えてくれるんだよ。苛々した気持ちとか靄靄した濁った感情を吹き飛ばしてくれる。風と走れば、束の間かも知んねーけど、確かな手応えがこの手にあるんだ」
開かれた手のひらを、ぎゅっと握り込む。
ちゅーとストローを啜りながら、バイクの話になると目が輝く啓介に、自分と似た匂いを涼介は感じた。
その気持ち、よく分かる―――。
「―――高橋くんはバイクが好きなんだな」
「そりゃまぁ…てか、その〝高橋くん〟ってのキモチワリーから、啓介でいーよ。〝くん〟も要らねー」
「そうか、じゃあ…啓介」
自分で言っておきながら、いざそう呼ばれると、ドキンとした。
チームの幹部連中にだって名前で呼び捨てにされているのに、この違いは何なんだ?
「っ、センパイは、大学はど―――」
動揺を誤魔化すように話題を変えようとしたら、玄関がガチャリと開いた。
「ただいま。涼介、どなたかいらしてるの?」
リビングに入ってきたのは、年配の女性だった。
「お帰り、母さん。さっきN町のコンビニ跡地でサラリーマンが不良に襲われてて、それを助けて怪我をした彼の手当てをしていたんだ」
涼介は立ち上がり、母を出迎える。
「まぁ…さっきご近所の方が話しているのを聞いたけれど…この辺も物騒ね。怪我は大丈夫なのかしら?」
「擦り傷は多いけど、大したことないと思うよ。襲われていた人も、Nクリニックに行ったのを見届けたし。彼は高崎の高橋記念病院の院長先生の息子さんなんだ。高校の後輩だよ」
「高橋啓介…デス。ども、お邪魔シテマス」
紹介されて啓介も慌てて立ち上がって、ぺこ、と軽く頭を下げた。
「まああ…! 高橋院長先生の…! 院長先生のお蔭で、わたくしどもの会社は成り立っているんですのよ。主人に代わって御礼を申し上げますわ」
夫人は興奮気味にまくし立て、どうぞお座りくださいな、と言われ、啓介は腰を下ろし、涼介も座り直した。
「あーいやその、オレはなんもしてないすから…センパイのウチと取り引きがあるの知ったのも最近だし…オヤジに言っときます」
顔を合わせたらだけど、と久しく見ていない父親の顔を思い浮かべる。
学会だ何だと忙しい父は、殆ど家にいない故に、若い頃の顔しか思い浮かばなかったのだが。
涼介の母親は、啓介の母親より随分年が上のように見えた。
遅くに出来た子だってさっき言ってたな、と思い出し、だが余り似てないんだな、と夫人を見て思う。
男の子は母親に似る、と聞いたことがあるが、実際啓介も母親似だし、涼介は父親似なんだろうな、と考えた。
(そーいやセンパイって、オヤジの若い頃にちっと似てるかも…)
まさかオレはセンパイに父性を見出だしてるんだろうか、と思ってしまい、愛情に飢えた小さい子供じゃあるまいし、と小さく咳払いした。
「あーセンパイ、あんま長居しちゃ悪ィし、オレ帰るよ。手当てしてくれてサンキュな」
所謂夕飯時にヒトサマの家で寛ぐのは落ち着かなくて、早く帰ろう、とアイスコーヒーのストローを啜って飲み干し、立ち上がる。
「まぁ、折角いらしてくださったんですから、お夕飯召し上がっていってくださいな。大したものはありませんけれど」
「あーいや、ウチも家政婦サンがオレのメシ用意してくれてるんで」
家で夕飯が用意されているのは事実だが帰るというのは方便で、チームの溜まり場に行くつもりなのを、適当に誤魔化した。
「啓介、バイクを運転して帰れるのか? 怪我も心配だし、オレのクルマで送っていこうか。バイクはまた後で取りにくればいいし」
後を着いてきた涼介は、ズボンのポケットに入れていたFCの鍵を取り出す。
オレンジ色の物体が揺れているのが見えて、気紛れに渡した誕生日プレゼントをちゃんと使ってくれているんだ、と思うと心がくすぐったくなる。
「や、だいじょぶだよ。大した怪我じゃねーし。じゃ、お邪魔シマシター」
「またいつでもいらしてくださいね。ウチの涼介を宜しくお願いします」
恭しく頭を下げる夫人から逃げるように、啓介は家の外に出る。
もう少し涼介と一緒にいたかったけれど、時間が悪かった。
でも、今日だけで色んな面を見れた気がする。
話してみると結構表情変わるんだ、とか、人間味のある面もちゃんとあったんだ、とか、近寄りがたい女神様が、グンと近付いたような。
怪我は大したことない筈なのに、涼介に触れられた箇所が、熱い―――。
単車を飛ばしながら、熱に浮かされたように、暑い夏が近付いてきているのを感じた。
「涼介、高橋院長先生の息子さんとは、親しくさせていただいているの?」
父の帰りが遅いので、母と二人で夕食を摂っていると、そう訊いてきた。
「え? いや、そんなに親しいって程じゃ…彼が高校に入ってまだ2ヶ月だし、部活も違うからそう話すことは無かったんだけど、今日はたまたまだよ」
そのたまたまの偶然も嬉しかったのだが、母の問い掛けに、意味を理解して、心の中で小さく息を吐く。
そう、嬉しかった。
同じ不良をしていても、一般人が襲われていれば助けるような、仁義のあるタイプだと分かって、印象を改めた。
史浩から、啓介の所属するチームはクスリやウリなどは御法度の筋の通った連中が集まっていると聞いて、所謂喧嘩も啓介自身は売られたものを買うだけで、暴走行為で法を犯しているくらいだ、ということは、自分も似たようなことをこの先やる予定だし、不良にもピンキリあるんだな、と認識を改め、啓介に対する苦手意識は無くなった。
いや、最初軽蔑していたことを詫びたい。
素行は良くないかも知れないが、学校の連中に手を上げたりはしていないのだから、教師受けが良くないのも学校側には改めて欲しいものだと思う。
あの色素の薄い茶髪も地毛だと史浩が言っていた。
見た目だけで決め付けてしまう、それがどれだけ愚かなことか、今日啓介と話してみて、つくづく自分を恥じたのだった。
「涼介が女の子だったら、高橋院長先生のご子息のところへ嫁がせたかった、ってお父さんともいつも言っていたのよ」
その話も耳タコだった。
長い不妊治療の末ようやく授かった子を高橋記念病院で出産して、その後取引契約がなされ、会社は大きくなった。
高橋記念病院と院長先生には足を向けて寝られない、今も変わらず大きなお得意様でいてくれるお蔭で会社の経営も安泰、その繁栄を末永いものにする為に、子供が女の子だったら高橋家に嫁がせたい、何度も聞かされた話だ。
「母さんまたその話…オレは男なんだから、無理を言うなよ」
「高橋院長先生のお子さんが女の子だったら良かったわね。アナタが婿入りすれば良いんだから…」
「そんなこと言ったって、無理なものは無理なんだから、やめなよ、その話は」
「だって、アナタは医者になるんですもの…お父さんの跡を継いで医学者として研究に手を広げるのも良いけれど、アナタは優秀ですもの、立派なお医者さんになれるわよ。勤務医になるなら、高橋記念病院に雇ってもらうのよ」
「分かってるよ…」
何度も言い聞かされた話。
大きいと言っても県外に出れば一般的には知られていないような、中小企業。
会社経営している家の子供というのは、生まれた時から将来が定められているものなのか。
繰り返し言い聞かせられて、まるで洗脳だ。
大切に育ててきてくれて、クルマが欲しい、サーキットで走りたい、という我が儘も成績優秀を通すことで許してくれて、感謝はしているけれど、会社第一の考え方には、ウンザリする。
互いに男で良かった。
もし自分が女だったら、啓介のことを嫌いになっていたかも知れない。
啓介本人に罪はなくても、絶対に好きにはなれなかっただろう。
男で良かったと心底思う。
政略結婚なんて、時代錯誤だ。
だが、いつか誰かと結婚はする―――その点は未だにピンと来なくて、好きな女もいないし、告白してくる女と付き合いたいと思ったこともない。
啓介も同じだろうか。
大きな病院の一人息子で、程度は違えど、涼介と啓介は同じような境遇だ。
先程啓介に言った言葉の数々も、気持ちが分かるから、つい同調してしまった。
もっと深く関わり合えば、互いの境遇に共感し合って、親しくなれるだろうか―――。
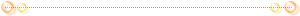
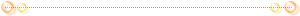
約束の日の午前10時、涼介は愛車FCを駆って、高崎の高橋邸を訪れた。
此処から程近いT高校に通って3年目だし、親友の史浩のところにもちょくちょく行っているから、この屋敷は見慣れていたが、まさかこうしてお邪魔することになるとは。
「センパイはえーな、流石優等生。15分前行動ってか?」
腕時計が示す時間は午前9時45分。
立派な門構えのチャイムを鳴らそうとしたら、今通ってきた路地の先から、啓介がコンビニ袋を提げて歩いてきた。
暦の上では秋でも残暑の厳しい夏休み、午前中でも容赦ない陽射しの中、ニカッと笑う啓介は太陽よりも輝いて見えた。
タラタラ歩く白ジャージの上下姿は、いかにもなヤンキーだな、と思ったことは黙っておく。
「コンビニでレジにいたらセンパイのクルマ見えたからさ、早く戻らなきゃ、って思ってたら煙草買いそびれたぜ」
「あのな…高校生がコンビニで堂々と煙草を買おうとするな」
認識を改めたとはいえ、大病院の御曹司がこれでは先が思いやられるな、と息を吐く。
「苛々すっとどーしても吸いたくなっちまうんだよなー」
門の前で暗証番号を押して解錠しながら、啓介は口を尖らせた。
「医者を目指すなら、煙草はやめた方がいい。それに成長期の子供には百害あって一利無しだ」
「あー…分かってっけど、口サミシーっつーか…」
自動で門が開いていき、啓介が入っていくのを涼介は後を着いていく。
広々とした敷地の洋風庭園は、地元ローカルテレビでも紹介されていたな、と眺めながら玄関までの長い道のりを歩いた。
この手入れに手間がかかりそうな立派な庭園だけ見ても啓介が大きな病院の御曹司なのだとまざまざと感じる。
「口寂しい理由で煙草を吸うのは、赤ん坊が母乳を欲しがるのと同じだよ。つまり、今でも母親のおっぱいが恋しい訳だな」
「ちっげぇよ! そんなんなんもねぇし! ~~ただ苛々するとか、どうでもいいような理由なんてモンなんかねぇんだ。別に美味くて吸ってる訳じゃねぇし…」
ポケットに手を突っ込んで歩いていた啓介は、背後の涼介を振り返って声を上げた。
結構からかうようなこと言うよな、と涼介の色んな面が見れて、嬉しいけれど、面白くない。
「背伸びしたいお年頃なのは分かるけど、美味くないと思うならやめた方がいい。ところで…クルマは前に停めておいて大丈夫か?」
振り返って門の傍に停めた愛車を見遣り、啓介に尋ねる。
前の通りの行き交う車の邪魔にはならないだろうが、長時間の路駐は宜しくないのでは、と思う。
「あーうん。あそこならだいじょぶだよ」
ポケットから鍵を取り出し、玄関のドアを開けると、啓介は靴を脱いでズカズカと上がっていく。
「―――お邪魔します」
思うところあるように啓介の背を見つめながら、涼介も靴を脱いで上がり、脱ぎ散らかした啓介の靴とは対照的に、きちんと揃えて立ち尽くす。
外観も立派な洋風建築だが、中も豪奢で、ジャージ姿の啓介が浮いて見えるかと思ったが、意外と馴染んでいたので、それは啓介の存在感から来るのだろう。
見る者を惹き付ける、器の広さ―――そして滲み出る育ちの良さ。
「莱子サン、客連れてきたからさ、昼メシは二人分用意して」
リビングかダイニングか、啓介が中にいる誰かと話しているのを、廊下で遠巻きに待った。
「かしこまりました。朝食が遅うございましたから、13時頃で宜しいですか? 」
「うん」
「お客様に何かお出ししましょうか?」
「あーじゃあ後で何か飲みモン持ってきて。部屋にいるから」
「かしこまりました」
口調からして、家政婦なのだろう。
屋敷内の空気からして、他には誰もいなそうだ。
家族がいたら挨拶を、と思っていたが、取り敢えず手土産を渡すか、と啓介の元に向かう。
「啓介、これ…お家の方に召し上がって頂いてくれ」
荷物とは別に持ってきた紙袋を啓介に渡し、チラと先程啓介が開けていたドアを見遣った。
「え、何、わざわざいーのに」
「そういう訳にも行かない。冷菓だから、冷やしておいて」
「サンキュ。莱子サーン、コレ貰ったから、冷蔵庫に入れといてー」
「はい。まぁ、前橋で有名なお店の冷菓ですね」
ひょこ、と家政婦が廊下に顔を覗かせたので、涼介は会釈した。
「こんにちは、前崎涼介と言います。お邪魔します」
優等生宜しく、爽やかに挨拶する。
「まぁまぁ、啓介ぼっちゃまがお客様をお連れするのは初めてで御座いますね。ようこそおいでくださいました。家政婦の藍尾で御座います。ごゆっくりしていかれてくださいませ」
恭しく頭を下げる家政婦は、パッと見で長年勤めている、と見受けられる。
どう見たって啓介と涼介が親しい間柄には見えないだろうに、涼介を見ても、変に表情を変えたりはしなかった。
プロの家政婦とはそういうものなのだろう。
「じゃあ上行こーぜ、センパイ」
豪奢な螺旋階段を上がっていくと、途中で階段が二手に分かれ、啓介の行く先は、自分しか使っていないフロアだ、と階段を上りながら説明した。
「オレの部屋コッチ。隣は空き部屋で使ってねーんだ」
木製のドアが開けられ、室内を見て涼介は絶句する。
広々としているのに、足の踏み場もない程に散らかって、空気も澱んでいそうだ。
「……啓介、この部屋の何処で勉強するって…?」
「あー…やっぱ無理がある?」
ばつが悪そうに、啓介は頬を掻く。
机の周りも上も物が積み上げられ、椅子には脱ぎ捨てられた衣服がだらしなく何着も無造作に掛けられており、とても勉強する気があるようには思えなかった。
「…せめて机の周りくらい片付けておいたらどうなんだ? こんな状態で、よくオレを呼ぶ気になったものだな」
「あーいや、ゆ~べ片付けとくつもりだったんだけど、忘れて寝ちまって」
タハハ、と啓介は悪びれずに笑う。
この大雑把さは、O型かB型のどっちかだな、と息を吐いた。
「片付けている間に昼になりそうだな…家政婦さんに掃除してもらっていないのか?」
涼介は潔癖症という訳でも無いが、この部屋に入るのは少々躊躇われる。
「ドコに何があるか分かんなくなるじゃん。莱子サンにはオレの部屋には入らんでって言ってあるし」
部屋が散らかっている者は皆、口を揃えてそう言うんだよな、と呆れる以外に無い。
ベッドの上は一見綺麗だが、シーツは定期的に換えているのか、彼方此方に脱ぎ捨てられている服はちゃんと洗濯しているのか、思わず引いてしまう。
「しょーがねー、隣の部屋使うか。誰も使ってねーんだけど、机とか椅子とかあっからさ」
啓介は自分の部屋から勉強道具を持ってきて、椅子もぱぱぱと掛けられた衣服を床に落として持ってきて、隣の部屋に向かった。
その横着な仕草を見ているだけで、それが部屋の散らかる原因だ、と言ってやりたい。
隣の部屋は硝子張りのドアで室内が見え、啓介に着いていって中に入ると、立派な机に椅子、中身は空の大きな本棚、キングサイズのベッドと、広々とした部屋に家具など全て揃っている。
「客間という感じじゃないけど…」
「オヤがさ、結婚してこのウチ建てる時、子供は二人は欲しいからって子供部屋に二部屋用意したんだってよ。でもオレ一人っ子だからさ、一部屋空いちまってるって訳」
壁に備え付けられたエアコンのリモコンをピッとスイッチを入れ、ウィンとフィンが廻る。
季節の始めに使うエアコンならではの独特の匂いは何処の家でも同じだな、と思いながら、普段使われていない高価そうなエアコンは、すぐに部屋を涼しくしてくれた。
部屋には埃も溜まっていないし、家政婦が定期的に掃除しているのだと分かる。
「あぁ、成程…じゃ、始めようか」
実力テストの傾向と対策を踏まえ、いざ教えてみると、啓介はそれ程頭が悪いという訳でもなく、丁寧に教えれば、飲み込みも早かった。
これなら、もう少し頑張れば、三年になる頃には群大医学部も合格ラインに行けるだろうと思う。
夏休みの宿題からも出題されるので、終わっている部分の説明やまだ手つかずの部分を教えたりしながら、啓介の覚えやすい勉強法を判断し、そのやり方をも教えていく。
啓介は乾いたスポンジの如く、みるみる吸収して、勉強は効率よく進んでいった。
昼少し前、家政婦の藍尾が冷たい飲み物を持ってきてくれたので、小休憩する。
「やー、センパイ教え方うまいな! すっげー分かりやすいし、久木よか言ってること理解できるわ」
出された飲み物がカルピスの牛乳割りなのは、やはりもう少し身長が欲しいだろう啓介の日常的な飲み物なんだろうか、と思うと何だかおかしい。
成長期だし、一ヶ月でだってグンと伸びる年頃だし、入学式の頃よりは何cmか伸びているな、とは思っていた。
「久木? あぁ、一年の学年トップか。同じクラスだったか…? 確か久木は4組じゃ…」
「クラスはちげーけど、中学ん頃からの知り合いでさ」
グラスの氷をカランと音を立てさせながら、ストローをちゅーと啜る姿は、子供のようで可愛いなと思ったことも黙っておく。
「同じ中学だったのか?」
「い~や、全然。中学ん頃は顔見知り程度で、殆ど話したことなかったし」
それで学年トップとどういう繋がりがあるのか、疑問に思う。
「ハハッ、何で学年トップの久木とオレなんかが繋がりあんのか、やっぱ不思議?」
「や、まぁ、確かに…」
顔に出てしまったかと思ったが、啓介はそう考えてしまうのが普通だと分かっていて、試すような言い方をしているんだ、と気付く。
ただ単純なだけではない狡猾さを感じながらも、嫌味さが無いのは、啓介の人柄なのだろう。
「コレ勝手にバラしちゃマズイからオフレコだけど、久木は中学ん時ヤンチャしてたんだよ。オレの入ってるチームの系列チームにいてさ、けっこー笑えねー武勇伝あるんだぜ? 久木のヤツ」
「へ…え…」
意外だった。
が、久木とは話したことは無いが、雰囲気のある異質な空気をまとっていて、修羅場をくぐってきていそうな他とは違った強靱な瞳をしているのが引っ掛かっていたので、納得した。
「オレと違ってヤンチャは中学で卒業したとかって言ってっけど、未だに無免で単車転がしてんだぜ? ガッコじゃ優等生ぶってるけどさ」
アイツ早生まれだからまだ免許取れねーんだよ、とカルピスをちゅーと啜る。
「はは…そうなのか」
中と外では自分を偽り取り繕って、久木に自分と似た匂いを感じていたのはそれか、と涼介は内心クスリと笑う。
「久木も確か群大医学部志望だったな。彼も医者になるのなら、強力なライバルだな」
ストローを啜ってるセンパイは何かエロい、と思ってしまって、啓介は誤魔化すようにずずずと残りを飲み干した。
オレのカルピスも飲んで、とかしょーもない下ネタが浮かんでしまうアホさに、何でこの部屋にはベッドまであるんだ、とチラチラ目を遣って慌てて逸らす。
「や、久木は医学部だけど保健学科の方の志望」
「え…そうなのか? 確か彼の親御さんは群大の教授だろう? てっきり医者になるものだと…」
久木教授は分子細胞生物学の分野では有名で、涼介は著書も持っている。
いずれ先輩になる群大生の知り合いが久木教授の研究室に入っていて、教授の次男がT高校に入学した、という話をその人伝いに聞いたことがあったので、何となく久木も気に掛けていたのだが、まさか啓介と親しい間柄だったとは、思わなかった。
やはり三年と一年だと、細かい情報までは知り得ないんだな、とカルピスを啜る。
啓介が淫らな想いで見ていることには、気が付きもせずに。
「あーそうだってな。久木の年の離れたアニキも医者らしーんだけどさ、跡継ぎもういるからって、医者じゃなくて、何だっけ、臨床検査技師? になりたいんだってよ」
「へぇ…ヴィジョンがしっかりしているんだな。一年のうちからそこまで決めているなんて」
成程、ヤンチャの件だけでなく境遇も似ているから親しくなったのか、と納得した。
3組と4組なら体育の授業も一緒になるし、同じクラスでなくとも必然的に交流は多いのだろう。
「どーせオレは目の前にいっぱいいっぱいでソコまで考えらんねーよ…センパイみてーに何科志望とか全然考えてねーし…」
オヤジは小児科だけど、オレは小児科ってガラじゃねーし何科が向いてんだかピンとこねぇ、と口を尖らせる。
「はは。啓介はまだ一年だし、医学部で六年間学んで、研修医として二年間学んで、それでやっと決めるという人も少なくないと聞いている。今から一つに絞って視野を狭めるよりは、色んな経験が出来るから気にすることはないよ」
「ふーん…そっか、それでいいんか…」
硝子張りのドアがノックされ、家政婦の藍尾が廊下に控えていた。
「啓介ぼっちゃま、お食事の用意が調いました」
「あー、腹減ったな、メシ食ってこようぜ、センパイ」
腹をさすりながら啓介は立ち上がって、うんと伸びをして階下に降りていく。
ダイニングに用意された食事は、昼だというのにかなり手が込んでいて、たった二人分なのに立派で、涼介は申し訳なく思った。
「有り難う御座います、ご馳走になります」
家政婦に礼を述べ、向かい合わせで食卓に着く。
啓介は黙ったままナイフとフォークを手にし、ぱくぱくと食べ始めた。
「―――いただきます」
思うところあるようにチラと向かいの啓介を見遣って、手を合わせてナイフとフォークを手に取る。
藍尾は恭しく頭を下げると、ダイニングから下がった。
「莱子サンのメシ美味いだろ」
ニカッと笑う啓介に、思ったことを言うべきか、でしゃばりすぎだろうか、考えながら行儀よく食べていく。
「…あぁ、美味しいな」
啓介のナイフとフォークの使い方は、慣れていてきちんとしている。
マナーとして教えられているのなら、それがちゃんと身に付いているのなら、言うべきこともマナーではないのか。
育ちの良さは端々に感じられるのに、ただ悪ぶっているからではないと思う。
やはりお節介でも注意するべきか。
「…啓介、お節介は重々承知だが、言ってもいいか?」
「? 何?」
「外から帰ってきた時、〝ただいま〟と言わずに家に上がっただろう? 今も、食事の前に手を合わせて〝いただきます〟を言わずに食べ始めたな。どちらも大事なマナーだ。何故言わない?」
「へっ…」
何を言われたのか、分からないといった風に啓介はきょとんとしている。
「だってオレいつもメシは一人だし…家も普段誰もいないし、誰も聞いてねーじゃん」
「そういう問題じゃない。誰もいなくても、家政婦さんはいるんだろう? 泥棒じゃないんだから、帰ってきた時には〝ただいま〟を言う、出掛ける時には〝行ってきます〟と言う。例え誰もいなくても、自分が聞いている。食事の時も、食べる前には手を合わせて〝いただきます〟を言う、食べ終わったらまた手を合わせて〝ご馳走様でした〟と言う、当たり前のマナーだぞ」
啓介はきまりが悪そうに、口を尖らせている。
「第一、〝いただきます〟と〝ご馳走様〟を言わないのは、作ってくれた人に失礼だ。自分の血や肉になり命をくれる動植物にも失礼だ。たった一言言うだけなんだから、面倒なことじゃない筈だろう?」
「あー…うー…わぁったよ」
ぱくぱくと食べ終わると、ナイフとフォークを揃えて置いて、目を泳がせながら、手を合わせた。
「……ゴチソウサマデシタ」
涼介も食べ終わり、ナフキンで口を押さえ、手を合わせる。
「ご馳走様でした」
空いた食器はそのままに、啓介は立ち上がり、キョロキョロ見渡した。
「莱子サーン」
少しして、藍尾がダイニングに姿を見せる。
「何で御座いましょう、啓介ぼっちゃま」
「あの、さ。メシ美味かった。ゴチソーサン。いつもサンキュな」
照れ臭そうにぶっきらぼうに、啓介は言い放った。
藍尾は驚いたような顔を見せ、すぐに綻ばせた。
心なしか、目尻に光るものが滲んでいるのを、涼介は気付く。
恐らく先程の会話も聞いていただろうが、触れるのは無粋というものだろう。
「いえいえ、こちらこそ有り難う御座います。お勉強はまだ続きますの?」
「あーうん。夏休み終わったらすぐ実力テストあってさ。ちっと頑張ってみようって、センパイに教わってんの」
「ご馳走様でした。とても美味しかったです」
涼介は悠然と微笑み、礼を述べた。
「恐れ入ります。ではまた後程、お飲み物とお菓子をお持ちいたしますね」
「ヨロシク~」
二階に戻って、勉強を再開する前に、啓介が何か言いたそうな顔をしているのに気付いた。
「どうした?」
「や、その…オレのこと注意してくれてサンキュな。ガキの頃はちゃんと言ってたのに、いつの間にか言わなくなって、それが当たり前んなって…でも、ちゃんと言ったら、何つーか、気持ち良かった。今度から気を付ける」
悪ぶっていても、啓介は根は素直なのだ。
赤の他人の涼介が注意するようなことではないのに、反発することもなく、素直に聞き入れている。
間違ったこと・曲がったことなら反発したかも知れないが、それが正しいと分かっていたのだ。
そんな純粋さが、愛おしく感じる。
(愛おしくって…オレは一体何を…)
「オレさ、分かったんだよ。一人っ子だからきょうだい欲しいってガキの頃思ってたけど、センパイみてーなアニキいたら良かったなって。この家広いのにオレいつも一人でつまんねーからさ、グレちまってオヤにも迷惑かけてっけど、オヤにはもう諦められてるし、でもセンパイみてーにオレのこと注意してくれるアニキいたら、ちったぁマジメになれっかなって」
啓介の言葉で涼介も気付いた。
ずっと啓介に対して感じていたこの想いは何なのか分からなかった。
弟のように思って、こんな弟がいたら楽しいかも知れないと思っていたのだ、と。
「そうだな…オレも同じかも知れない。ずっと弟か妹がいたら楽しいだろうなって思っていたけど、啓介みたいな弟がいたら面白かったな。あれこれ世話を焼いたりするのも、楽しそうだ」
穏やかな空気が流れ、何となく良い雰囲気なのだが。
(っと待て! アニキだったらとか弟だったらとか、そんなこと言ってたら〝センパイが好きだ〟とか言いにくいじゃん! オレは兄弟愛みてーな意味でセンパイを好きなんじゃねーんだよ! コレじゃ告れねーじゃん!)
折角良い雰囲気なのに、家に二人きりでいいチャンスなのに、今この場で告ったら、KY以外の何物でもない。
久木は脈アリだと言っていたが、この流れで「好きだ」とか言っても、絶対受け入れられはしないと分かる。
というより、自分から告る、という経験の無い啓介は、どんな雰囲気・どんなシチュエーションに持って行ってどう言えばいいのか、言った後どうすればいいのか、チェリーボーイのように分からないのだ。
(どうせなら告ったらヤリてぇし…)
男同士のウニャララなコトは、久木とツーリングに行った時に、ラーメン食って餃子一皿で教えてもらった(久木には安いと文句言われたけどすげー細かく教えてくれた)。
ゴムは普段から常備してるが、ローションが必要だと言うから、久木のお薦めを買って自室の枕元には置いてある(ツーリングに行って何してんだというツッコミはすんな!)。
最近またご無沙汰してるから(半月もシてなきゃご無沙汰だっつの)、下半身がはち切れそうだし、このままソコのベッドにセンパイを押し倒してしまいたいのを、ずっと我慢しているのだ。
「…? 啓介? どうしたんだ? 勉強再開するぞ」
悶々としている啓介を怪訝そうに涼介が覗き込む。
近ぇ! 顔が近ぇよ! オレかなり我慢の限界!
この部屋じゃ駄目だって、廊下から丸見えだし、シーツ汚したらモロバレだっつの!
えーとこーゆー時何て言うんだっけ?
シントーメッキャクスレバ…何だっけ?
「あー…ちっとトイレ行ってくる!」
脱兎のごとく逃げる啓介を、涼介は呆気にとられたように見送った。
~~そーれから~~
随分長いトイレだったのを、不審に思われただろうか。
オカズは当然センパイだった訳だけど、出すモノ出してスッキリはしたけど、別の意味でまだ悶々としちまってんの、どうしよう。
そーいやセンパイって、女も知らなそうなんだよな。
でもセンパイも十代の男なんだし、どんなひとりえっちしてんだろ、どんな顔してヤッてんだろ、なんてコトを思ったら、すげームラムラすんだけど。
勉強教えてくれてるセンパイの低くて深い声が、勝手に脳内で喘ぎ声に変換されちまうんだけど、コレ何のビョーキ?
ダメだ、数式全然頭に入ってこねー。
「…流石に疲れたか? 今日はここまでにしよう」
啓介が集中できていないのが分かって、涼介は参考書を閉じた。
「えっ、あ、……ワリ」
情けねー。
ケーベツされたらどーしよー。
「明日以降別の日に、一~二時間くらいなら、高校の図書館で勉強見るよ。定期戦の準備で登校するから、その日で良ければ」
「あ、うん」
締まらない終わり方で勉強会は強制終了して、涼介は帰って行ってしまった。
エアコンが効いたままの空き部屋で、誰にも使われたことのないキングサイズのベッドに大の字に寝転がる。
自分の部屋はリモコンが行方不明なので戻る気になれない(それでよくあの部屋で勉強しようと思ったなとかツッこまねーでくれ)。
「あー…オレよくガマン出来たよな…」
ぼ~っと真っ白な天
井を見つめる。
ゆっくりと、視線を机に移す。
さっきまで、あそこにセンパイがいた。
学年首席の家庭教師って贅沢だよな(久木にはヤマ当てしかしてもらってないのでカウントしない)。
勉強はキライだけど、センパイに教えてもらってどんどん分かるようになっていくのは、楽しかった。
こんな風に日常的に教えてもらえたらいいのにな、と思う。
そしたらツマンネー毎日も楽しくなるだろうな。
(や…ていうか…)
センパイに告って想いが通じたら、面白味のねーオレの人生もバラ色じゃねーの?
「てか…バラ色って…;」
相変わらずボキャブラリーが貧困だ。
でも、センパイといると、モノクロの世界が色付いて見えるんだよ。
ホントなら夕方まで一緒にいられる予定だったのに、ボンノーでいっぱいな馬鹿なオレのせいで、早く切り上げられちまった。
もっと一緒にいたい、ずっと一緒にいたい。
センパイの気を引く為っつー情けねー理由だけど、もちっと勉強頑張ってみよう。
恋愛すんのに相手との釣り合い考えるなんて下らねーって思ってたけど、どう考えても今のオレとセンパイじゃ、釣り合ってねー。
センパイの隣に立って恥ずかしくない男になりたい。
センパイに惚れられるような人間になりたい。
そう考えたら、取り敢えず散らかりまくってるあの部屋の片付けから頑張ってみるかな、と思って起き上がった。
「あーあ、このオレが夏休みにベンキョーする為にわざわざガッコ行ってるとか、天変地異じゃね…?」
一応制服を着て、自宅から目と鼻の先のT高校に向かう啓介は、勉強の為というより、センパイに会う為かも、とタラタラと歩く。
初夏の翠巒祭と秋の定期戦、それぞれの実行委員会に所属する者は、激務の為、それぞれの期間中は部活動にも参加せず、実行委員に専念する、と聞いた。
涼介は実行委員ではないらしいのだが、人手が足りない時に、手伝っているとのことだった。
手伝うくらいなら実行委員にちゃんと入ってた方が内申にいいんじゃねーの、と言ったら、他にやることがあるんだ、と意味ありげに答えた。
でも去年は生徒会長だったってことは弓道部の他に生徒会もやってたんだし、それでいて学年首席だし、複数のことを両立する器用さは羨ましく思う。
天文部の幽霊部員でしかない啓介には、えれぇこったな、と思う以外にない。
まぁ自分は運動神経を活かして、定期戦で活躍してやればいいや、と気を取り直す。
学校で会う涼介は、相変わらず一分の隙もない、完璧さを感じる。
校外で会う方が砕けている感じで好きかも、と思うが、どんな涼介でも、例えみっともない姿でも、好きだな、なんてこっ恥ずかしいことを思ってみたりする。
「なぁ、センパイってウチは前橋だろ? あそこM高の近くだろ? 何でわざわざ隣の市のT高にしたん?」
秋に行われる定期戦はM高校との対抗戦なので、ふと疑問に思って尋ねた。
「ん? 何でって?」
「だってM高とT高って偏差値同じくらいじゃん? 何でわざわざ遠い方受けたんだよ?」
まぁそのお蔭でセンパイに会えたから有り難いんだけど、と勉強の合間に訊いてみた。
「そうだな…二校を比べてみて、此方の方が授業のカリキュラムや行事が魅力的だったから、かな…近い遠いはあまり考えていないよ」
「へー。オレなんか、近いからギリギリまで寝てられるじゃんとか、すげーアホな理由でT高にしたからなぁ」
「はは、どんな理由であれ、合格できてテストもクリアできていれば、いいんじゃないか? 啓介は定期戦でも活躍するだろうし、崇高な理由なんて無くても、日々学んでいく中で、目標を見つければいいんだし」
取り敢えず呆れられなくて良かった、と安堵するが、最初の頃とはだいぶ自分に対する反応が変わってきている気がする。
最初は、その他大勢にと同じだったのが(てゆーか多分嫌われてたんじゃと思う)、トクベツになったような。
気のせいだろうか、そう思いたいだけだろうか。
いや、史浩が『最近涼介が何となく雰囲気が変わってきた気がする』と言っていたから、他の人間が見てもそう感じるなら、気のせいじゃないんだ。
センパイに影響を与えているかもなんて、そう思ったらぶわっとセンパイに対する気持ちが大きく膨らんできてしまって、「好きだ」と言ってしまいたい衝動に駆られる。
もし言ったら、どんな反応されんのかな。
脈アリだっつってた久木の言葉を信じても、確かまだ自覚はしてないだろうとか言ってたしなぁ。
ビックリされるかな。
や、ビックリされるだけならいい、拒絶されたらどうしよう。
あー、告るとか初めてなのに、ましてや相手は男だし、さっぱ分かんねー。
大体思ってること言わずに腹に溜め込んでるなんて、オレのガラじゃねーんだよな。
玉砕覚悟で(いや砕けたくないけど)、言っちまおうか。
今なら周りに他に誰もいない。
勉強しに図書館来てるヤツらも、近くにはいない。
「なぁ、センパイ…」
「ん? 何だ?」
「オレ、センパイのコト好きなんだけど」
案の定というか、センパイは目を見開いてた。
告ったこと、オレは後悔してねーから。