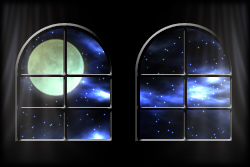
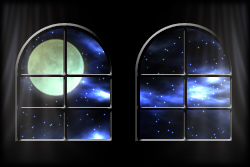
| 【出会いはいつも偶然と必然】 第九章 夜も更け、お開きにしたカカシとは、夜風に当たりながら、家路を歩いていた。 「全く、はザルだな。初めて呑んだとは思えないよ」 やや足元の定まらないカカシは、殊更ゆっくり歩いた。 そのカカシの腕に、ピッタリと絡みついて軽快に歩く。 「えへへ〜。楽しかった〜♪ また来ようね、カカシせんせぇvv」 陽気には、ご機嫌でカカシにしがみつく。 豊かな胸の柔らかさと温もりが、正気を保っているつもりのカカシの思考を麻痺させていく。 「わ〜〜星空キレ〜〜vv」 見上げると夜空は満天の星空。 真っ暗な夜道を、星星と月光が2人を照らしていた。 足元に落ちる影が重なり合っていて、感じる体温の熱さにカカシは己が昂ぶっていくのを感じた。 家の前まで来て、鍵を開けると、するりとは中に入って、風呂に湯を張りに向かった。 カカシはベストを脱いで、口布と額当てと手甲を外して居間のソファに沈み込んだ。 ふぅ、と大きく息を吐き、窓越しに夜空を見つめる。 思考もかなり怪しくなっていた。 「カカシせんせぇ〜! お風呂沸いたよ〜」 台所で弁当箱を洗い終わったが、カカシを呼びに来た。 「あぁ、有り難う。入ってくるよ」 真っ白なエプロン姿を直視できないカカシは、着替えを持って直ぐ様風呂場に向かった。 早風呂で上がってくると、はダイニングで本を読んでいた。 どうやら、酒酒屋で話していた、ゲンマから貰ったという料理の本のようだった。 鼻唄混じりに、は頁を捲る。 カカシは大分思考が覚束ないというのに、のこの酒の強さは何なんだ、と思う。 「、風呂空いたから入っておいで」 アルコール分を身体の中で中和させるのが早いんだろうな、と感じた。 「あ、ハ〜イ」 本を閉じると、は軽快な足取りで寝室に向かい、着替えを持って風呂場に向かった。 聞こえてくる水音に、カカシは鼓動が早くなる。 何事もなく済ませられるだろうか、と不安になる。 今でも脳裏に浮かぶ、温泉でのの理想的な滑らかなボディライン。 バスタオル越しでも、ピッタリと張り付いたそれは、豊かな膨らみとくびれたウエストラインを、容易に想像させた。 クラリと思考がおかしくなってきたので、勢いに任せ、酒瓶を取り出した。 「あ〜! カカシせんせぇ、またお酒呑んでる〜!」 暫くしてが風呂から上がってくると、カカシは大分ボトルを開けていた。 「もう呑みすぎだよ〜。呑みすぎは良くないって打ち止めにしたの、カカシせんせぇじゃな〜い」 プクゥ、とは頬を膨らませた。 「ん〜? ヘーキヘーキ。風呂上がりの水分補給だよ」 「湯冷ましとかじゃなきゃダメだよ〜。清涼飲料水とか〜」 もうダメ! とは取り上げて、酒瓶をしまい、グラスを洗った。 「もう寝ようよ、カカシせんせぇ。大分遅いよ。明日起きれるの?」 「大丈夫だよ。一晩くらい寝なくても平気だから」 大分思考の回らなくなっていたカカシは、に腕を引っ張られて、寝室に連れられて来ていた。 「早く寝よ? 少しでも睡眠取らなくっちゃ」 ちょこん、とベッドに腰掛け、カカシの腕を引っ張る。 「ん? 何でオレまで寝室に連れてくるの?」 「え、だって一緒に寝てくれるんでしょ?」 「ダメだって言ってるでしょ。人形貸して。チャクラ練り込んであげるから」 高鳴る鼓動を抑えつつ、枕元のカカシ人形を手に取り、カカシはチャクラを練り込んだ。 「え〜。私、賭けに勝ったのにぃ」 「引き分けでしょ。オレは酔ってないよ」 ハイ、と人形をの傍らに置いた。 「え〜〜〜足元ふらふらだったし〜、呂律回ってなかったよ〜」 ここで寝ようよ、とはカカシの腕を引っ張った。 「、ホントにキミは分かってないね。男は危険な生き物だって言っただろ? 特に酒の入った男なんて、何をするか分かんないんだよ。目茶苦茶にされてもいいの?」 の横に腰を下ろし、カカシはの肩に手を置いて言い聞かせた。 「目茶苦茶って?」 キョトン、と大きな闇色の純粋な瞳でカカシを見つめる。 その愛くるしい闇に吸い込まれそうで、カカシは益々己が昂ぶっていくのが分かった。 「オレがこういうことをしてもいいの?」 カカシはの両肩を掴み、顔を間近に近付けた。 少しでも動けば触れそうな位の、至近距離にあるお互い。 「? どういうこと?」 のふっくらとした瑞々しい唇が、ゆっくりと動く。 カカシのそれと触れそうだった。 お互いの目と目が見つめ合う。 その引力に引かれて、理性の糸が途切れそうだった。 もうダメだ。 「こういうこと!」 カカシはをベッドに押し倒し、馬乗りになってそれぞれの手首を掴んで押し付けた。 「? 何?」 は訳が分からず、キョトンとしてカカシを見つめた。 月光と星明かりが照らすの姿が、眩しかった。 散らばる絹糸のような滑らかな長い髪が、妙に艶めかしい。 カカシは益々昂りを感じた。 もうどうにでもなれ。 糸の切れる音がすると同時に、カカシは己の唇をの唇に押し付けた。 貪るように、の唇を吸い取る。 「・・・ん・・・っ、ふ・・・っ・・・」 角度を変えて、何度も何度もの唇を求めた。 時折漏れるの息が、カカシを益々加速させた。 柔らかい感触を堪能すると、唇を割らせて、己の舌を侵入させる。 の舌をからめ取り、愛撫する。 「・・・んふっ・・・ふぁ・・・っ・・・ぁふっ・・・」 の甘い喘ぎ声が、カカシの思考を狂わせた。 もう止められない。 口腔内をくまなく蹂躙し、溢れた唾液を飲み込むと、再びの舌をからめ取った。 重なる肌と肌の体温が、衣越しでも熱く伝わってきた。 何度も何度も口付けを繰り返し、に息付く間を与えずに再び口腔内を蹂躙する。 カカシは、下腹部の中心が益々熱く昂ぶっていくのを感じながら、の甘美な唇を何度も味わった。 最初は驚いて目を見開いていただったが、カカシの熱いその行為に身を委ね、次第に瞳を閉じていた。 どれくらいの時が過ぎただろう。 カカシの口付けは留まることを知らず、いつまでもを求めていた。 まるで吸い付いて離れなくなってしまったかのように、2人の唇は重なり合っていた。 そしてチュッと音を立てて離れると、カカシは深く息を吐いて吸い込み、直ぐ様の耳元に顔を埋めた。 耳の裏から首筋にかけて、ゆっくりと、熱く舌を這わせて愛撫する。 カカシのを求める行為は、止まりそうになかった。 今まで自制してきた全てを、思いを、にぶつけた。 呼吸が自由になったは、大きく息を吐き、そして吸い込んだ。 「・・・っ、カカ・・・シ・・・せん・・せぇ・・・っ?」 の言葉に、ハッと我に返るカカシ。 ビクンと身体を震わせた後、そっとの首筋から顔を上げた。 「カカシせんせぇ?」 相も変わらず、純粋な瞳でカカシを見つめる。 潤む瞳が、艶やかな唇が、艶めかしかった。 「ゴ・・・ゴメン・・・」 カカシは重ね合わせていた身体を起こし、きつく握り締めていたの手首を解放した。 「どしたの・・・?」 「ゴメン・・・やっぱり酔ってるみたいだ、オレ。頭を冷やしてくる」 そう言い残すと、カカシはベッドから下りて寝室を出て行った。 カカシはパジャマのまま外に出て、家の屋根の上に寝転がっていた。 普段は吸わない煙草を燻らせながら、満天の星空を眺める。 『そう言えば、忍服以外で家の外に出るのは久し振りだな・・・ま、こんな時間誰もいないからいいか・・・屋根の上だしな・・・』 自分を止めることが出来なかった。 酔っていたとはいえ、あんなにまで思考が狂うとは思わなかった。 沈着冷静であることが自信だったのに、これ程まで歯止めが利かなくなるとは思っていなかった。 「参ったな・・・」 はあの行為をどう思ったのだろう。 果たして、何処まで理解しただろう? 「もっと段階踏んでいくつもりだったのにな・・・何を焦っているんだ、オレは・・・」 暫く屋根の上で色々反省しながら思慮に耽っていたが、流石に夜も遅かったので、飛び降りて窓から居間に戻った。 ソファに横になっても、寝付けなかった。 下腹部の疼きは未だ治まらない。 『オレは・・・を・・・』 その先の言葉はまだ言えない。 酔った勢いだった為、はっきりと確証が持てない。 『でも・・・』 脳裏に浮かぶは、汚れを知らないの愛くるしい笑顔。 闇の中だというのに、とても眩しかった。 大切な思い出すら掠れる程、との口付けは甘美だった。 いや、掠れた訳ではなかった。 そこにデジャビュがあったのに、気付かない程カカシは濃厚な口付けに夢中だった。 『・・・オレはオマエを・・・』 隣室から流れてくるのチャクラの心地好さに身を委ね、襲い来る睡魔に吸い込まれていった。 カカシはを抱いた。 狂おしい程に抱き壊した。 ・・・・・夢の中で。 目覚まし時計の音にハッと目を覚まし、毛布を捲って確認し、カカシは赤面する。 夢の中で蹂躙するなんて、10年振りだった。 「10代のガキか、オレは・・・」 そして冷静に振り返る。 あれ程酒を浴びたのに、二日酔いにはなっていなかった。 のチャクラが癒してくれたのだ、と言うのは分かった。 そしてのことを思う。 酔っていたとは言え、記憶は失っていない。 が、酔いに任せて犯してしまった行為に、激しく自己嫌悪する。 「オレもまだまだ修業が足らんな・・・」 着衣を全て脱ぎ捨てて洗濯機に突っ込み、セットして、忍服に着替えると、カカシはそっと足音を立てないように寝室に入った。 はあどけない顔で眠っている。 カカシ人形を抱き締め、幸せそうな寝顔だった。 『そんなにオレと寝たいのかな・・・』 でも、そんなことをしたらもう歯止めは利かない。 この思いはもう止まらない。 暫くの寝顔を見つめ、口布をずらしてそっとの頬に口付けを落とし、カカシは出掛けていった。 戻ってくると、ドア越しに味噌の香りが鼻をくすぐった。 「あ、おかえりなさ〜いvv」 花のような笑顔で、カカシを出迎える。 すっかり朝食の用意が出来ていた。 「起きてたんだ、。昨日遅かったから、まだ寝てればよかったのに」 何となく気まずくて、目を泳がせながらテーブルに着く。 「だって、カカシせんせぇのゴハン作りたかったし」 ニコ、と微笑んでも向かいに座る。 昨日はゴメンね。 喉まで出かかった言葉が、そこから出てこなかった。 仕方無しに黙って食事を摂っていたが、を見ると、何やらご機嫌そうに食べているので、気は悪くしていないのかな、と思う。 帰ってきてから謝ろう、とカカシは食事を平らげ、食器を流しに運んだ。 いつものように、のチョーカーにチャクラを練り込み、今日も一日が外に出られるようにし、洗面所で歯を磨いて戻ってくると、は洗い物を終えていた。 「じゃ、オレもう行くよ」 どことなく、いつもよりぎこちない。 「あ、カカシせんせぇ、ハイ、お弁当」 ぱたぱたと駆け寄り、包みを差し出す。 「あ、あぁ、いつも有り難う」 ふと、カカシはキッチンに料理と、大きな弁当箱が置いてあるのが目に入った。 「あれ、今日も忍者ごっこ? アカデミーあるよね、今日は」 「あ、あれですか? えへへ、昨日イルカせんせぇに色々教えてもらったから、そのお礼のお弁当なの」 「お礼?」 「うん。何かお礼しますって言ったら、一緒に昼食をって言うから、奢るんじゃ味気ないし、折角だから手料理をって。今日はイルカせんせぇとお昼食べるんだvv」 ニコ、と微笑む。 テラスで空を眺めながら食べたら気持ちいいよね、と笑う。 「そうなんだ。・・・ゲンマ君には?」 「ゲンマさんには、いつもお世話になってるから、たまにご飯作りに行ってるよ。合鍵貰ったから、ご飯作ってきて、それからこっちに帰ってきてるの」 「合鍵?」 イルカ先生とご飯食べるくらいいいや、と思ったカカシだったが、ゲンマとのことを聞き、途端に不機嫌になった。 「ねぇ、今度3人で晩ご飯食べようよ。作るだけで一緒に食べないから、ゲンマさん1人だし、それって寂しいよ。今度呼ぼう?」 ぴと、とカカシの腕に絡まって見上げる。 「・・・そのうちね」 明らかにぶすくれた表情で、カカシはの腕を振り解き、じゃ、行ってきます、と出ていった。 「・・・? 変なカカシせんせぇ。どしたんだろ?」 暫く考え込んだが、すぐに気持ちを切り替え、楽しそうに弁当の続きに取り掛かった。 午前中、はアカデミーの授業を受けた後、昼休みになると、職員室に顔を覗かせた。 「イッルカせんせぇ〜♪ お昼食べに行こvv」 「あ、さん! 今行きます!」 顔を真っ赤に赤らめ、頭を掻きながらイルカはの元へやってきた。 階段を上っていき、テラスに出て、は弁当を広げた。 「やぁ、美味しそうですね。感激だなぁ」 頬を掻きながら、イルカはあせあせと腰を下ろす。 「えへへ。お口に合うか分かりませんけど。どうぞ召し上がって下さい」 「いただきます!」 品数豊富で豪華な食事を前に、嬉しそうに口に運ぶイルカ。 「美味い! 美味しいです、さん」 「良かった。どんどん食べて下さいねvv」 言われるまでもなく、ガツガツと次々食べていくイルカ。 食べっぷりの良さには嬉しくなり、ニコニコと自分も箸を進める。 「さん、料理お上手なんですね。凄いですよ」 「そうですか? 毎日作ってるから、最初はてんてこ舞いだったけど、大分慣れてきたからかな」 「いやぁ、オレも独り暮らしだから料理はしますけど、こんなに美味いのは初めてですよ。有り難う御座います」 「イルカせんせぇのご要望のオフクロノアジってのはクリアしてます?」 「えぇ! こんな家庭料理、料亭でだってお目にかかれないですよ。女性ならではなんですかね」 じっくりと味わいながら、イルカは綺麗に平らげた。 食後のお茶を飲みながら、ふぅ、と一息つく。 「やぁ、こんなに美味くて楽しい食事は久し振りですよ。有り難う御座いました」 「いえ、お口に合って良かったです」 茶を含みながら、はニコ、と微笑んだ。 「こういうのがオフクロノアジって言うんですか?」 あぁ、は意味を理解していないのだ、とイルカは気付いた。 「えぇ、何て言うのかな・・・お袋、つまり母親の手料理って言う意味ですよ。それに近いです」 「あぁ、成程」 「オレは早くに両親とも失って、ずっと独り暮らししてきましたからね。一家の団欒とか、家庭の味、って言うのに飢えているんですよ。久し振りに思い出させてもらえて、嬉しかったです」 「イルカせんせぇもひとりぼっちなんですか?」 「・・・えぇ、12年前に両親とも殉死しました」 寂しそうに、ふっと微笑む。 「・・・って、九尾の妖狐事件で?」 「ご存じでしたか。カカシ先生か火影様から聞いてるんですね。そうです。両親とも忍びで、九尾と戦って散った、英雄です」 「その九尾って、ナルト君の中に封印されてるんですよね」 「・・・! そこまで知ってるんですか?!」 ギョッとして、イルカはを見据えた。 「あ、ハイ。ナルト君って不思議なチャクラ持ってるな〜、身体の中に何かあるな〜って思ってて、火影様にお訊きしたら、教えて下さったんです」 「あ、そうでしたか・・・そのこと、ナルトには言いました?」 「いえ。他言無用って仰られたんで。でもナルト君自身ももう知ってるんですよね」 そう聞きました、とは茶を飲み干す。 「えぇ。図らずも。ナルトも大変なんですよ」 「聞いてます。勇気ある里の英雄って思って欲しいのに、大人達には冷たい目で見られてるって。変ですよね、それって。ナルト君が悪いことした訳じゃないのに」 ぷく、とは頬を膨らませた。 「そうやってナルトを理解してくれる人間が1人でも増えてくれれば、オレは嬉しいです。アイツもずっと独りですから、よかったらたまにメシ作りに行ってやってくれませんか? ナルトのヤツ、放っとくとラーメンしか食べないんで」 手間でなければ、とイルカは請うた。 「いいですよ。ナルト君とももっとお話ししてみたいし。今日にでも行ってみますね」 「有り難う御座います! ただナルト、好き嫌い多いから、ちゃんと栄養ある物を無理矢理にでも食べさせてやってくれませんか。背が伸びないぞ〜とでも脅して」 「あはは。強くなれないぞ〜の方が効きますよ、きっと」 ナルト君も火影を目指してるんでしょ、木の葉丸君みたいに、と笑う。 「でもイルカせんせぇ? イルカせんせぇも一楽に入り浸りだって聞いてますよ」 ダメじゃないですか、とは微笑む。 「ハハ・・・いやぁ、好物なもんで、つい・・・それにしても、カカシ先生は毎日こんな美味しい手料理を食べてるんですね。羨ましいなぁ」 「カカシせんせぇにはお世話になりっぱなしだから、せめてものお礼なんです」 私、カカシせんせぇがいないとこの里で生活できないから、とは微笑んだ。 まるで愛の告白を聞かされているようだ、とイルカは照れる。 「さんはカカシ先生のことがお好きなんですね」 「うん、大好きvv」 極上の笑みで、嬉しそうに言う。 当てられるなぁ、とイルカは思った。 こんなに綺麗で魅力的な女性に思われて、カカシ先生もまんざらではないだろう、と少々羨ましく思う。 家庭を持つのもそう遠くないのでは? とイルカは感じた。 だが、は記憶を失っている異国人。 記憶が戻ったらはどうするんだろう、と思った。 自国へ帰るのか? それともこのまま木の葉の里に残って医療忍者になるのか? イルカは疑問をそのままにぶつけた。 「さんは・・・記憶が戻ったらどうするんですか?」 「え? そうですね、記憶が戻れば能力の使い方ももっとちゃんと分かると思うし、一般常識も知らない馬鹿からも戻れると思うから、そうすればちゃんと忍者になれるなぁって思ってるんですけど、どうやったら記憶が戻るんでしょうね?」 逆に訊き返されてしまった。 「え・・・自国には戻らないんですか?」 「だって、カカシせんせぇと離れたくないもん。一杯術も教えてもらったし、カカシせんせぇと一緒に任務出来るようになるのが夢かな」 ここにいたいです、とはニッコリ微笑んだ。 随分と愛されてるんだなぁ、とイルカは感じた。 「今は頑張ってお勉強です」 絹糸のような長い黒髪が風になびく。 絡まらないようには押さえるが、イルカはの首筋に、赤い痕がいくつかあるのを見つけて赤面した。 今までは長い髪に隠れて見えなかったのだ。 イルカは、カカシとはとうにそういう仲だと思い込んでいたので驚きはしなかったが、目の当たりにしてしまうとどうにも照れた。 「? どうしたんですか? イルカせんせぇ」 キョトンとして、はイルカの顔を覗き込んだ。 「あっ、いや・・・何でもないです。さん、カカシ先生は優しいですか?」 「うん。とってもvv でもね、厳し〜い顔してる時とかの方が好きだな」 「え、どういう?」 「ナルト君達と任務や演習やってる時に時々見せる顔とか、術教えてくれる時とかvv」 でも、家にいる時の優しいカカシせんせぇもどっちも大好き、とは笑顔満面で言った。 「家に・・・」 それはつまり・・・とイルカは、あらぬ想像をして赤面する。 その時、昼休み終了を告げる予鈴がなった。 「あ、もうこんな時間? イルカせんせぇ、授業の準備があるのに、気付かなくってごめんなさい」 バタバタと慌てては片付けた。 「あ、いや、大丈夫ですよ。それより、本当に有り難う御座いました。大したことしてないのに。分からないことがあったら、いつでも訊いて下さいね」 「一つお願い聞いてもらえます?」 立ち上がって、はイルカを見上げた。 「え、何ですか?」 「私はイルカせんせぇより年下だし生徒みたいなものなんですから、名前も呼び捨てで、敬語じゃなくて普通に話して下さい」 ずっと言おうと思ってて、とは微笑む。 「え、そそそ、そうですか? いや、あの・・・若い女性と話すのに慣れてなくて・・・」 「お願いしますvv」 ニコ、と微笑みながら覗き込んだ。 「ど、努力はしますが・・・」 「じゃ、私、午後は病院行きますね。明日また来ま〜す♪」 手を振りながら、は帰っていった。 「参ったな・・・」 頭を掻きながら、立ち尽くすイルカ。 イルカの担任授業の開始が遅れたのは、言うまでもない。 遅い昼食を摂っていたナルト達7班は、満腹になると暫し休憩に入った。 昼食前の演習がハードだったので、ナルトもサスケもそれぞれ離れて木陰で昼寝していた。 当然カカシも昨日遅かった為、木の根元でイチャパラを開いて昼寝しており、サクラは、女のコがこんな所で昼寝するのもどうか、と暇を持て余していた。 何より、今日のカカシが、何だか心此処にあらず、なのが気になり、昨日何かあったのか、訊きたくてウズウズしていた。 つつつ、と足音を立てずに気配を殺してカカシに近付き、隙が垣間見えるカカシに向かって、手裏剣を投げつけてみた。 見事に全部命中する。 「やったぁ!」 が、そこにあるは手裏剣の刺さった木の丸太。 「変わり身・・・?」 ちぇ、と舌打ちする。 途端に寒気が走りぞくりとする。 「何すんの、サクラ」 カカシがサクラの首筋にクナイを突きつけ、背後に立っていたのだ。 「オレの寝込みを襲うなんて、100年早いよ」 ふぅ、と息を吐き、クナイをホルスターにしまう。 「だってぇ、カカシ先生ったら、今日隙だらけだったんだもん。ついさぁ・・・」 「そうか?」 ヤレヤレ、と腰を下ろして幹に寄り掛かり、イチャパラを開く。 「な〜んか、しょっちゅうボ〜ッとしたり、考え込んだりさぁ。それでもしっかり私達のこと見てるのは凄いと思ったけど、いつもと違うんだもん。何かあったの?」 サクラもカカシの傍に座り込む。 「別に何もないよ」 しれっとして頁を捲る。 「うっそぉ! さんと何かあったんでしょ」 「だからオマエは何でそう何でもかんでも絡みにしたがるの。何かと言えばすぐ、、って」 「だって、カカシ先生に何かしらの変化があるのって、いつもさん絡みだから」 「そんなことないと思うけど・・・」 図星だったので、視線を泳がせたのをサクラは見逃さなかった。 「喧嘩でもしたの?」 「してないよ。する訳ないだろ? となんて。ちゃんと仲良くやってるよ」 「ふぅ〜ん。仲良くねぇ・・・どういう風に仲良く?」 サクラに問い質されて、改めてカカシは口が滑ったことに気が付き、顔を背けた。 「どうでもいいでしょ。衝突もなく、しっかりと生活してるって事だよ」 あくまでもカカシははぐらかした。 「毎日愛妻弁当持参だもんねぇ・・・」 「愛妻って、妻じゃないって、だから!」 「似たようなもんじゃない。いずれそうなるんでしょ?」 「そんな予定は無いよ」 ホラホラ、オマエも何処かで昼寝でもしてなさい、読書の邪魔だ、とカカシは素っ気なく突き放す。 一先ず退いて様子を見よう、とサクラは隣の木に移って腰を下ろし、身体を預けて空を眺めていた。 暫し静寂が包み込む。 「あ、そう言えばカカシ先生、さんって私の貸した小説読んでる?」 「ん〜? あぁ、あのお子様小説ね。よく分かんない、って言って、何度も何度も繰り返し読んでるよ。アレ続き物だろ? 理解できたら次の巻を読む、って、最近ようやく2冊目読んでるよ」 「へ〜、まだ2冊目かぁ。でもどうやって理解してるのかしら。読み込めば理解できるようなら、カカシ先生もそんなに苦労してないはずなのにね」 「あぁ、火影様が、にも分かりやすいように、って、男女の心の機微ってのを話して聞かせてくださったら、少しは理解できるようになったようだ」 読書に夢中のカカシは、何気なく受け答えしていた。 「へぇ、火影様もヤルわね。腐っても年の功なのかなぁ・・・」 「こらサクラ、腐ってもは失礼だろ」 「あは、ごめんなさ〜い」 「ま、でも確かに火影様のお陰で、も少しずつ一般的な感情も理解できてきてるし、もうちょっと分かってくれればいいんだけどな」 「さんってオープンな性格だもんね・・・」 「オープンすぎるんだよ。お陰でこっちは大変だ」 「でもあんなに慕われてて、悪い気はしないでしょ」 「そりゃま、ね。嫌われるよりは」 「さんの唇って柔らかい? どんな感じ?」 「柔らかいよ。刺身を甘くしたような感・・・」 言っていてカカシは、サクラの誘導尋問に引っ掛かったことに気が付き、しまったと口を覆うが、後の祭り。 「何を言わすんだ、サクラ!」 「へっぇ〜っ。もうキスは済んでるんだぁ。何よ、進展してないとか言って、ちゃんとしてるんじゃない。ただの同居人とキスはしないわよねぇ?」 チロ、と不敵な笑みでサクラはカカシを見遣った。 「キスしたなんて言ってないだろ! 手が唇に触れたことがあるだけだ!」 「へぇ。手に触れると甘いって事まで分かるんだぁ」 知らなかったな〜、とサクラはニヤニヤ笑う。 またしてもしまった、とカカシは顔を背ける。 「カカシ先生、ホントに里一のエリート上忍なの? 下忍なりたての新人の私なんかの誘導尋問にこんな簡単に、面白いくらい引っ掛かってさぁ。秘密にしたいと思うことをこうも簡単に口を割っていいの?」 「任務だったら絶対に口は割らないぞ! 卑怯だぞ、サクラ。人の弱味に付け込んで・・・」 「弱味なんだ、さんのこと。敵とかが知ったら大変よね。さん危ないんじゃない?」 全くサクラは頭の回転がいい、とカカシは頭を抱える。 「危なくはないよ。は能力的にいったら、もう中忍レベルは超えてる。己の身を守るだけの力はあるよ」 チャクラの量と使える術のレベルで言えば上忍にも引けを取らない、とカカシは言い放った。 「でも、さんの性格を利用されたらどうするの。巧みな話術でさんを捕らえて、機密を渡さなければこの女は返さない! とか」 「それも考慮して、ちゃんと言い聞かせているよ。不穏な輩を識別する能力は持っている。余計な心配しなくていい。は天然ではあるが、オマエと同じで、頭がよくて機転も利く。大丈夫だよ」 敵に捕まるほど馬鹿じゃないよ、とカカシは頁を捲りながら呟いた。 「それならいいけどぉ、でも、捕まった姫を颯爽と助けに行く王子様、なんてことになれば、カカシ先生、さんに益々惚れられそうよね」 今以上の進展望めるんじゃない? とサクラは笑う。 「お子様は大人の世界に余計な首突っ込まなくていいの。オレはオレ、はだよ。進展なんてのは、自然の成り行きに任せるのが一番だよ」 「でも進展は望んでるんじゃない、その言い方じゃ。さんは綺麗で魅力的だから、もてるでしょ。のんびりしていて、他の人に取られないように気を付けてよね、先生」 「分かってるよ」 サクラにはもう何もかもお見通しだから弁解するだけ無駄だ、と、カカシは素直に受け答えした。 満足したサクラは、うん、と伸びをした。 病院を早めに出てきたは、街中を歩いてると、ナルトの姿を見つけた。 「あっ、ナルトく〜ん!」 笑顔で手を振って、駆け寄っていく。 「姉ちゃん! こんな所で、どうしたんだってばよ」 「えへ。お散歩。任務もう終わったの?」 「うん。今日は早めに解散したんだってばよ。これから一楽に行くんだ〜♪」 姉ちゃんも行く? とナルトは笑った。 「う〜ん・・・一楽もいいけど、たまには普通のご飯食べない?」 「普通のご飯?」 ナルトはキョトンとしてを見上げる。 「うん。イルカせんせぇにね、ナルト君はラーメンばっかり食べてるから、たまには栄養のある物を食べさせてやってくれって言われたの。ナルト君のお家に行ってもいい?」 すらりと背の高いは、少しだけ屈んで、ナルトを見つめた。 「え・・・? 姉ちゃん、作ってくれるのか?」 「そう。大丈夫だよ〜食べられる物作れるから。ナルト君のお家に行きながら、近くの商店街でお買い物して帰ろ?」 はナルトの腕を引いて、歩き出した。 「や・・・やっぱいいってばよ・・・オレといると姉ちゃんまで・・・」 「いいからいいから」 戸惑いながら、ナルトはから離れようとするが、はナルトの手を握って離そうとしなかった。 道行く人や店の人のあからさまな冷たい目や態度を気にすることもなく、は鼻唄混じりに歩き、買い物する。 「ナルト君はラーメン以外に何が好き?」 家路を歩きながら、はナルトに尋ねた。 「おしるこ!」 「う〜ん・・・普通のご飯は?」 「オレってばラーメンしか食べないってばよ」 「朝も?」 「朝はパンと牛乳」 家の前まで来て、ナルトは鍵を開けた。 「散らかってるから恥ずかしいってばよ」 「気にしないよ♪ お邪魔しま〜す」 食卓に荷物を置き、は台所に向かって調理を始めた。 「すぐ出来るから、ちょっと待っててね〜」 手際よく調理を進める。 ナルトは所在なげに、食卓の椅子に座っての後ろ姿を眺めていた。 ナルトは生まれた時から両親を知らない。 母親が子供に料理を作ってくれるのって、こういう感じなのかなぁ、とナルトは何だかくすぐったくなった。 ナルトの前に並べられた料理は、どれも栄養満点の、豪華な食事だった。 「すっげ〜〜〜〜」 沢山のご馳走に、目を輝かせるナルト。 「一杯食べてね、ナルト君」 いただきま〜す、とナルトは口を付ける。 「美味いってばよ!」 「そう? 良かった。あ、ナルト君、野菜避けちゃダメじゃない」 「え〜〜〜オレ、野菜好きくね〜もん!」 「ダメだよ〜、好き嫌いしちゃ。背が伸びないぞ?」 「オレってばちゃんと牛乳毎日飲んでるから大丈夫だってばよ」 「あはは。冷蔵庫、ホントに牛乳だらけだねぇ。一杯作っておいたから、明日も温めて食べてね」 冷蔵庫を覗き込み、ラップした料理の皿をしまった。 「牛乳飲んでたら背は伸びるかも知れないけど、好き嫌いしてたら、強くなれないよ? 将来火影になるんでしょ? 何でも食べて、栄養付けなきゃ」 「う〜〜〜〜・・・」 「野菜が嫌いな人にも美味しく食べられるように調理してるから、大丈夫だよ。食べてみて?」 ナルトが食べるのを眺めながら、は洗い物を済ませた。 「姉ちゃんは食わないのか?」 「ん? 私はお家に帰ってカカシせんせぇのご飯作って一緒に食べるから」 「あ、そっか」 恐る恐る、ナルトは野菜に口を付けた。 「あ・・・食える・・・んまいかも」 ムグムグ、とナルトは味わう。 「でしょ? 良かった。いつでも作りにくるから、いつでも呼んでね」 ニコ、とは微笑んだ。 「いいのか? 悪いってばよ」 「そんなことないよ。ナルト君とも仲良くなりたいし、全然迷惑じゃないよ。喜んでもらえれば、嬉しいし」 眩しいの笑顔に、ナルトは照れて食べることに集中した。 「ふ〜、食った食った。満足だってばよ。ありがとうな、姉ちゃん」 満腹の腹をさすりながら、ナルトは茶を飲んだ。 「どういたしまして。一杯食べたね〜。流石に成長期の男の子は凄いなぁ」 作りがいあるよ、とは嬉しそうに食器を洗った。 「なぁ、姉ちゃん。姉ちゃんはいつかカカシ先生と結婚するのか?」 鼻歌まじりのの背中に向かって、ナルトは尋ねた。 「え? まさか」 「しないのか? てっきりするんだと思ってたってばよ」 「無理だよ。そりゃ、カカシせんせぇの傍にいたいな〜とは思うけど、結婚とかより、今の夢は、立派な忍者になって、カカシせんせぇと一緒に任務出来るようになりたいから」 洗い物を済ませ、手を拭きながら振り返ったは、ニコ、と笑った。 「ホントに忍者になるのか?」 「うん。私の夢とナルト君の夢、競争しよっか」 「おぅ! 負けないってばよ!」 暫く歓談し、イルカの話で盛り上がったりしながら、陽が傾いてくると、は帰っていった。 「う〜ん・・・サクラちゃんの話だと、姉ちゃんはカカシ先生のことが大好きだって言ってたけど、カカシ先生もそうらしいって話だけど、それと結婚は別なのかなぁ・・・? やっぱ大人の事情は分からないってばよ」 暫く考え込んだが、カカシ先生にも今度訊いてみよう、と気持ちを切り替え、ナルトは修業部屋に向かった。 え〜、次の第十章ですが、 |