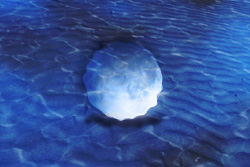
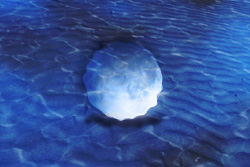
| 【出会いはいつも偶然と必然】 第二十四章 「・・・今何処にいる? 無事でいるか・・・?」 が木の葉の里から消えてから、数日が経った。 ゲンマは手掛かりとなる里の外れの周辺をくまなく歩き回ってみたが、何も見つからなかった。 10年前、一歩違えていたら、自分が迷い込んでいたであろう場所。 忘れもしない。 カカシがずっと炎色の少女を捜していたように、ゲンマもまた、カカシの謎を解くべく、この辺りを散策し続けていた。 何故一緒にいたオレは迷い込まなかったのか。 カカシが選ばれたのには理由があるのか? 知りたいことが多すぎて、必然と身体が動いた。 気まぐれに彷徨く。 何も見つからない。 「やっぱり、研究院に協力してもらうか」 研究院では、まず鉱石の謎を調べてもらっていた。 が戻ってくる時の目印の為にカカシの部屋に置いておこうと思ったが、どうやらはこれを拾ったか何かした為にこういう事態になったのでは、と言うことで、鉱石を分析している。 「どうだ、その後は」 「あ、ゲンマさん。さんを調べている時に、さんがしていたこれと同じ鉱石の腕輪も分析してたんですが、未だ見たこともない成分で出来ていて、完璧な分析は不可能だったんですよ。神の国でしか採れない鉱石なのかも知れません」 「神の国・・・がいたかも知れないという東の果ての国か。もしくは、地上ではない、神の世界か・・・」 ゲンマは鉱石を拾い上げ、光にかざす。 「・・・ん?」 「どうかしましたか、ゲンマさん」 「この鉱石・・・のしていた物とは、違うような気がする・・・。もう一度、詳しく分析してみてくれ」 違う機械を使って、研究員は調べ始めた。 「・・・あ」 ピーッ、と合致したような音がする。 「何か分かったのか?」 「えぇ。ゲンマさんの読み、当たっていましたよ。さんの物の方は自然物でしたが、これは、どうやら人工的な物です。人為的に創り出された、いわゆる装置です。以前に例の場所から迷い込んできたオーパーツの中にあった物で、僅かにこれと似た分析結果が出た部分がありました。同じ物ではありませんが、似た物であることは確かです」 物自体は、分析後に消滅してしまって、無いんですが、と言いながら、鉱石を光にかざす。 「ホラ、この部分。光の中に、僅かに黒い斑点が見えるでしょう? さんの方は、濁りのない光でした。恐らく、さんの物に近くなるように似せて作ったのだと思われます」 「その昔のヤツってのは、いつのだ? 何だったんだ?」 「オーパーツなので確証はありませんが、羅針盤のようだ、と記されています。えぇと・・・5年前ですね。うちはイタチが里抜けをして、追い忍の中で生き残った者が見つけています」 資料を遡りながら、研究員は話す。 「場所も同じ場所なんだな?」 「はい。神隠しのあると言われる場所ですね」 「そうか・・・イタチのやらかした一族抹殺は、確か当時の住民登録で生きているうちはの者の中で生き延びたのは、弟のサスケだけだったが、住民登録の数と遺体の数が合わなかったよな? 逃げおおせたヤツが居たのかも知れねぇし、それ以前に里から抜けていたのかも知れねぇから、真相は分からねぇままだったな」 「あぁ、そうですね。確か、その日以前に行方不明になっていた者も幾人かいましたから、それが、前もってイタチが殺したのか、別の理由で行方が分からないのか、不明なんですよね」 「あぁ」 ふとゲンマは考える。 「・・・は、見たものをそのまま再現できるだろう? 写輪眼のように。もしかしたら、行方不明のうちの誰かが、その神の国とやらに迷い込んでいて、そこにいたが、写輪眼の仕組みを分析して、身に付けたことも考えられる。同じような理由で、西の国にも迷い込んだヤツが居て、写輪眼の能力を利用されている可能性もあるな」 「成程。確か、文明は発達しているようですが、忍びの能力のような、肉体的な異能の者はそういないかも知れませんよね。だから世界中を発掘して回っている、と。さんを攫ったのと同じ方法で、能力者、つまりうちはの写輪眼を持つ者を攫っていったかも知れませんよね」 「それで更に高い能力を持ったが標的にされたって事か・・・ってことは、つまり、はかなりの知名度があるのかも知れねぇな。虎視眈々と狙われる程」 「もしかしたら、能力者の探知機とかあるんじゃないですか?」 「それも考えられるな・・・。よし、此処で話していても埒があかねぇ。能力者集めて例の場所に行って、時空の歪みを見つけよう」 「見つかりますかね?」 「分からん。だが、何もしねぇよりはマシだ。カカシ上忍とサスケを治せるのは、綱手様を除いたらだけだ。綱手様の捜索にも時間が掛かるだろうから、一刻を争う。早くしねぇと、日に日に弱っていくばかりだからな」 手練れの者を幾人か連れ、例の場所に向かった。 「先に行っててくれ。木の葉丸に、の消えた場所をちゃんと示してもらおう」 ゲンマは研究員達を先に行かせ、木の葉丸を捜しに分かれた。 「じじィ・・・オレ、こうやってじじィの好きだった花も採ってこれるようになったぞコレ。すぐに一人前になって、火影の名前を貰うから、天国で見ててくれるか?」 木の葉丸は慰霊碑の前で呟き、空を見上げた。 慰霊碑には、先日採ってきた花が供えられてある。 「じじィ、姉ちゃんが消えたんだコレ。大人達が一生懸命捜してるけど、見つからないんだコレ。じじィ・・・姉ちゃんの行方が上から分かったら、教えてくれよ・・・」 一人前になる。 もう泣かない。 涙を堪え、木の葉丸は空を見上げていた。 上空を鳥が旋回して鳴く。 それを合図に、ゲンマが背後に現れた。 「此処にいたか。家にいねぇから、此処だと思ったぜ」 「楊枝の兄ちゃん・・・」 木の葉丸は後ろを振り返り、ゲンマを見上げた。 「木の葉丸、の捜索に協力してくれるか?」 「も、勿論だコレ!」 「悪ィな。危険な目には遭わせねぇから、例の場所、ちゃんとした場所を教えてくれるか」 「分かった。今から行くのか?」 「あぁ。ご無礼を失礼しますよ」 ゲンマは木の葉丸を小脇に抱き抱え、瞬身の技で消える。 気が付くと、森の中を駆けていた。 木の葉丸には、恐ろしい程のスピードで。 「お、下ろすんだコレ! 自分で行くんだコレ!」 木の葉丸はじたばたもがく。 「悪ィな。急いでるんだ。オマエの足に合わせてる余裕はねぇ」 「う・・・」 木の葉丸は黙って、ゲンマにしがみついた。 悔しいが、このスピードには、とてもついて行けない。 舌を噛みそうだ。 目を開けていられない。 口をきつく結んで、猛スピードに耐えた。 近くまで来ると、ゲンマは木の葉丸を解放し、大地に立たせた。 ふらふらと、木の葉丸はへたり込む。 「悪かった。大丈夫か?」 ゲンマは腰を屈め、木の葉丸に手をさしのべた。 「大丈夫だコレ!」 しかし木の葉丸はゲンマの手を取らず、すっくと立ち上がった。 「分かった。こっちだコレ」 先に来て彷徨いていた者達を呼ぶと、木の葉丸の案内でその場所に向かう。 「此処だコレ。この場所で、姉ちゃんが光に縛られていて、宙に浮いて消えたんだコレ」 正確な場所に木の葉丸は立ち、示した。 「何か分かるか?」 「そうですね・・・奇妙な違和感を感じます。確かに何かありそうですね」 お互いの顔を見合って頷き合うと、木の葉丸を囲んで輪になった。 「お孫様。危険ですので、ゲンマさんの傍へ」 「わ、分かった」 とてとてと、木の葉丸はゲンマの隣まで行き、様子を眺めた。 チャクラが放出され、空間を作る。 かなり長い時間が経った。 時折、光の放出が電波障害のように歪む。 「く・・・っ」 滝のように汗を流し、果てたように放出作業をやめた。 息が荒く、なかなか整わない。 「ダメですね・・・何かをキャッチしそうになるんですが、すんでの所でするりと掻き消えてしまって。時空の歪みは確かに感じたんですが、入口を開けることは出来ませんでした」 「そうか・・・鉱石はどうだ? 何か反応あったか」 輪の中央に置いた鉱石を指し、ゲンマは尋ねる。 「充電切れの機械のようで、僅かに反応しただけです。使用済みで使い捨てってところでしょうか」 「というより、オレ達の頭じゃ使い方を理解できないんですよ。オーパーツと似たようなものですから」 使い方が分かれば出来る筈、と別の男が付け加える。 「オーパーツって何だコレ?」 会話を聞いていた木の葉丸が、きょとんとしてゲンマを見上げた。 「この時代の文明や技術じゃ到底作れないシロモノのことさ。例えば、100年前にテレビやパソコンがある、と言うようなモンだ」 「成程」 「打つ手無しか・・・。どうしたものか・・・」 「やっぱり、さんに自力で戻っていただけるように、祈るしかないですよ」 「それしかねぇか・・・しかし、を攫って拘束できるなんざ、ヤツらの文明は相当なモンだな」 収穫無し、でゲンマ達は戻ることにした。 が消えて半月余り。 相変わらず、は帰ってこない。 カカシも意識が戻らない。 サスケも同様に。 任務に忙殺されながらも、その合間にサスケの様子を見ようと病院を訪れたゲンマは、病室の前でサクラに会った。 手に水仙の花を一輪持っている。 「よぅ。もしかして毎日来てんのか?」 「あ・・・本戦の試験官の・・・」 「不知火ゲンマだ。オマエのことは、からよく話を聞いているぜ」 「アナタがゲンマさん? 私の方こそ、さんからよく伺ってます」 「そうか。廊下で立ち話は迷惑だ。入ろうぜ」 ゲンマは病室の扉を開け、サクラを促した。 サクラは沈痛な面持ちでサスケを見つめ、花瓶に水仙を生ける。 昨日の花が生けたままだ。 「看護師さんに聞きました。さんが、行方不明だって。攫われたって、本当ですか?」 「かも知れねぇってな。真相は分からん。記憶が戻って、国に帰ったかも知れねぇしな」 「まさか・・・! あんなにカカシ先生が大好きで一緒にいたいって言い続けてたのに」 有り得ないです、とサクラは驚く。 「記憶が戻ったとしたら、もしかしたら、記憶喪失の時のことは覚えてねぇって話もあるだろ? もうオレ達は忘れられてるかも知れねぇな」 ゲンマは真摯な顔付きで、寂しそうに呟く。 「そんな!」 じわ、とサクラは涙ぐむ。 「ま、オレは信じてる。はちゃんと、カカシ上忍の元に戻ってくるってな」 泣くなよ、とゲンマはサクラの目尻の涙を指で拭き取った。 暖かい優しい手、とサクラは思った。 が懐く訳だ、と。 「神様がいるなら、恨んじゃいそう・・・だって、カカシ先生とサスケ君が倒れたって言う時に、治せるかも知れないさんが居なくなっちゃうなんて」 これが運命だって言うんなら、切なすぎる、とサクラは唇を噛む。 「そう悲観的になるな。オレ達に出来ることは、信じることだ。に、戻ってきて欲しい、と念じるんだ。そうすれば思いは伝わって、の元にも届く」 オレはそう信じてる、とサクラの頭を優しく撫でた。 そしてサスケの様子を伺う。 「サスケも相変わらず昏睡状態で、変化無しか。イタチの月読は厄介だな・・・カカシ上忍でさえ、太刀打ちできねぇんだ。サスケにはきつすぎたろう。オレはこれからカカシ上忍を見舞ってくる。オレは大抵アカデミーの奥にいるから、変化があったら知らせてくれ」 そう言ってゲンマは、踵を返した。 「あ、はい」 サクラはゲンマの後ろ姿を見送ると、サスケに視線を戻した。 「何でこんな事になっちゃったんだろ・・・火影様がお亡くなりになったばかりなのに・・・これから私達、どうなっていくの?」 答えの返ってこない呟きは、静かに病室に響いた。 ゲンマは、病院からさほど離れていないカカシのアパートまで来た。 鍵を開けて中に入り、寝室に向かう。 カカシの部屋は、今でものチャクラに覆われていた。 それが、が無事であることの証拠だった。 それを信じ、のチャクラに身を委ねる。 「・・・」 昏睡状態のカカシは、ただ眠っているだけのように見えた。 のチャクラがカカシを癒し、危篤に陥らないようにしているのだろう。 人工鉱石は、カカシの部屋の枕元に置いた。 その隣に、写真立てが2つ。 今は亡き4代目と幼いカカシとオビトとリンの写真。 大人になった今のカカシとナルトとサスケとサクラの写真。 は、里が落ち着いたら、カカシとゲンマと3人で写真を撮って、隣に並べて飾りたいと言っていた。 とは、一緒に暮らしていた頃、2人きりで写真を撮ったことはある。 確か、イチャパラに挟んである筈だ。 ゲンマも、焼き増ししてもらった物を、好きな時代小説に挟んで、ポーチに入れて肌身離さず持っている。 そっと取り出し、見つめた。 は今、カカシの危機を分かっているだろうか? 無事なのだろうか? 「早く戻って来いよ・・・・・・皆オマエを待ってるんだぞ・・・カカシも・・・オレも・・・」 戻ってきたら、まず何て言おう。 おかえり、が無難か? それじゃ芸がない。 でも、本当に言いたいことは、決して言ってはならない言葉。 「オレは・・・この先もずっと、カカシととオレの3人で、楽しくやって行けたらいい、なんて思ってねぇからな・・・」 誰も聞いていないからこそ、つい出た言葉。 カカシの顔を覗く。 「カカシィ・・・オマエがいつまでもモタモタしてたら、オレがを奪っちまうからな・・・」 反応はない。 ゲンマは自嘲した。 そしてカカシに囁く。 「早く目ぇ覚ませよ」 ゲンマは捨て台詞を残し、カカシの家を後にした。 階段を下りると、道の先に木の葉丸が立っていた。 「どうした? アカデミーが休校状態だから、時間を持てあましているんだろうが、いつも一緒にいるヤツらと任務ごっこでもして修行してたらどうだ」 木の葉丸の元まで歩いていき、見下ろす。 「ちゃんとしてる。オレは、火影になるんだからな!」 「そうか。頑張れ」 ゲンマが去ろうと歩を進めた時、木の葉丸は何か言いたそうだった。 「? 何だ?」 「・・・姉ちゃんは、まだ見つからないのか?」 通り過ぎたゲンマを振り返って見上げ、尋ねる。 「・・・あぁ。オレ達には、打つ手無しだからな・・・。が自力で戻ってくることを祈るばかりさ」 「オレ・・・姉ちゃんに、あそこで採ってきた花をまだ見せてないんだコレ。じじィに供える為に採りに行ったけど、ホントは姉ちゃんに見せたかったんだコレ。咲いている場所は覚えたから、姉ちゃんが戻ってきたら、一緒に行きたいんだ」 「そうだな。オマエも、祈ってくれ。強い祈りは、必ずに届く」 「分かった! モエギやウドンとか、クラスのヤツらにもお願いするぞ」 皆、姉ちゃんに戻ってきて欲しいと思ってるからな、と木の葉丸は駆けていった。 一方、西へと航海している洋上の大型船。 最深部に、は捕らえられていた。 暗い地下牢のような所で、光の鎖に縛られたまま、何重もの檻の中に閉じこめられている。 「まだ近付けないのか」 背広に身を包んだ、上役らしい人物が看守達に尋ねる。 「は・・・彼女自身が防護壁を張り巡らせていて、洗脳するどころか、近付くことも出来ない有様です。迂闊に近付こうものなら、電流が流れたように身体が痺れ、うっかりするとあの世行きです。大した力ですよ。あの障壁解除装置が効かず、縛り付けておくのがやっとなんて」 「そうか・・・船は今どこを走っている? いい加減本国には着かないのか」 「それが・・・ただでさえ潮流に逆流を走っていて向かい風で船足が遅くなっている上に、彼女の身体が元いた場所に戻ろうとしていて、まるで磁石のように、引っ張られている感じなんです。来る時は一週間足らずで来れましたが、逆流を考えても、本来ならもう着いていい筈なのに、まだ全行程の半分も進んでいません」 「彼女は、自身をその場所から出られないように、特殊な方法で身を定着させているようです。それ故に、そこから出てしまうと、磁石のように戻ってしまう。身を隠すには最適ですね。あの時彼女が強い念派を発しなかったら、未だに見つけられなかったでしょう」 「く・・・っ。折角の聖地の申し子を手に入れたというのに、何も出来んとは・・・誰かどうにか出来る能力者はおらんのか」 「この2週間あまり、手を変え品を変え試してますが、皆あの防護壁に手を焼いています。近付こうとして、使い物にならなくなった者も数名います」 「捕らえることは出来たのだ。彼女とて、鎖に抵抗して力を放出し続けている為にいずれ弱っても来るだろう。時が来るのを待つしかないな」 甲板に上がると、突き抜けるように空は青かった。 は朦朧とした意識の中で、深い闇を彷徨っていた。 カカシとデートの約束をして、向かおうとしていた。 るんるん気分で歩いていたら辺りは突然光と闇が交錯し、出会ったカカシの手を取ろうとしたら、引き離された。 笑っていたカカシが、切り裂かれる。 はっ、とは目を覚ました。 『夢・・・? か・・・夢じゃない・・・』 見覚えのない空間。 幾重もの鉄格子。 力を抑え込もうとするこの光る鎖。 聞き慣れない男達の声。 は背を向けていたので、目を覚ましたことには気付かれていない。 会話から推測するに、攫われたのだ、と分かった。 自来也が言っていた西の国だ、というのも分かった。 攫われてから半月は経過しているようだ。 耳を凝らして会話を聞き取る。 どうやら、の能力を利用して何かを企んでいるようだった。 どす黒い空気がを不快にさせる。 『気持ち悪い・・・胸の奥で危険信号が鳴ってるよ。カカシせんせぇに何かあったんだ・・・この鎖に捕まる前、カカシせんせぇのチャクラが変な感じに弾けたし・・・早く戻らなきゃ・・・』 でも、どうやったらこの鎖から解放されるだろうか。 気付かれないように力を込めてみるが、びくともしない。 益々は消耗した。 は初めて、疲れというものをその身に感じていた。 妙に気だるい。 看守が様子を遠巻きに見守っていた為、は寝たふりをしているうちに、いつの間にかまた眠っていた。 外が見えない上に時計も無いので、日にちの感覚はなかったが、あれからまた数日は経っているのが分かった。 見張りが薄くなる時を狙って束縛から逃れようと試みるが、また幾日経っても、それは叶わなかった。 明るくなると、また新しい人間がやってくる。 『え・・・?! あの目って・・・写輪眼?! まさか・・・』 思わず身体が動き、看守に気付かれる。 「大変です! 彼女が目を覚ましてます!」 「何だと?! 逃げられるなよ」 「どうやら、大分衰弱しているようです。そう簡単には、あの束縛からは逃れられないでしょう」 “写輪眼”を持つ男が、機械的に言葉を紡ぐ。 操られている、というか、洗脳されてしまっているのかも知れない。 『どうしよう・・・うちは一族の人かな・・・サスケ君に仲間が生きているって知らせたい・・・カカシせんせぇにも・・・でも・・・“自分”を見失ってる・・・』 「ソイツは、彼女が隠れていた忍び里から、5年程前に攫ってきた人間だったな。肉体を凌駕している忍びというのは、大変役に立った。まだ生きていたのか」 「まだ使い道はありますから。完全に洗脳されていて、自我を取り戻すことはありませんから、飼い猫のような物ですよ」 「コイツに、術を使わせて彼女に近付けるようにしよう。写輪眼とやらでも幻術とやらでも洗脳は出来るようだが、我々の作り出した装置の方が強大だ。コイツに突破口を開かせよう」 「おい、の申し子、起きているならこっちを向け」 上役の男に声を掛けられ、はゆっくりと身体を動かす。 気だるくて、僅かに動くのがやっとだ。 「この男の目を見るんだ・・・」 はうちはの男を見遣る。 カカシと同じ、写輪眼。 うちはの男は、写輪眼を使い、に幻術をかけようとした。 『・・・イヤ!』 は振り絞って力を込める。 その時、の瞳が赤く輝いた。 「ぐぁぁっ!!」 幻術返しを受けたうちはの男は、その場に倒れ込む。 上役も看守達も、その影響で倒れる。 それから数日、へ襲来は途切れていた。 だが、懲りない彼らは、諦めることなく、日に何度も、入れ替わり立ち替わり、誰かしらがに近付こうとしていた。 が、は無意識にも防護壁を働かせ、必死に抵抗した。 も相当弱ってきていた。 が、相手の方が先に打つ手が無くなったようだった。 陽も暮れた頃。 「あの首のチョーカーが厄介ですね。見て下さい。あしらわれている宝玉が、神の涙です。持つ者の身を守ると言われています。あれが障壁の源になっています。あれを外さない限り、彼女を解放することは出来ません」 「神の涙だと・・・! 彼女が御使いに与える物を、自身で使っているのか・・・! あれは希少価値が高く、大層高価な宝玉だ。それこそ大陸一個買えるくらいのな。何とかして手に入れたい・・・」 はじっと動かずに会話を聞き取っていた。 『早く・・・早くカカシせんせぇの元に戻らなきゃ・・・カカシせんせぇに会いたいよ・・・!』 は、根限りの力を振り絞って、解放を試みた。 「なっ、何だ?!」 の身体が赤く発光し、その眩しさに男達は目が眩んだ。 全員が思わず目を瞑る。 は一層強く力を込める。 鎖が掻き消えるように消滅したかと思うと、幾重もの檻は爆発した。 は解放され、甲板の上に降り立った。 「木の葉の里は・・・どっちの方向?!」 きょろきょろと洋上を見渡す。 辺り一面、漆黒の海原。 右腕の腕輪を額に当て、念じる。 思うは一つ、カカシのことだけ。 「いたぞ! 甲板だ!!」 「逃がすな! 取り押さえろ!!」 男達がに襲いかかってくる。 気が発されたかと思うと、男達は光に弾き飛ばされた。 は完全に、ヤツらの拘束から解放された。 身体に馴染んだ、引っ張られる感覚。 方向が分からなくても、この身体は、カカシの元へと飛んでいく。 「カカシせんせぇ・・・闇の中にいる・・・皆の声も聞こえる・・・カカシせんせぇ・・・今行くからね・・・!」 の身体は、闇の中に掻き消えた。 |